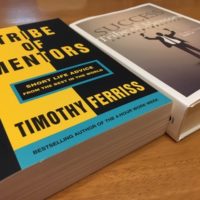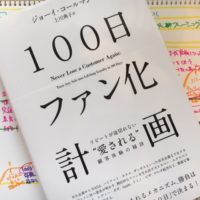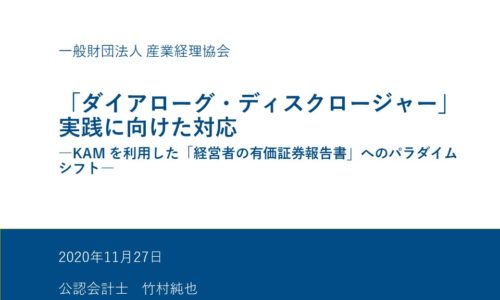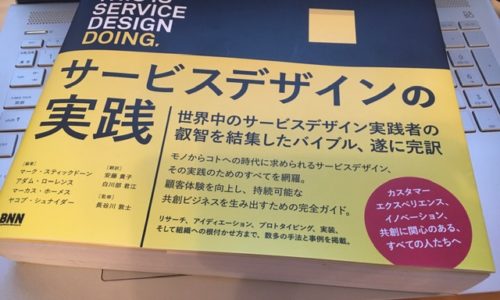先日、大阪に出張に行っていたとき。後輩クンと二人で夕食をとりに、お好み焼き屋さんに入りました。ここは以前に、大阪在中の知人に連れて行ってもらったところ。といっても、カジュアルな普段使いのお店。
そうそう、ここにお昼に立ち寄ることもあるのですが、本当に、お好み焼き定食があるのです。お好み焼きをおかずにして、白米を食べます。炭水化物・オン・炭水化物。でも、お好み焼きの誘惑で、ついつい、この定食を頼んでしまいます。
そんなお好み焼き屋さんは、宿泊先のすぐそば。だから、18時ちょい過ぎに、予約もしないままに席に着くことができました。二人でいくつかつまみながら、お店の様子を見ていると、来るわ来るわ、お客さんが。店員さんも「予約の方ですか~?」と尋ねるほどに、お客さんが集まっています。
そこで、ふと、夕食にお好み焼き屋さんをチョイスする機会がないことに気づきました。東京に住んでいると、自分から、あるいは、一緒にいる人から、夕食にお好み焼き屋さんが挙がることがほとんどない。思い浮かばないといったほうが近いかも。
そんな話を後輩クンにすると、「まあ、東京にはお好み焼き屋さんがあまりないからですかね~」との返答。確かに、身近なジャンルではない印象があります。意外に意識して探さないと、お好み焼き屋さんにたどり着けない状況。
以前に、東京で無性にお好み焼きが食べたいときに、スマホで検索しないと近くのお店がわからなかったことがあったほど。それほど、ふらりと立ち寄るほどに身近ではないのかもしれません。
「じゃあ、お好み焼き屋さんを出そうか」と提案しましたが、笑われて終わり。その理屈から言えば、大盛況のハズ。ということは、お店の数が少ないのが理由ではない。反対にいえば、お好み焼き屋さんを増やせば、夕食の選択肢に含まれる機会が増えるものでもない、ということ。
ここで、お好み焼き屋さんが多いか、少ないかの軸と、お好み焼き屋さんに行きたくなるか、そこまで行きたくなることはないかの軸とで検討してみます。
後輩クンの説に従えば、(1)お好み焼き屋さんが多いから行きたくなるか、あるいは、(2)お好み焼き屋さんが少ないからそこまで行きたくなることはないかのいずれか。しかし、そのほかにも、(3)お好み焼き屋さんが多くでもそこまで行きたくなることはないか、または、(4)お好み焼き屋さんが少なくても行きたくなるか、という状況も考えられます。つまりは、お店の数が要因ではないということ。
この(3)と(4)に照らすと、お好み焼き屋さんを選択するかどうかがキーとなります。ここで推測できるのは、食の文化や習慣が大きなファクターなんじゃないかと。
そもそも、お好み焼きを頻繁に食べる文化や習慣がなければ、いくらお店が多くても、そこに足を運ぼうと思う頻度は少なくなります。反対に、それを食べる習慣があれば、たとえお店が少なくても、探してまでたどり着きます。まるで、スマホで検索していたボクのように。
つまり、それを欲していなければ、いくらお店があっても、お客さんは買わないということ。これは、ビジネスの本質をついていますね。
ある著名なマーケッターが答えた逸話で、次のものがあります。ある人から「ハンバーガー屋を繁盛させるために、何が必要か」と尋ねられたときに、「たったひとつだけの条件が揃っていれば良い」と答えました。その場に参加していた多くの人は、ハンバーグの味なんじゃないか、値段なんじゃないか、お店の立地なんじゃないかと考えます。
しかし、そのマーケッターの答えは、それらとはまったく違います。その答えを聞けば、そりゃそうだと誰もが思うものの、それを聞かなければ味や値段といった点にフォーカスしてしまいます。つまり、的はずれなことをしてしまうのです。
ビジネスで的はずれなことをするのは、効果が得られないものに資金を投下することを意味します。また、それは投下した資金を回収できないことも意味します。すると、ビジネスが持続しないため、早晩にクローズするしか道は残されていません。
そんな道を誰もが好んで選ぶことがないはずなのに、現実には、ハンバーグに使う肉に品質やボリューム、値引きやセット割などに対応してしまう結果、ますます、効果が得られなくなってしまうのです。
その著名なマーケッターは、一体、何と言ったのか。それは誰もが聞いて、納得する答え。それを否定する人は誰ひとり、いないでしょう。彼はこう答えたのです。
「お腹を空かせたお客がいれば十分だ」と。
どうですか。これ以上ないほどに、本質をついた答え。もしかすると、「そりゃ、そうだよ」と呆れているかもしれません。
しかし。しかしです。
その呆れるくらいに本質をついたビジネスをしている人が、どれほどいるのでしょうか。そういう状況を作り出す前に、味やボリュームなどを変えることに一生懸命になっていないでしょうか。
今や、ネットやスマホで、多くの情報を即座に入手できるため、本質ではなく枝葉に惑わされやすくなっているのかもしれません。そんなときに必要となるのは、本質を考えること。どうしても情報が多くなるにつれて、ノイズも増えがちなため、意識して注意する必要があります。
あやうく大阪に立ち寄ったお好み焼き屋さんで、お酒の勢いも手伝って、東京にお店を出してしまうところでした。ボクらが所属する事務所の名前をとって、「仰」(ぎょう)なんてどうかと盛り上がりかけたのですが、幸い、冷静な後輩クンのおかげで、お酒の場の話ですみました。サンキュー、後輩クン。