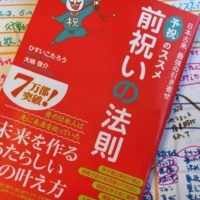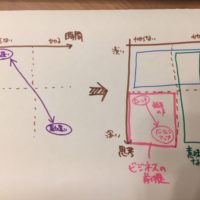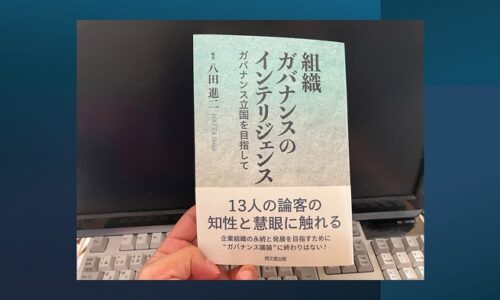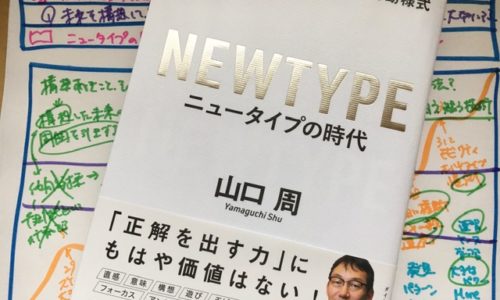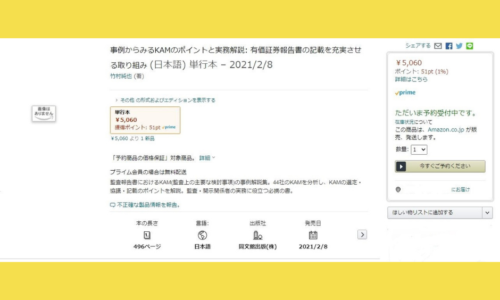あなたの好きな雑誌はなんですか。今朝来た、近々に参加するセミナーのリマインド・メールの真ん中に書いていた。
メールには、当日の持ち物のひとつとして「お好きな雑誌」と記載されていました。そう聞かれて、ボクは固まってしまいましたよ。好きな雑誌として思いつくものがなかったから。
もちろん、定期的に購入している雑誌もあれば、たまに購入する雑誌もあります。仕事とは関係のない雑誌ではあるものの、こうして買っている事実はある。だから、雑誌を読まないワケでもなく、嫌いなワケでもない。
しかし、その雑誌が好きだからかと問われると、困ってしまう。雑誌を買う理由が別のところにあるからです。その雑誌が欲しいのではなく、その雑誌に連載されていたり特集が組まれていたりする記事が読みたいから買うのです。
例えば、ボクはホイチョイ・プロダクションズさんのコンテンツが大好き。ホイチョイの連載記事や特集記事があれば、基本的に購入します。ホイチョイ作品が雑誌に連載されているなら、定期的に買い続けます。
とはいえ、連載が終わった途端に、その雑誌を買わなくなります。なぜなら、その雑誌を買う目的がないから。ホイチョイ作品が掲載されていない雑誌には関心が失せるからです。
そういう意味では、雑誌が醸し出す世界観が好きで買うのではなく、雑誌が提供するコンテンツに関心があって買っていることが理解できます。ホイチョイ作品に限らず、好きな情報がそこにあれば、その雑誌を買う。
これは昔から、そうでした。20代の頃、近所のコンビニで販売されていた女性誌を片っ端から買っていたことがありました。これも、女性誌の世界観に惹かれたのではなく、そこに掲載された飲食店の情報を知りたいからに他ならない。やはり、コンテンツ重視。
反対にいえば、世界観が打ち出された雑誌が少ないのかもしれません。昔、マガジンハウスから発行されていた男性向けファッション雑誌・情報誌の『POPEYE(ポパイ)』がありました。当時の文化に大きな影響を与えていたと聞くため、きっと強烈な世界観があったのでしょう。
では、こういう強烈な世界観を打ち出せる編集者がいなくなったのでしょうか。いや、そうではありません。今だと、幻冬舎の箕輪厚介サンがいらっしゃるとおり、そういう編集者がいなくなったのではありません。NewsPicks Bookシリーズでは、単行本を通じて世界観を打ち出していますからね。
世界観を打ち出せる編集者が、雑誌という媒体にとどまっていないことが原因かと考えています。かつてとは違い、個々人でもSNSを通じて情報を発信できる時代です。オンラインサロンを運営することもできれば、リアルな場でのイベントを開催することもできます。
このように表現する手段が増えたために、雑誌である必要性が低下したと考えます。もちろん、雑誌がダメとは言っていません。雑誌に限らず、読者にリーチできる手段が利用できるために、世界観を提供する媒体が雑誌だけでは限界が生じているのです。
ビジネスモデル的に考えると、編集者が提供する価値を相手に届けるチャネルが、何も雑誌だけにする必要がないのです。SNSというリソースを使って、オンラインサロンを通じて提供することができます。
また、オンラインサロンなどのチャネルを使うほうが、相手との関係性も強く、かつ、満足度も高くできます。すると、金銭的にも支払う額が増えるため、ビジネスモデルの財務的な持続可能性も高まります。むしろビジネスモデル的にシフトしない理由がないのです。
なるほど、ビジネスモデルで考えると、ボクが「好きな雑誌」に困る理由を説明することができました。個人的にスッキリとしました。
だけども、問題はセミナー参加のお題。「好きな雑誌」がない。探さなくちゃ。お題に合う雑誌を探さなくちゃ。セミナー参加のため。