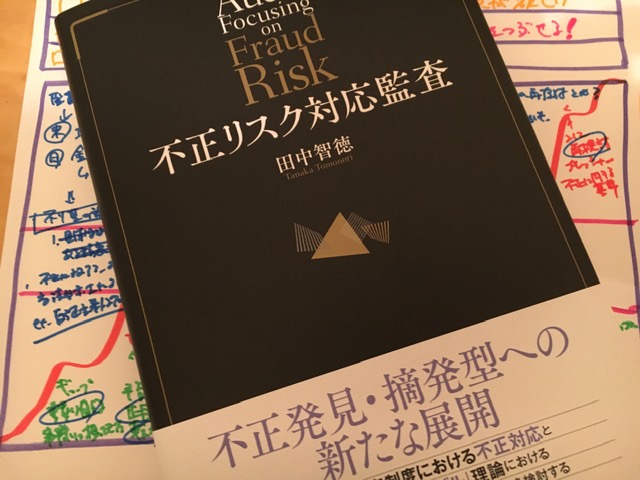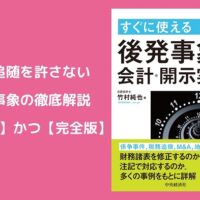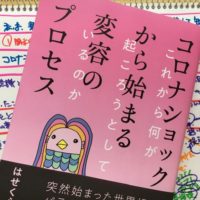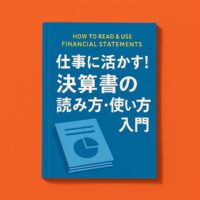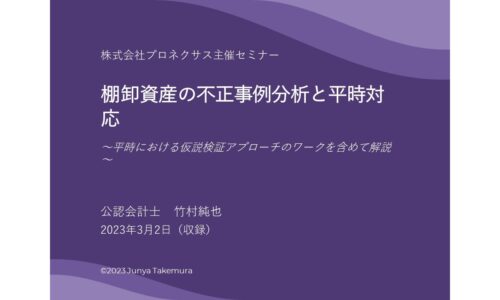会計や監査について研究者が書いた本って好き。エビデンスに基づき一つ一つ立証を組み立てていくため、根拠も含めて納得できます。よく知られているものでも、元資料が調べにくいものがあったりしますからね。
ボクはかなり昔、会計監査における不正リスク対応のメソッドづくりのために、不正調査の方法論について調べていたことがあります。不正リスク対応といえば有名な説に、「不正のトライアングル」があります。これは、①動機・プレッシャー、②姿勢・正当化、③機会の3つの要因によって不正を考えるモデル。
このモデルは、一般に、米国の犯罪学者であるドナルド・R・クレッシー氏によるものと言われています。そこで、このモデルの解説を探したのですが、どれも1ページにも満たない概要ばかり。当時は、深く掘り下げた文献が見つからなかった記憶があります。
しかし、今日、不正のトライアングルを深く掘り下げた文献に出会いました。それは、中部大学講師である田中智徳サンによる『不正リスク対応監査』(同文舘出版)。さすが、研究者の本。不正のトライアングルをはじめとして、エビデンスを積み上げています。
この本で知ったのが、「不正のトライアングル」は、クレッシーによる理論ではないこと。世間ではクレッシーの説だと説明されているのに、驚きの事実じゃありませんか。少なくともボクは驚きました。
もちろん、クレッシーの説が原型となっています。しかし、それは原型であって、「不正のトライアングル」理論のすべてではない。そもそも横領による犯罪を対象としています。クレッシーの説は、その後、アメリカのブリガムヤング大学教授のスティーブ・アルブレヒト氏によって、監査人が会計監査で利用できるモデルに発展していきます。それが今でいう「不正のトライアングル」理論。これについて多くのページを割いて説明されています。
こうした基礎的な事実以外にも、不正対応として学びがありました。最も役立ったのは、質問の相手。監査人が従う監査基準では、経営者不正に対応していくために、経営者に質問することが求められています。また、必要な場合には、その他の企業構成員にも質問すべきと規定されています。
一方で、会計不正の発見手段として最も多いのは、通報です。不正を実行していない人から「こんな不正が行われている」「あの人が不正をしている」と通報されて会計不正が発覚する事例が統計的に多い。
この事実を捉えて、「不正は不正を行った人物からではなく、それ以外の人物から明らかになる」と指摘します。すると、不正の疑義の中心人物から質問するよりも、疑惑の中心人物から最も遠い、関係のない人物こそ、質問相手としてふさわしい。実際、不正調査では、そのような順番で面談を実施しているとのこと。
したがって、会計監査における不正リスクへの対応としては、その他の企業構成員への質問は、必要な場合ではなく、積極的に行うべきと主張します。そのほうが、不正に関連する有益な情報が得られやすいと。
ボクの経験上、2つのアプローチがあると整理しています。今、紹介した質問とは、監査人が能動的に働きかけるプッシュ型のアプローチ。自ら質問していくことによって不正に関連した情報を収集していく方法。
これに対して、プル型のアプローチもあります。監査人が主体的に働きかけなくても、不正に関連した情報が飛び込んでくる状態を作る方法です。いわば、内部通報の相手先が監査人となるようなイメージ。
このプル型のアプローチを実践するためには、この会社の方々と信頼関係を築いている必要があります。信頼されているからこそ、会計不正を知っている人が監査人を頼ってくる。
特に経営者や経営者に近い人たちが会計不正を行っている場合には、社内通報しても潰されたり報復を恐れたりすることがあるから。それでも何とかしたいときに、身近にいながらも外部の人であり、かつ、会計不正を解決してくれると期待できる存在が監査人だから。
10年以上も前に、IPOを目指していた企業で経営者による会計不正が起きたときに、現場の責任者を務めていたボクは、プル型のアプローチ状態になっていました。経理部以外の複数人から、会計不正のタレコミを受けていたのです。
これらのアプローチは、どちらかだけではなく、双方を採用することが効果的。チャネルは1つよりも複数のほうが断然良い。このブログのBusiness modelカテゴリーで、チャネルが1つではいけないと伝え続けてきたことは、会計不正でも同じなんです。
そんな経験も踏まえて、今週、プロネクサスさんで会計不正の対応に関するセミナーを行います。ただし、新型コロナウイルス感染症のため、オンライン受講のみ。在宅勤務でも、このセミナーを受講できます。お申し込みはお早めに。