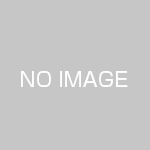2025年7月1日11時40分。会議室に入る前に、氷倉隆は黒嶺尚吾と会った。廊下の窓から差し込む光が、二人の姿を淡く照らしていた。
「おはようございます」
「おはよう。創業記念日なのに悪いな」
氷倉の声には、珍しく申し訳なさが混じっていた。彼の表情は、いつもより柔らかく見えた。
「いえ、どうせ家で寝ているだけですから」
黒嶺は照れ臭そうに頭を掻いた。普段から几帳面な彼らしからぬ仕草だった。彼もまた、いつもと違う。その様子からは、今日の会議への緊張が窺えた。
そう声を交わした直後に、会議室から夜島誠人が二人の間を駆け抜けていった。その表情には、普段の屈託のなさは微塵も感じられない。まるで追われているかのような、切迫した様子だった。彼の額には、薄い汗が光っていた。
「どうしたんだ?」氷倉が呟いたが、誠人にはもう聞こえていなかった。
会議室のドアを開けると、スクリーンには新リース導入プロジェクトの説明資料が映し出されていた。作成者欄の「霧坂美咲」の文字が、資料の確かさを物語っている。
「おお、いい出来じゃないか」
「あいつ、昨日も残業で対応していましたから。相当、力が入っているはずです」
黒嶺が説明資料の完成度を誇らしげに語る中、プロジェクターに繋がれたノートパソコンの傍らに、一枚のメモが目に入った。
「ごめんなさい。今日付けで退職します。霧坂美咲」
たった一行の文字が、13時からの監査法人との協議に向けた空気を一変させた。会議室の空気が凍り付く。
「どういうことだ?」という黒嶺の声が、静寂を破る。いつもの冷静さが揺らいでいるのが分かった。彼の指先が、わずかに震えていた。
氷倉は一瞬の動揺を見せただけで、すぐに冷静さを取り戻した。数々の修羅場をくぐり抜けてきた管理本部長の本領が発揮される。その目には、状況を瞬時に把握し、対応策を練る知性の光が宿っていた。
「とりあえず、霧坂がいない状態でも対応できるように進めよう。俺はこの説明資料を読み込むから、黒嶺は監査法人に共有した資料に漏れがないか、改めて確認してくれ」
11時50分。陽野沙織が会議室に入ってきた時、すでに氷倉は資料に没頭し、黒嶺はノートパソコンの画面を食い入るように見つめていた。待ち合わせの10分前にもかかわらず、異様な緊張感が漂っている。沙織は、何か起きたことを直感的に察知した。
「おはようございます…って、どうしたんですか?」
沙織の明るい声が、この重苦しい空気の中で浮いていた。
「悪いニュースだ」と氷倉が重い声で告げる。彼の声からは、感情が抜け落ちていた。「霧坂が退職した。今日は来ない」
「えっ、だって、今日は監査法人との…」
その言葉を遮って黒嶺は話を切り替えた。「とりあえず、一緒に資料のチェックをしてくれ」
沙織は急いでリュックを下ろし、ノートパソコンに向かった。しかし、彼女の動作には普段のキビキビとした感じがなかった。その手がわずかに震えていた。
「おい、銀座店の事前説明書、開けないぞ。パスワードがかかったままだ」
黒嶺の声が会議室に響いた。その声には、普段の冷静さではなく、微かな苛立ちが混じっていた。
沙織の顔から血の気が引いた。定期建物賃貸借契約の有効性を証明する重要書類。これがなければ、契約は普通建物賃貸借として扱われ、残存契約期間の2年じゃなく、残存耐用年数の12年分のリース負債を計上しなければならない。月額賃料500万円だから、6億円の増額──。その数字が頭をよぎる。彼女の頭の中で、警報のような音が鳴り響いた。
「えっ…課長から『更新がないこと』の事前説明書だって受け取ったんですけど…」
「ファイルを開けなければ、ないのと同じだ」黒嶺の声が冷たく響く。「監査法人から”No documentation, no evidence.”と言われてしまう。銀座店のリース負債が6倍とみなされるぞ」
氷倉が「今日は悪いニュースが続くな」とつぶやいた。その言葉には、諦めと覚悟が入り混じっていた。その横で、沙織は必死に課長に連絡を取ろうとするが、創業記念日で休日のため、連絡がつかない。
「私、外部倉庫に行って、現物を確認してきます」沙織はそう叫ぶと、リュックを背負ったまま飛び出していった。
12時30分になって、誠人が会議室に戻ってきた。いつもなら手にしているはずの肉まんの姿はない。その目は、何か遠くを見ている。昨日の会議室での出来事が、まるで永遠に消えないスクリーンのように脳裏に焼き付いている。美咲の驚きに満ちた表情。床に転がる肉まん。そして、彼女が放った一枚のメモ。
「13時には監査法人がやってくる。黒嶺の確認を手伝ってくれ」
氷倉の声に、誠人は力なく頷いた。彼の瞳には、疲れと後悔が混じっていた。
「は、はい…」
誠人もノートパソコンに向かい、黙々と資料の確認に没頭した。しかし、昨日の出来事を後悔しきれない。そして、美咲がいなくなってしまった現実を、まだ受け入れられないでいた。
「監査法人には、初めから全件オンバランスに疑問があると説明するつもりだった」氷倉が資料を確認しながら呟く。「霧坂の表計算ソフトの結果が、その根拠になるはずだったんだが…」
水ノ原監査役の「素人の判断」という言葉が、皮肉めいて響く。誠人の中で、怒りと悔しさが入り混じった。美咲の作った計算モデルは、素人のものなどではない。彼女の知識と経験、そして細部まで行き届いた思考力が結晶化したものだった。それを否定するなんて、彼女自身を否定するようなものだ。
12時50分、氷倉のスマートフォンが鳴った。誠人と黒嶺は思わずスマートフォンに目を向けた。もしかして美咲からかもしれない──その僅かな期待は、すぐに打ち砕かれた。
監査法人が予定より早く到着したという連絡だった。休日のため、電話で迎えに行くことになっていた来客が、こんな時に限って早めに来てしまう。誠人は苦い思いに駆られた。
氷倉は一旦会議室を出て、監査法人の一行を迎えに向かった。戻ってきた彼は、いつもの落ち着きを取り戻していた。長年の経験から、表情をコントロールする術を身につけていたのだろう。
「すみません、霧坂が急遽、欠席となってしまい、バタバタしています」
事情を知らない監査法人の筆頭サイナーの暁原雅人は、「それは大変ですね」と形式的な返事を返すだけだった。その表情には、興味よりも、仕事を早く終わらせたいという思いが見え隠れしていた。
「では、少し早いですが、皆さん、お揃いのため、協議を始めましょう」
氷倉の声が響く中、誠人の胸には、財務モデルの計算式よりも、昨夜の沙織との抱擁を目撃した美咲の表情が重く刻まれていた。彼女がどんな思いで退職を決意したのか、想像するだけで胸が痛んだ。
会議室の窓からは、創業記念日の晴れた空が見えていた。その青さが、今日という日の異常さを際立たせている。あまりにも美しい空だったが、誠人の心は曇ったままだった。欠けたパズルのピースを、必死に探しているようだった。
監査法人の暁原が資料を開いた音が、会議室に響いた。協議が始まろうとしている。しかし誠人の心は、別の場所をさまよっていた。そこには美咲の姿があった。彼女はどこにいるのだろう。そして、どんな思いでここを去ったのだろう。
時間は容赦なく進み、取り戻せないものが確実に増えていくように感じられた。
(第17話「対峙の時」へ続く)