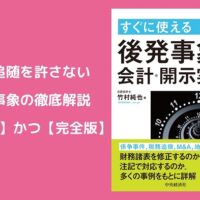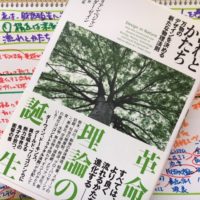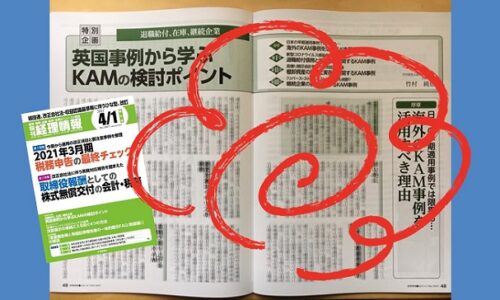物事を解決しようとするときに、いきなり手段から検討しだす状況に遭遇することがあります。「□□が問題なら、○○しよう」という感じで。こんなミーティングに参加したことがあるかと思います。
もちろん、そう話す人の頭の中には、問題の原因を想定したうえで、それに対応する手段を提示しているのでしょう。そのこと自体は悪くありません。
悪いのは、原因の特定が推測でとどまっていること。「~に違いない。だから、○○しよう」と、推測したことを何ら確かめることなく、進んでしまうのです。危険ですね~。
仮説を立てたのなら、それを検証したうえで次に進む必要があります。仮説を検証しないなら、妄想にすぎません。
そう言うと、環境の変化のスピードが早いから、仮説をとことん検証する時間なんてない、と反論があるでしょう。確かに、検証に時間をかけすぎると、タイミングを逸してしまうことにもなりかねない。
しかし、検証することすら省いてしまっては、達成したい状況と違う方向に進んでしまうリスクもあります。検証しないままに違う方向へと進んだ結果、それに投入された時間や労力が報われない。ほんの少しだけ検証していれば、妄想であったことに気づいたかもしれないのに。
だから、現状で何が起きているかを冷静に観察することが必要です。ビジネスの場であれば、顧客に直接インタビューすることもひとつの方法。
会計や監査の世界で、最近、それを痛感したのは、監査報告書に記載することになるKAM(監査上の主要な検討事項)のこと。
意味のある制度導入とするために、原則適用(2021年3月期)の一年前の事業年度(2020年3月期)に早期適用することも認められました。
これは、財務諸表の利用者としては積極的かつ早期の導入を求める一方で、財務諸表の作成者は消極的な意見が多い中での着地点。「そうだよな~。きちんとしたKAMが公表されるには、ある程度の時間も必要だよな~」と考えていました。
ところが、月刊誌「企業会計」2018年12月号に掲載されている、座談会「監査人・監査役等・利用者の視点で考える KAM《監査上の主要な検討事項》の導入」を読んで、ビックリ。こんな発言があったのです。
今のご発言は非常に重要なポイントを含んでいると思うのですが、現状ではKAMにどういう文章、内容を書くかではなくて、ある意味で見出しが重要だということですよね。
これは、財務諸表の利用者の発言を受けて、司会者が話したもの。
KAMは、財務諸表の利用者の理解を助けることを目的としています。KAMの提供先、つまり顧客とは、財務諸表の利用者。その利用者との座談会で、まずは見出しだけでもあれば、財務諸表を作成した企業の経営者との対話のきっかけになるというのです。
ということは、早期にKAMが適用されている状況を目的とするなら、別の方法も考えられます。例えば、2020年3月期からKAMを導入するものの、2~3年の間は何をKAMとしたのか、その見出しだけで良いとする経過措置を設けるのです。
何も適用するならフルフルにしなくても良い。これであれば、利用者も作成者も納得いったのではないでしょうか。だから、顧客から直接、意見を聞くことが大きな意味を持つのです。
まあ、もう決まってしまった話なので今さらひっくり返すことはできませんが、運用面でヒントになります(ちなみに、見出しだけだと規定違反ですので、ご注意を)。一緒によい導入事例を作っていきましょう。
P.S.
今回、紹介した座談会では、KAMの早期適用の落とし所についても意見が述べられています。個人的には別の見解のため、来月のセミナー「上場企業へのKAMインパクト」で説明します。https://www.gyosei-grp.or.jp/images/pdf/seminar_tokyo_20181214.pdf(終了しました)
P.P.S.
イノベーションのメソッドは、やはり、こちら。顧客の観察のステップもちゃんと組み込まれています。本当は教えたくないくらい。実際に体験すると、このすごさがわかります。今、ボクが回すプロジェクトはこれ一本です。
・ハイス・ファン・ウルフェン『START INNOVATION ! with this visual toolkit.〔スタート・イノベーション! 〕―ビジネスイノベーションをはじめるための 実践ビジュアルガイド&思考ツールキット』(ビー・エヌ・エヌ新社)
P.P.P.S.
日本におけるKAM早期適用事例の分析について、当ブログでは「財務報告の流儀」というシリーズ投稿で解説しています。ただ、ワンコインの有料コンテンツとして提供しているため、「お試し版」をこちらで用意しています。
P.P.P.P.S.
2020年3月期に早期適用されたKAMについて分析した結果は、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説』にてご覧いただけます。まずは、こちらの紹介ページをご確認ください。