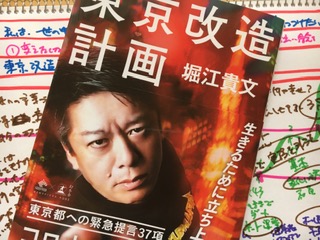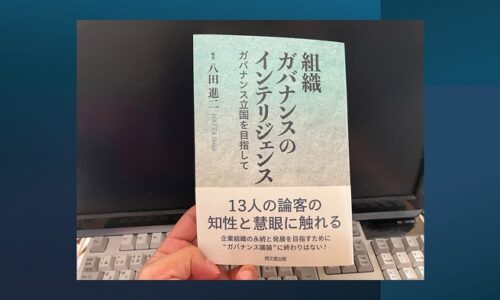人生に一度はしてみたいこと。そのひとつに、広く大衆にリリースされる楽曲への作詞があります。10代の頃、見よう見まねで作詞と作曲をしていたことから、広く世間に受け取って欲しいという想いがあるのかもしれません。
ボクが10代の頃に大好きだった作詞家は、松本隆サンと売野雅勇サン。お二人とも職業的作詞家。自身で作詞や作曲をしないアイドルやミュージシャンに対して、歌詞を提供するのが仕事。
作曲家が先にメロディを作り、その次に作詞家が歌詞を作る「曲先」(きょくせん)が多いと聞きます。曲先で作詞家が大変なのは、メロディが作詞にあたっての制約になること。例えば、本当はこういう歌詞を当てたいのに、音符が足りないとか、メロディの印象と合わないとか。作詞作曲をひとりで手がけていないため、歌詞を優先してメロディを変えられないのです。
そんな制約がありながらも、作詞家は歌の世界観を言葉で創り上げていきます。ボクの整理では、松本隆サンは短編小説系で、売野雅勇サンは、せつなさ系。
松本隆サンの歌詞の特徴は、情景がはっきりと浮かぶこと。特に薬師丸ひろ子サンの『探偵物語』の歌詞は、ひとつひとつの言葉が意味を持っていたり、伏線となっていたりしていて大好きな作品。構成を分析したものを国語の教科書に載せたいくらい。言葉の表現力をこれでもかと理解するには最高の作品。
また、斉藤由貴サンの『情熱』の歌詞もすごい。駅のホームを舞台にした男女の別れを描いているのですが、現実世界の時間にすると数分程度の風景をここまで感情に訴えられるのかというほどに切なさを描写しています。1番のサビの歌詞で、電車が走り出すことで二人が無理やり引き裂かれていく様子は、圧巻。この歌詞がボクを文系に勧めた要因のひとつ。
一方で、売野雅勇サンは、男女の恋愛が結ばれない悲しさやせつなさを描くのが得意。チェッカーズのセカンドシングル『涙のリクエスト』から11枚目のシングル『Song for U.S.A.』までの間、一曲を除き、作詞を手がけます。きっと、チェッカーズのボーカルをしていた藤井フミヤさんのその後の作詞にも影響を与えたように感じます。
また、中森明菜サンの初期のシングルも詞を提供しています。『少女A』や『1/2の神話』、『禁句』、『十戒(1984)』と、少し背伸びをしたような女性の気持ちを描いた歌詞が中森明菜サンのキャラクター作りに活かされています。
こんな風に、まだ歌謡曲として括られていた時代のJポップスの歌詞は、「詩」として成り立っていました。美しくて、小説のような作品として成立しています。しかし、1985年くらいを境にして歌謡曲が衰退していきます。ホラ、今じゃ、歌謡曲なんて誰も言わないですよね。
そんな中で、当時の流行りの歌の歌詞が、詩ではなく、単なる文章や日記のようになっていったのを寂しく感じていたものです。リスナーの立場として歌詞を堪能する楽しみや味わいがなくなっていったのです。
しかし、色あせた歌謡曲あるいはJポップの世界が一変します。それは、1998年の宇多田ヒカルさんの登場。世界観を作るだけじゃ収まらなくなったのです。
ボクは、宇多田ヒカルさんの歌が大好き。歌声もメロディも、そして歌詞も。歌詞は世界観もそうなんですが、歌うときの気持ちよさを考えての母音揃えにいつも感心しています。例えば、サビなどで同じフレーズでは「e」で終わるようにするとか、一番と二番で対応する箇所の母音を合わせるとか。
もちろん、韻を踏んでいる側面もあるかと思います。ラッパーに限らず、他のミュージシャンも韻を踏む歌詞を書いています。しかし、宇多田ヒカルさんのそれは、歌うときの気持ちよさや聴いている人の気持ちよさを重視するために、母音を揃えているようにボクには思えます。
以前、何かの密着系のテレビ番組で、レコーディングしていた歌の歌詞について、「サビの歌詞の終わりは、この母音にしたい」と話していた記憶があります。つまり、意図したうえで楽曲に織り込んでいるのです。
これ、すごいことなんですよ。歌詞に用いる言葉の母音にまで気を使いながら、その世界観を保つのです。世界観だけなら「この言葉で行こう」で済んでいたところ、母音まで気にすると「この母音で表現できる言葉はなんだろう」とさらに作業負荷がかかるのです。
そんな負荷がかかってもピタリとする言葉が見つかれば、まだ救われます。でも、そう簡単には言葉は、しかも、メロディの制約がある中での文字数で見つかるのは至難の技。プロでもアマでも作詞の経験が一度でもあるなら、そんな芸当はなかなかできないことが理解できるハズ。
桑田佳祐サンも、そんな変化を感じてか、歌詞の作り方が変わってきています。最近の歌詞は明らかに母音を意識したつくり。宇多田ヒカルさんのように、聴こえ方や歌うときの気持ちよさを重視しているような印象があります。サザンオールスターズやソロの初期の歌と比べて、作詞のしかたが変化しているのです。
このように、今の作詞は、世界観を作るだけでなく、母音にも気を払って作るのがスタンダード。昔と比べて複雑化しているのです。
それは、ビジネスやキャリアでも同じ。かつての考え方や手法にとらわれていては、最近の状況から外れかねない。常にブラッシュアップしていかなければなりません。
そうそう、ボクの知り合いが、北海道は十勝の「どろぶた」のPR曲『どろぶたのうた』の作詞を手がけました。そんな取り組みをしていると話を聞いてはいたのですが、ついにローンチされたのです。作詞家デビュー、ボクよりも先を越されましたよ。う~ん、ちょっと悔しい。
ということで、作詞の依頼、絶賛、募集中。FORTHイノベーション・メソッドに夢中になっているため、リスナーのことをリサーチしまくって、西野カナさんのようなマーケティングの観点からアプローチしようかしら。おっ、10代の頃の歌詞とはひと味違うかも。