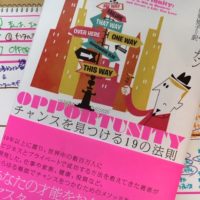言葉ひとつによって、受ける印象は大きく変わる。ボクは、セミナー講師という立場だったり、ファシリテーターという、場の仕切り役という立場だったりと、行動を呼びかける機会が多い。そこでは、どんな言葉がけが良いかに気をつけています。
例えば、お隣の人とのペアワークを行うときに、「誕生日が一番早く来る人」から気づき事項を発表しましょうと呼びかけることがあります。で、話し終わると、次に話す人に交代する。このときに、「では、誕生日が二番目に早く来る人」というようにしています。
何も考えないなら、「誕生日が遅い人」と呼びかけがち。でも、わざわざ「遅い」という言葉を投げかける必要はありません。最初の人と同じようなセリフとしたほうが、変な差がつかなくて済む。だから、ボクは、そう呼びかけます。
ペアワークではなく、グループワークでも同じ。4人くらいで座っているテーブルの中で、気づき事項を共有するときにも、例えば「今朝、一番早く起きた人」から発表するように促します。このときも、他の3人にも同じような言い回しにしています。「では次は、○番目に起きた人から、どうぞ」というように。
こういった言葉の配慮をしていると、セールスレターのときに困ることがあります。セールスレターでは、購入をはじめとした行動を呼びかけるために、心理的に追い込むような言い回しをすることがあるからです。具体的には、緊急性や限定性を謳うような局面。あおりってヤツですね。
とはいえ、これがセオリーだと思い込んでいたため、純粋に使っていました。しかし、どうにも違和感が残ります。そんなときには、プリンセス・ストーリーが有益。先日のブログ「『プリンセス・マーケティング』から呼びかけの前提を学ぶ」で紹介したとおり、女性性を想定したアプローチをすると良い。
そのブログの終わりに、女性性が強いであろう人たちに向けた文章を書いていると話しました。で、この『プリンセス・マーケティング 「女性」の購買意欲をかき立てる7つの大原則』(エムディエヌコーポレーション)という本を片手に、文章を手直ししていました。
その結果は、とても良い。これ、ホントに良いんですよ。ほら、セールスレター的なアプローチだと、「買え、買え、買え」というような迫り方になるでしょ。それが、プリンセス・ストーリーのアプローチだと、「どう? ご興味があれば、どうぞ」と一歩引いた感じで、非常にスマート。実際に使ってみて、心地が良い。
セミナー講師やファシリテーターとして言葉に気をつけている身としても、ピッタリと来ます。セミナーの告知文で心理的に追い込んでいながら、セミナーの現場では言葉に気をつけている、という不整合。それらを一致させることができるのです。これは有り難い。
今、手掛けている文章では、とくかくプリンセス・ストーリーを経験することを重視していることから、これでもかと、そのアプローチに基づく言い回しを多用しています。やり過ぎがいけないのは承知しているものの、経験を積まないと効果も実感できない。今回のトライアルで薄っすらと様子がつかめたため、今後はもう少し、エッセンス的に散りばめられるようにしたいところ。
それにしても、セールスレターをはじめとした行動の呼びかけの作法は、流れが変わってくるかもね。「これでもか、これでもか」とパンチを繰り出すようなランディング・ページにも、飽きられている気もしますし。っていうか、自分自身がそういうページを見るのも飽きてきた。
これからは、プリンセス・ストーリーをベースに文章を書く機会を増やしていくつもり。あなたも、とりあえず試してみてはいかがでしょうか。あっ、この呼びかけもプリンセス・ストーリーがベースだって、お気づき?