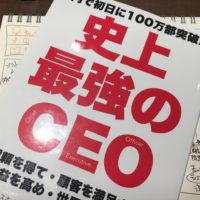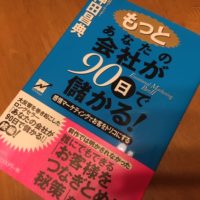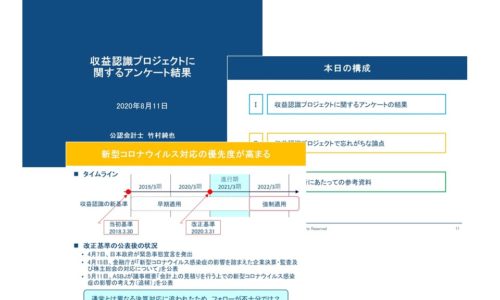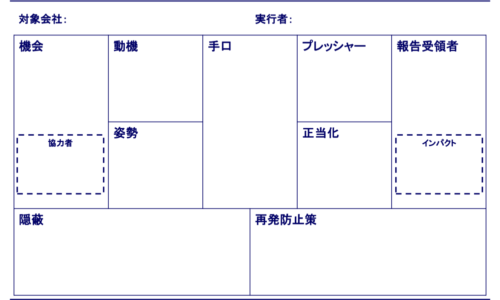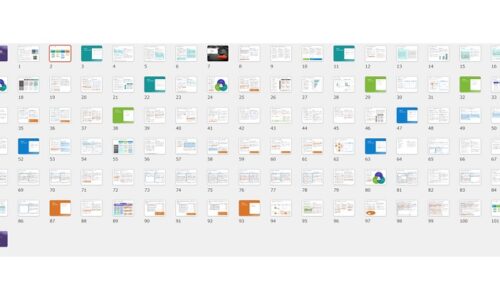音楽の力って、すごいですよね。そのせいか、夏になると音楽の特番が増えてきます。
例えば、2019年7月6日(土)に放映された日本テレビ系列の『MUSIC DAY』や、2019年7月13日(土)に放映されたTBS系列の『音楽の日』など。一視聴者としては、英語と日本語の違いやん、とツッコミたくなりますが、別の番組となっています。
そんな音楽の力といえば、イントロを聴いただけで、その当時の状況や特定の感情を想起させるのが凄い。そういう意味でボクの中で強烈な一曲に、麻倉未稀サンの『ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO』があります。
これは、1984年に発売された、TBS系ドラマ『スクール☆ウォーズ』の主題歌になった曲。イントロ出だしのドラムの連打を聴いた瞬間に、あの当時に引き戻されてしまいます。
この曲は、元々は1984年に公開された映画『フットルース』の挿入歌をカバーしたもの。ちなみに、このカバー曲の日本語詞を担ったのは、ボクの大好きな売野雅勇サン。もう売野ワールド炸裂の日本語訳。そういう意味でも、好きになった歌です。
そんな歌が、高校ラグビーをテーマにしたドラマのテーマ曲であったことから、ボクはこのイントロを聴いた瞬間に、スクラムした様子が思い浮かびます。ビジネスパーソンとしては、スクラムと聞くと、プロジェクト管理法「スクラム」を確立したジェフ・サザーランド氏による『スクラム 仕事が4倍速くなる“世界標準”のチーム戦術』(早川書房)を思い出すかもしれませんね。
昨日のブログ記事『慶良間のウミガメでビジネスモデルを学ぶ』ではありませんが、何かの瞬間に、あるビジネスを思い出させるとは凄いこと。それが耳で聴いた瞬間なら、なお凄いこと。なぜなら、目なら見なければその情報は入ってこないのに対して、耳ならその情報だけを聞かないなんてできないから。
五感に訴えるのは、効果的。このとき、文章だと見なければ、なかったことにできます。しかし、目で見ることは防げても、耳で聞くことや鼻で臭うことは、防ぐことができない。あなた、この時期に、ある店からウナギを焼いた煙の匂いを嗅いだら、もうウナギ・モードになってしまうでしょ。それと同じこと。
耳から入ってくる情報は、受け手が望まなくても、ポーンと体の中に入ってくる。それを受け付けないことができない性質があるのです。例えば、「ピコーン」という電子音を聴けば、任天堂のゲームを思い出すように。
まあ、耳にイヤホンをぶっ込んでいる輩には、効果はないかもしれませんが。それでも、昨日のブログで話した視覚情報よりも、聴覚をはじめとした情報のほうがダイレクトに相手に届きます。
そんな耳から入ってくる情報の性質を活かして、昔、別の監査法人の会計士と、これを営業で活用できないかと話し合ったことがあります。特に低音が体に響くため、営業の現場に持ち込んだスピーカーで低音を鳴らし続けると、営業の成果が得られるのではないかと、冗談まじりにアイデア出ししていたものです。もちろん、現実化することはありませんでしたね。
とはいえ、防ぎようがない聴覚情報をビジネスに活かさない手はありません。ビジネスモデル・キャンバスでいえば、「チャネル」の要素に該当します。否が応でも顧客の体感覚として届く聴覚情報を活用することによって、より認知されやすくなります。
あの「ピコーン」という音のように、これを聞けば、あのビジネス、という構図が成立するほどに認知されれば、ビジネスは持続させやすい。ということは、一度、採用した音はずっと使い続けたほうが良い。継続は力なりとは、こういう局面でも活きてきます。
音によって顧客があなたが提供する価値を認知するなら、どんな音を採用しますか。一度、本気に検討してみる余地が十分にあると思いますよ。ドラムの連打だったり、ピコーンという電子音だったり、ね。