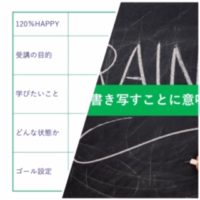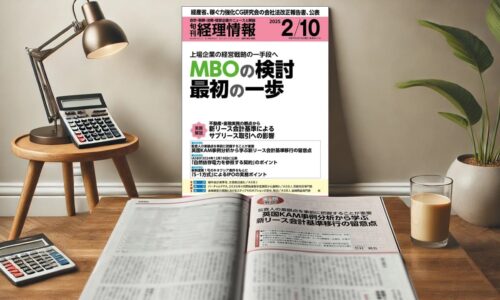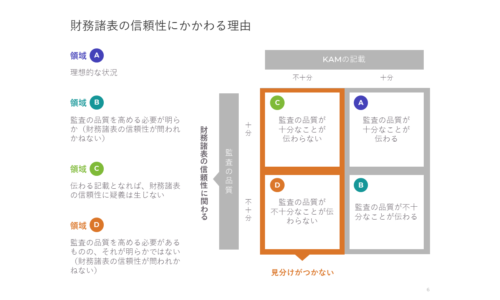ここ最近、人様の原稿を集中的に添削する機会がありました。今日も、原稿のレビューを依頼されたため、気づいた点をコメントしていたところ。
コメントをしていながら感じていたことがあります。それは、文章には、書き慣れているかどうかがハッキリと現れるってこと。これ、手書きのものだろうと、ワープロ打ちしたものだろうと関係ない。また、長文ではなくても、2,3行程度でも現れる文章もあります。
書き慣れているといっても、ただ文章を書いていては、意味がありません。それでは、下手なことを数多く練習していることに等しいから。どう書くべきかの作法を知った上で、それを意識して実践することが大事。
例えば、「~と一般的には考えられる」なんて表現を何気なく使ってはダメ。文章には説明責任が伴います。「一般的にこうだ」と言うのであれば、その根拠を持っている必要があります。統計データや然るべき人が調査したものなど。そういう根拠なく一般論として語るのは、乱暴なこと極まりない。
確かに、「表現の自由」という考え方があるため、何を言おうが構いません。どう主張しようが、それは誰にも止める権利はありません。しかし、その根拠を示さなければ、無責任な発言として受け取られます。それでは、相手にされないだけ。
このときに役立つフレームワークは、トゥールミン・モデル。哲学者であるスティーヴン・トゥールミン氏が、『議論の技法』(東京図書)の中で説明したロジックの型。これに従うことでロジカルな表現になれるのです。
原著の”The Uses of Argument”は1958年に公表されています。この本の登場によって、三段論法がロジックではないことが明確に言語化されたインパクトを与えたもの。だから、競技ディベートを行うときも、その出身者が政治の世界で議論するときにも、このトゥールミン・モデルは欠かせません。
このモデルは、主張(クレーム)、事実(データ)、論拠(ワラント)の3つが最低限の要素。文章やプレゼンなどで伝えようとする内容が、主張(クレーム)といいます。
主張するには、証拠が必要です。それが、事実(データ)。子どもの喧嘩でも、「じゃあ、証拠を見せろ」というでしょ。
主張と事実があっても、それらが関連しなければ意味がない。提示した事実から主張へと関連付けられる要素が必要。それが、論拠(ワラント)です。
ロジックであるためには、この3つの要素が揃っていることが求められます。反対に言えば、これらを揃えていれば、ロジックでもあるということ。ならば、この3つを意識した文章を書けば良い、ってこと。
ボクはディベートを学ぶ過程で、このトゥールミン・モデルに出会いました。これを意識して使うようになってからは、書籍や寄稿で自説を展開することにまったく恐れなくなりました。3つの要素を揃えているため、少なくともロジックは成立しているから。
もっとも、このモデルは正確にいえば、6つの要素で成り立っています。だから、他の3つの要素も使いながら主張を展開しているため、よりロジックが緻密になっています。
また、ディベートの方法論を用いれば、反論のポイントも明確につかめます。ということは、文章やプレゼンで反論ポイントを自ら示し、かつ、その反論を潰しておけば、さらに強固な主張になるのです。
そうそう、論破しようとしてくる人に対して、このトゥールミン・モデルを使うことがあります。ボクは反論ポイントを押さえているため、相手の主張が次々と崩れていきます。それを感じ取ってか、どんどん別の話を展開してくる。
で、ボクが「それ、論点がすり変わってますよね」と返すと、顔を赤くして感情的になって怒り出します。逃げ道がなくなるため、こういう反応が多いです。もちろん、誰それ構わずにトゥールミン・モデルを振りかざしているのではありません。とーーーっても失礼な相手だと判断したときにだけの話。
話を戻すと、文章力を高めたいなら、むやみに書き散らかしてもダメ。然るべき方法論にのっとって練習していくことが大事。これについて思い出すセリフがあります。それは、三谷幸喜サン脚本のフジテレビ系ドラマ『王様のレストラン』でのセリフ。
歌はな、テクニックじゃないんだ、心だ。だけど、心を表現するにはテクニックが要る。
文章はテクニックじゃなく、想いを書くもの。しかし、その想いを表現するにはテクニックが必要なんです。だから、何かしらの方法論を使うべき。
えっ、トゥールミン・モデルをもっと知りたくなったって?
実は、全面改訂する前の版の拙著『税効果会計における 繰延税金資産の回収可能性の実務』(中央経済社)に少し解説しています。9割ほど書き直したため、現在、発売されている<全面改訂版>ではトゥールミン・モデルのくだりもばっさりカットしました。それがどんな解説だったかというと・・・、それはまた、別の話。