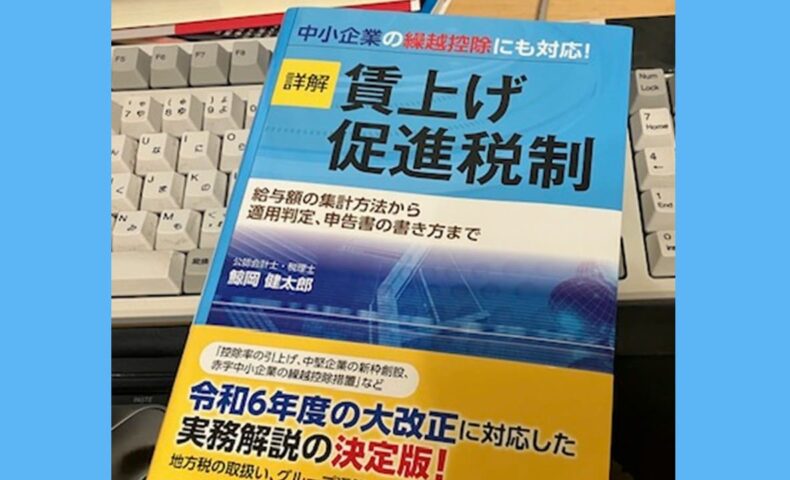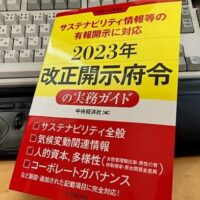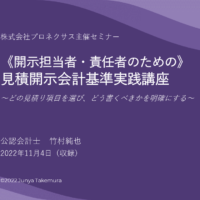令和7年の税制改正大綱では、新たに「防衛特別法人税」(仮称)が導入される予定です。この新税は、法人税額に対して上乗せで課される形となるため、多くの企業にとって財務負担が増加する可能性があります。この背景の中で、法人税の軽減効果を持つ賃上げ促進税制が、改めて注目を集めています。
賃上げ促進税制は、単に法人税の負担を軽減するための措置にとどまらず、従業員への給与引き上げを促進し、かつ、企業の持続可能な成長を目指す重要な政策ツールとして位置づけられています。同税制を活用することで、企業は防衛特別法人税の影響を緩和しつつ、財務戦略に柔軟性を持たせることが可能となります。その結果、賃上げ促進税制は、企業経営における重要な柱の一つとして再評価されています。
しかし、この税制を効果的に活用するには、経営者や経理部門がその適用要件を正確に理解し、実務的な課題を克服する必要があります。この点において、公認会計士兼税理士である鯨岡健太郎氏による『詳解 賃上げ促進税制』(清文社、2024年11月出版)は、実務家にとって極めて有益なリソースとなっています。本書では、賃上げ促進税制の理論から実務的な適用方法までを網羅的に解説しています。特に、次の点で優れています。
【おすすめポイント1】賃上げ促進税制における多部門連携の重要性
賃上げ促進税制の適用には、経理部門単独では完結できない多部門間の連携が必要です。同税制を活用するためには、マルチステークホルダー方針を策定したうえで、それを外部に公表することが求められます。この方針は経営層の承認が不可欠であり、さらに情報管理部門や総務・人事部門との協力が求められます。
本書『詳解 賃上げ促進税制』では、第1編第2章「大企業向けの賃上げ促進税制」において、これらの組織間連携を示唆する図表が掲載されています。経営層や部門間の連携を促進するための実践的な指針が提供されています。
【おすすめポイント2】用語の定義とその解釈の重要性
賃上げ促進税制を適用する際には、税務特有の用語を正確に理解することが不可欠です。たとえば、「給与等」という用語は損金算入されるものに限られますが、これを給与台帳に基づき集計すると税額計算が正確に行われないリスクがあります。本書では、第1編第5章「用語の定義」において、こうした用語の解釈を詳細に解説しています。
特に、実務上頻繁に問題となる用語について具体的な事例が示されているため、現場担当者が迷わず適切な判断を下せるよう配慮されています。これにより、税務処理の精度向上に貢献しています。
【おすすめポイント3】申告書記載の実務的サポート
賃上げ促進税制の最終的な適用は、申告書における正確な記載を通じて完了します。しかし、法定の申告書様式を見ただけでは、どの項目にどの情報を記載するべきか迷うことが少なくありません。本書では、第2編第3章「申告書への記載」において、設例を用いた記載例が豊富に掲載されています。
この章では、申告書作成のプロセスが段階的に解説されているため、記載ミスを防ぐための具体的なポイントや注意事項が整理されています。このため、税務担当者が効率よく正確な申告書を作成するための実践的な手引きとなっています。
ご購入の機会をお逃しなく
防衛特別法人税の導入を控えた今、賃上げ促進税制の重要性は一層高まっています。この適用には、多部門連携の必要性や専門的な知識の習得といった課題があるため、これらを克服するためには適切なリソースの活用が鍵となります。
書籍『詳解 賃上げ促進税制』は、こうした課題に対する最適解を提供する一冊です。経理や税務担当者のみならず、経営層にとっても有用な指針となるでしょう。本書を活用し、かつ、新たな税制環境を前向きに活用することで、企業としての競争力をさらに高めていくことが期待されます。