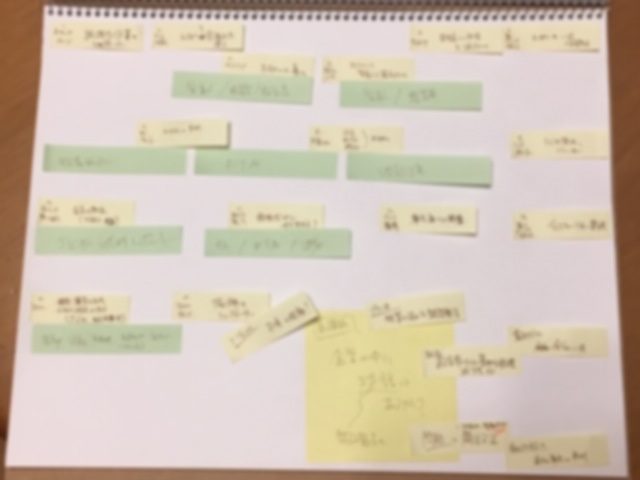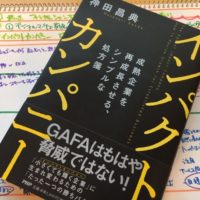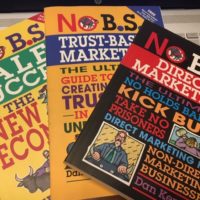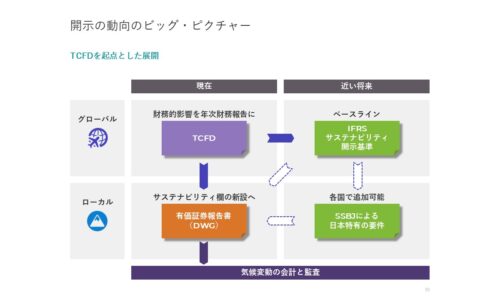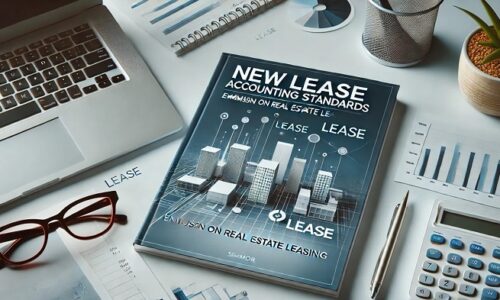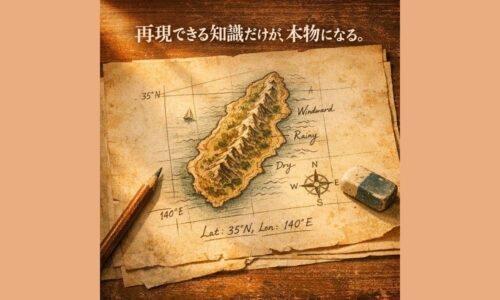何かを学ぶときには順番が大切。そんなことを今日、痛感しました。
今日の午前中に取り組んでいたのは、ある案件についての全体構成。先日、ブログに投稿した記事「ディズニーパリのCMが泣ける理由」では、ディズニーランド・パリのCMについて、売れる映画の脚本術を使って分析したところ。そこで、そのツールに基づいて考えていました。
そのツールとは、「ブレイク・スナイダー・ビート・シート」。ハリウッドの脚本家であるブレイク・スナイダー氏が、著書『SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術』で紹介したもの。売れる脚本に不可欠な15のシーンと、そのタイミングを示したもの。
先ほどのブログ記事で、実際のCMを分析したこと。また、その後に、この脚本術に基づき、1つの研修の構成を見直し、加えて、別のワークショップの構成を新規に考えたりもしました。そうした経験から、この脚本術の使い方とすごさが少しわかるようになりました。
そこで今回の案件でも、このツールを使って全体構成に必要な15のシーンを考えていました。ただ、今日の取り組みは、15のシーンだけではありません。これをさらに40のシーンにまで拡張したのです。
この拡張版のツールは、先ほどの本の続編の続編『SAVE THE CATの逆襲 書くことをあきらめないための脚本術』で詳しく紹介されているもの。今回の案件のために購入しましたよ~。
何が良いって、40のシーンが構成の時点で考えられる点。全体構成を考えるときに、まったくのゼロからよりも、15のシーンが出来ていたほうが遥かにやりやすい。それが、40のシーンまで出来ていると、なおさらのこと。
このブログに掲載した写真が、本日の成果。ぼかしてはいますが、付箋紙が40近く貼り付けられているのがわかると思います。付箋紙が切れてしまったため40枚はありませんが、シーンとしては40を想定しています。ちなみに、右下のブロックは別のメモなので、無視してください。
ここで気をつけたいのが、学びの順番。最初から40のシーンを考えるように説明されると、おそらく取り組んでいなかったでしょう。すべき作業があまりにも多いため、やる気が起きないから。
それを揶揄した場面が描かれていたのが、1995年に放映された、三谷幸喜サンの脚本によるフジテレビ系のドラマ『王様のレストラン』。
レストランのオーナーが朝礼で、シェフたちに対して教訓めいた話をしようとします。最初は「3つのW」や「5つのP」と話していたところ、やがて「37のS」にまで拡張されていくのです。3つや5つなら聞けても、37にまでなると聞く気になれません。
呼びかける相手に聞く耳を持ってもらう、行動を起こしてもらうには、最初は簡単なものが良いのです。だから、たとえ40のシーンを考えることが本来のツールであっても、もっと少ないシーンに絞り込むことで取り組みやすさを出したほうが良い。イントロダクションやショートバージョンといった形で、効果が確かめられるほどの水準で簡単な枠組みを示すのです。
ワークショップも同じですね。最初は簡単な枠を示す。それで一度、体験してもらった次に、拡張したものを教える。それに取り組んだときの不明点を解消したうえで、もう一度やってみる。この順番が正解。
今日の取り組みは、その順番でいうと、まだ2番目の段階。よし、これから細かな点もフォローして仕上げていきます。あなたに感動してもらえるように。