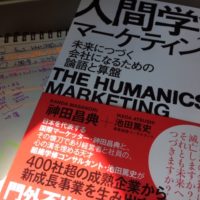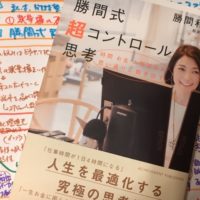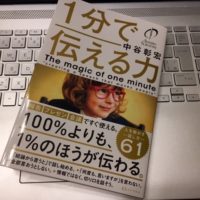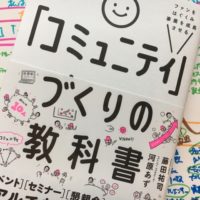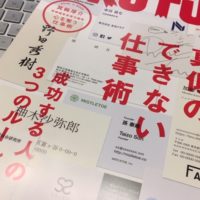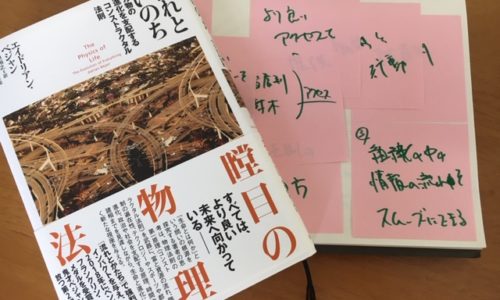参加者の成長を促すことを目的としている講師にとって、研修アンケートによる満足度調査は何の意味もない。そう、1ミクロンも。
ボクが属している会計士業界では、日本公認会計士協会から「監査品質の指標(AQI)に関する研究報告」なるものがリリースされています。そこでは、監査の品質を図る指標のひとつに、研修の満足度を測定したアンケート結果が挙げられています。
きっと、満足度が高い研修は質が高いと考えているのでしょう。一般的にも採用されている指標ですし。数値化されていることで、あたかも客観的に研修の効果を測定できていると感じても仕様がない。
そういう意味では、理解度テストなんていうのも同じ。これもきっと、参加者が理解できたら研修の目的を達成していると考えているのでしょう。何割が出来ているから合格点とか、わかりやすいので受けが良い。
これらはいずれも、研修を行う側にとって都合が良い指標。ほら喜んでもらえた、ほら理解してもらえた。だから、研修の効果があったと説明したい。それは講師側の都合もあれば、研修を提供する組織側の都合もあるでしょう。あるいは、そうした研修サービスを事業として提供している会社の都合もあるかもしれません。
研修の目的に照らせば、これらでは測定できないことがわかります。果たして、研修をすることで参加者に喜んでもらうことがゴールでしょうか。研修をすることで参加者に理解してもらうことがゴールでしょうか。
研修は、ある行動を呼びかけたうえで、それを実践してもらいたいから提供されます。いくら喜んでもらっても、その行動を実践してもらえなければ研修を行った意味がありません。また、いくらその場で理解できていても、行動を起こすべき場で実践してもらえなければ、やはり研修をした意味がない。
このように、研修の目的を、呼びかけた行動の実践とする限り、アンケート調査や理解度テストなどでは測定できないのです。
ここで、理解していなければ実践できないだろうという反論があるかもしれません。確かに、何も理解していなければ、実践することはできません。しかし、大人の学びの場合には、必要な状況でその行動が実践できれば何の問題もない。詳細を暗記していなくても、その場で解説を読み返せば済む話。
そもそも、たかだか2時間程度の研修で、呼びかけた行動を完璧にできるようになるなんてことはない。講師ができることは、気づきを与えるだけ。呼びかけた行動の必要性を理解してもらい、それが何かに触れてもらい、少し取り組んでもらうのが精一杯。あとは、参加者にその後、継続して取り組んでもらうことで身につけてもらうしかない。だから、それを継続させていく仕掛けも必要。
こうした背景があるため、ボクが所属している法人の東京事務所では、ボクが研修担当になってからは研修アンケートを一新しました。従来は満足度調査を5段階評価していたところ、何を学んだかを記載させる形式に変更したのです。
研修は毎月開催していることから、定点観測ができるため、参加者の学びの姿勢がよく分かります。「この人はどんな研修でも学びを得ることができている」「この人は自分が望む形で提供されない限り何も学べない」ということが手に取るようにわかります。
実際、こうした取り組みに否定的だった人もいます。あるとき、そんな人に研修の講師をお願いしたことがあります。そのときに、何を学んだかの研修アンケートをフィードバックしたところ、「確かに、誰が聞いていたか聞いていなかったかが、はっきりわかるね」と、満足度調査ではない形の研修アンケートの意義について体感していただけたことがありました。
このような取り組みを行っているからこそ、参加者が常に同じではない研修やセミナーのアンケートにネガティブな回答があっても、それは参加者の学びの姿勢が原因のこともあると理解できます。そういう人は、どんな研修やセミナーを受けても否定的な回答しかしません。
講演や研修講師を数多くこなしている中谷彰宏サンも、著書『人は誰でも講師になれる』(日本経済新聞出版社)の中で、アンケートを気にしすぎないと注意喚起しています。
もちろん、ネガティブな回答を無視するのではなく、そういう見方もあるのだなと受け止めればよいだけ。心の奥底まで受け入れる必要まではないのです。回答の内容を次回に反映させていくかどうかを冷静に判断していけば良いのです。
となると、研修の真の成果とは、こちらが呼びかけた行動を参加者が実践できているかどうか。その観点からいえば、1回こっきりの研修ではなく、その後もフォローできる環境を整えるほうが大事。
最近ではFacebookのグループを活用しているケースもあります。ただ、SNSでの書き込みに慣れていない人が多いと盛り上がらないのが難点。それだったら、研修の場を複数回提供するほうが良い。最初の研修の次は、希望者だけ複数回の研修に来てもらう流れ。こうして興味をもった人やできるようになりたい人を応援していくのです。
やっぱ、サステナビリティですよ。研修も。