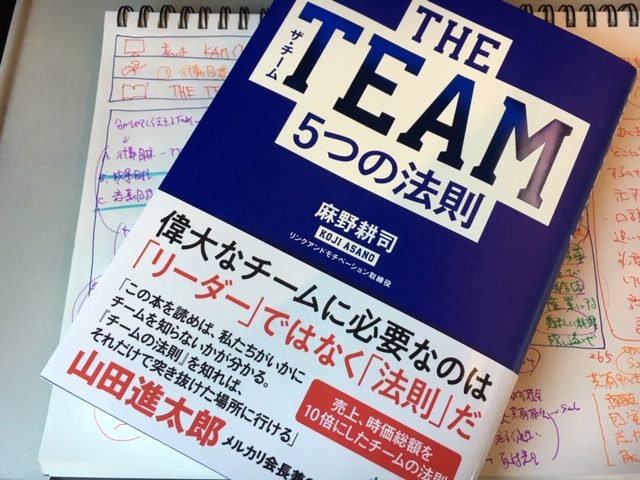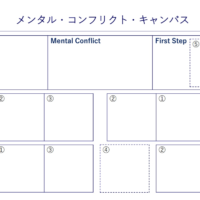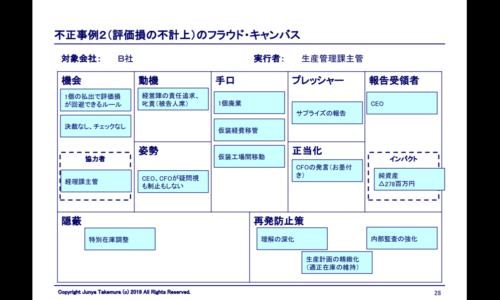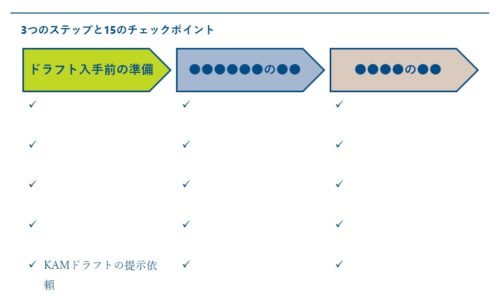来週、とある所でワークショップ型のセミナーを行います。ボクはいつも通りに、ファシリテーション全開で進行していくつもり。
ただ、そこに参加する人の多くは、おそらくビジネス系のワークショップセミナーを受けた経験が少ない方。そこで実施するグループワーク、いわゆる助け合い学習に慣れていないのです。
すると、いつもの調子で進めていくと、拒絶感を覚えられかねない。セミナーを受けたことによる気づきが得にくかったり、気づきの範囲が狭まったりと、ワークショップの効果が少なくなる可能性があるのです。
そこで来週のワークショップ型のセミナーでは、いつも以上に慎重にことを運ばなければなりません。そんな中で、チームビルディングに関する本が発売されました。何というグッドタイミングでしょう。
その本とは、組織変革についてコンサルティングしている麻野耕司サンによる『THE TEAM 5つの法則』(幻冬舎)。チームづくりに特別な能力や経験は不要だと説きます。必要なのは、5つの法則を実践していくことだといいます。
ワークショップ型のセミナーでは、4人程度のグループを作って運営していくことを想定していました。このメンバーの中にワークショップに不慣れな方もいたとしても、チームとしての力を高められるなら、十分な効果が得られると期待できます。単なる経験談ではなく、学術的な知見の裏付けが示されているため、再現性があるのです。
安心したのは、今までのファシリテーションの考え方に大きな違いがなかったこと。ただ、細かな点で、十分にやりきれていないことがあり、また、新しい気づきもありました。
やりきれていない点としては、心理的な安全が不足していたこと。特に、ワークショップそのものに慣れていない人が受講するため、この点への配慮はもっと徹底して行うべき。
当日の映写スライドでは、セミナー冒頭で注意喚起していたつもりでした。しかし、心理的な安全を確保するためには、至る所で何度も繰り返して強調するように変更するのが良い。そんな風にスライドを手当てすべきことが明確になりました。
この他に気づきを得たのは、チーム力を高めるために共有すべき4点。それは、「経験」「感覚」「志向」「能力」。これらを話し合うことで、相手に伝わり、感情を動かすコミュニケーションができるといいます。
ボクのワークショップ型のセミナーでは、隣の人と話し合う時間を何度か設けています。これだけでも効果はあるものの、経験、感覚、志向、能力の4つを引き出すような観点を取り入れたなら、チーム力をさらに高められそうです。これは来週、挑戦したい事項でした。
さらに、この本には、モチベーションタイプの別に反応しやすい言葉も紹介されています。これらのタイプ別の言葉をカードにして、隣の人と話し合った直後に、今、話していた人の姿勢をこのカードで示すエクササイズなんてのも面白そう。これも取り入れてみたい。
いろいろとアイデアが湧いてきます。この本には、ファシリテーターにも大いに役立つヒントが溢れていますね。本当はあまり紹介せずに自分のものにしたいため、あなた以外の人には内緒ですよ。