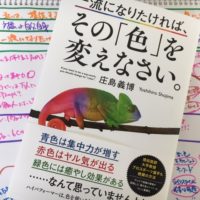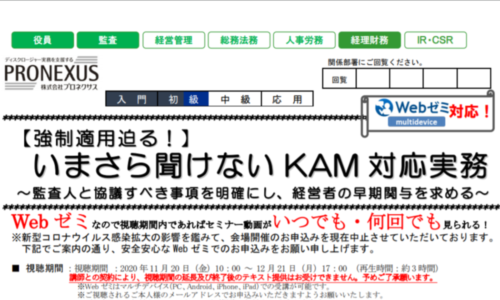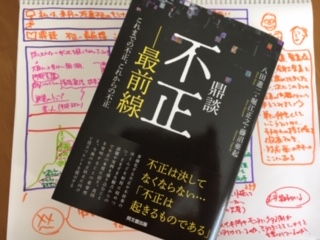10月1日の今日は、東京都が制定した記念日である「都民の日」。都立や都内の公立の学校では、お休みになるところがあります。また、都内の会社でも、この日を休みとして設定しているところもあります。
ボクの所属する事務所では、お休みでした。都民の日だからではなく、会計監査の最も多用な時期であるゴールデンウィークの出勤日の振替休日に指定されているため。
ちょうど丸一日、予定を入れていなかったため、滞っていた商業出版の執筆にあてました。書くための素材を用意していたこともあって、随分と捗りましたよ。
今日は、従来とは違った方法で執筆をしてみました。いつもは、ライティングする前に、記載する内容の構成をしっかり決めてから、書き出していました。構成を書き出した手書きのメモ帳を左に置きながら、パチパチとキーを打っていく。
今回、試してみた方法は、まず、パソコンにモニターをつなげて、ダブル画面の状態にしています。一方の画面には音声入力のソフトを立ち上げ、また、もう一方の画面には参考資料のファイルを立ち上げます。記載する内容の構成を見出しレベルでメモ帳に手書きします。このメモ帳と資料のファイルの画面とをチラ見しながら、パソコンに向かって話していく。
ここで気づいたのは、構成はしっかりと決めなくても大丈夫なこと。構成を事前に決めておく理由は、ライティングし終わった後に書き直す手間をなくすため。この手戻りが執筆作業において非効率なこと、極まりない。
構成を決めておけば、大きな手戻りは生じません。段落を入れ替えることもなければ、見出しの区分が変わることもない。見出しも段落も変えることなく、その中の文章を少し見直す程度で済みます。
反対にいえば、大きな手戻りが生じないレベルで構成を決めておけば良い話。文章の一部を見直す作業は、キーパンチだろうと音声入力だろうと影響を受けない。ならば、今日の執筆の方法のように、素材が集まっている限り、構成を見出しレベルで決めておけば、音声入力するほうが圧倒的に時間は短くて済む。つまり、同じ時間であっても、より多くの分量を書けるのです。
具体的には、今朝の時点では、10ページ程度、ラフに下書きしていた状態でした。それが夕方の時点では、29ページまで増量し、かつ、文章も仕上げた状態へと至ったのです。ボクの体感覚として、2倍にはなっていないものの、それでも1.5倍程度にはなっているかも。
そのおかげで、当初、予定した以上の分量を書きあげました。今日、手掛けていた章は40ページ程度とする予定でした。ところが、このペースでは50ページ程度にまで膨らみそう。まあ、この本のひとつの山場であるため、読者により楽しんでもらえるハズだから問題なし。
というワケで、都民の日は執筆に没頭していました。そうそう、都内の区立小学校に通っている甥っ子は、休みにならずに登校したそうです。先日、その甥っ子から「竹ちゃんって、本を書きながら働いているんでしょ」と聞かれ、「いやいや、働きながら本を書いているんだよ。本を書くのは趣味だから」と訂正すると、ポカンとしていたっけ。
でも、本を書きながら働くスタイルって、素敵ですね。実現できるアイデアをお持ちの方は、こっそりボクに教えてくださいませ。