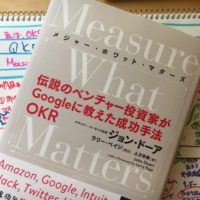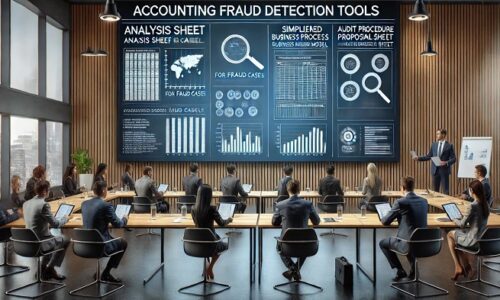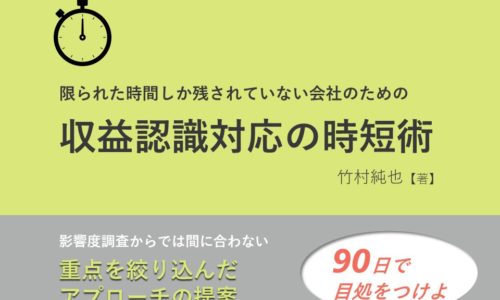本を書くときに音声入力を使う場合には、1つ、注意すべき事項があります。それは、音声入力した時点から時間を置かずに、見返すこと。
音声入力の精度が高まってはいるものの、こちらの発声の関係もあってか、期待したとおりにテキスト化されていない箇所が残ります。時間を置いて見直したときに、その箇所で何を話していたかがわからなくなることがあるのです。
今日も、その音声入力による謎のテキストに悩まされました。さすがに、1ヶ月も2ヶ月も間を置くと、そのときに何を話したかを忘れてしまいます。
もちろん、何を伝える箇所なのかは理解できますし、また、忘れてもいません。意図をもって内容を組み立てているため、構成がわからなくなることはありません。
しかし、一つの文章の中の一部分というレベルだと、これがわからない。わかりやすい誤変換なら一括置換で対処できます。例えば、本来は「KAM」と入力したいときに、「かむ」と発声します。これに対して、音声入力上は「噛む」「株」「カム」などと誤変換されている箇所があります。こうした傾向がわかると、文章を見返すときに最初に置き換えすれば良い。
これに対して、音声入力ならではの、次から次へと溢れ出る内容部分となると、どんな表現や言葉を使ったのかが再現できないことがあるのです。アドリブ的に生まれた箇所のため、なかなか思い出せない。
いくら悩んでも思い出せないときには、きれいに削除することにしています。思い出せない程度の内容なら、思い出しても読者にインパクトを与えることはないハズだから。
もっともボクの場合、手書きでも後で判読できないことも珍しくない。自分で書いた文字であることは十分認識できるのですが、何と書いた文字なのかが理解できないのです。このときも、思い出せないなら、きれいサッパリに削除します。
今日の作業では、そんなふうに削除した箇所は少なくない。また、当時は必要だと思って音声入力した箇所でも、見直してみると不要だと判断したために、ごっそり削除したセクションもあります。
でも、不思議なのが、見直し前よりもページ数が増えていること。音声入力では話の勢いをつけられるのですが、一部、緻密さが欠けることがあるため。キーパンチで見直すときには、それを補完していく結果、記載ボリュームが増えていることにも気づきました。
こうして音声入力について試していますが、実践してみると事前には気づかないことがありますね。今日の教訓は、「音声入力の見返しには時間を置くな」。これに尽きます。
また、音声入力の気づきがありましたら、シェアしますね。