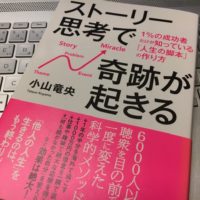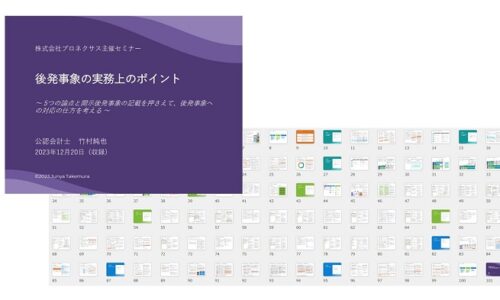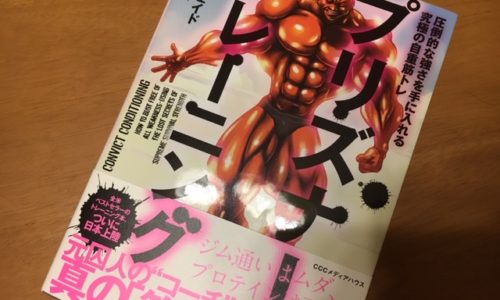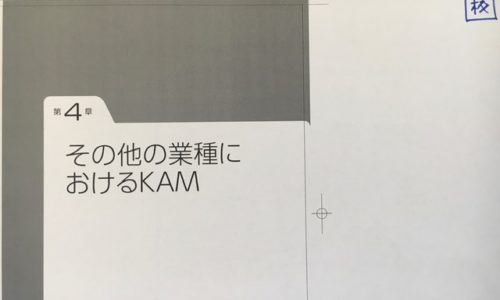今日も読書で、面白い体験をしました。午前中に取り掛かっていた執筆の区切りが良くなったため、午後に本を読むことにしました。
その本は、「月刊ビジネス選書」という洋書の翻訳本を定期購読するサービスで送られてきた『Perennial Seller 稼げる定番商品の作り方』(ダイレクト出版)。累計200万部のベストセラー作家が、定番商品の作り方と売り方を説いた内容です。
執筆している身として、かなり興味がそそられます。まず、読書のゴールとして、「今、執筆している本が定番商品となるようにしたい」と設定しました。次に、本を手に取り、パッとページを開くと、こんな引用文が目に飛び込んできたのです。
「真っ暗な部屋に座り込み、(新しい作品はつくらず)すでに書いたものの思い出に浸るだろう。」
この一文から、次のようなことを考えました。定番商品ができると、それに寄りかかってしまう。安定というよりも、依存するようなイメージ。もう作品をつくることはなく、ただ過去の作品から得られる稼ぎに固執している。
これはボクがイメージしているゴールとは、かなり違います。ボクのゴールは、作品をもっと知ってもらうことであって、創作から引退することではありません。終わりを迎えたいのではなく、始まりの機会を作りたい。
とすると、一文からイメージした状態にならないためには、常に作品を作り出していくのが良い。1つの定番商品に拘らずに、量を重視すべき。なぜなら、執筆している理由は、そこから得られる印税で楽をしたいからではなく、読者に価値を届けたいから。
こんな感じで、パッと目に入った一文から、自分のイメージを広げていきました。この後に、本文に目を通していく。すると、驚くことに、残り10%くらいの箇所で、次のような記載があったのです。
すごい作品をつくり続けることが、自分の価値を高める最高の方法なのである。
この本で著者が主張しているのは、とにかく、作り続けていくこと。価値のあるオンリーワンこそが古典となり、定番商品となっていくため、定番になるような仕事にだけ取り組むことが必要だといいます。だから、その方向性に沿って作って、作って、作りまくることを勧めています。
なんと、ボクが最初に目にした文章からイメージした内容と、同じ趣旨の文章が書いてあったのです。本を手にとってパッと開いた時間は、わずか数秒のこと。そこからイメージを広げていくのみ、数十秒。つまり、30秒もしない間に、ボクのイメージが著者の主張とリンクしたのです。それはさておき。
この本で再確認したのは、執筆もそうだしセミナーもそうだけど、こうした創作活動のゴールは、対象とする相手に価値を届けること。その価値によって、相手の快を増やしたり、不快を減らせたりできたなら最高。
そうした活動が行える環境に身を置きたいと考えていたら、もうひとつ参考となった記述がありました。それは、創作のビジネスの利益の大半は印税や売上ではない、という指摘。作家の現実の収入源は、講演や創作指導だというのです。
つまり、ただ作品を作るだけではなく、それが可能となるような環境を構築していくことも重要だと説きます。その環境のことを、この本ではプラットフォームと呼んでいます。つまり、ファンとの関係を深める基盤。中でも、Eメールを推奨しています。
Eメールはもう使えないかと思いきや、この本の原著の発売が2017年のため、そうでもないようで。なんと、50年も続いたサービス。代替する新技術が出てくる可能性があるものの、当面は最高の選択肢だと言います。ちょっと、考えてみます。