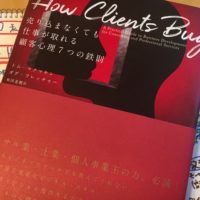物価スライド制という言葉があるのなら、「年齢スライド制」という言葉もあって良いハズ。また、この言葉から、マーケティングの基本が学べるとしたら。
物価スライド制とは、取引価格が物価に応じて上がったり下がったりすること。公共工事の契約には、このスライド条項が入っています。
工事の期間が長いほど、契約した時点から物価が変動する可能性が高まります。特に物価が上がる局面では、取引価格が上がらなければ、請け負った会社は仕入価格の上昇分だけ損失を被ります。
物価は、請け負った会社にとってコントロールできません。なので、発注者が、物価が上昇した分だけ取引価格も引きあげる措置が、物価スライド制です。モノやサービスを提供する側にとって優しい仕組み。
この物価スライド制のように、自身の年齢が上がるにつれて、相手が大人だと思う年齢も上がると感じることを、ボクは「年齢スライド制」と呼んでいます。
例えば、中学生の頃は、高校生のアイドルをみて、大人の女性に見えたものです。でも、実際に自分が高校生になると、そこまで大人には感じない。
大学生の頃は、20代の働く女性をみて、大人の女性に見えたものです。でも、実際に自分が20代の働く男性になると、そこまで大人には感じない。これは、自分が30代になったときの40代、また、40代になったときの50代をみても、同じ。実際に自分がその年代になると、そこまで大人には感じないのです。
このように、大人だと感じる年代が、歳を重ねるにつれて同じようにスライドしているのです。これが、年齢スライド制。もちろん、いつまで経っても年下に異性が好きな方もいます。しかし、ボクに限っては、同じようにスライドしていく。
先日、後輩から、30代でも「熟女」と呼ばれる話を聞きました。いやいやいや、待ってください。自分よりも年上の年代を指すものと思っていたところ、その年代をすでに超えている。スライドどころか、どこかで年齢をスキップしたかのよう。
そうそう、年齢スライド制について、とてもロマンチックなセリフがあります。それは、北川悦吏子サンが脚本の、フジテレビ系ドラマ『ロングバケーション』のワンシーン。年下の主人公を演じる木村拓哉サンが、年上のヒロインを演じる山口智子サンから、65歳で再婚してあげるときには59歳だと言われたときの返答。
「俺、59だったら、55の女の子がいい」
それを聞いたヒロインは、笑顔でこう返します。
「ロリコーン!」
ね、最高にロマンチックじゃありませんか。年齢スライド制のボクは、このセリフがよく理解できます。自分が59歳になっても、55歳の女性は「年下の女の子」ですからね。
ただし、年齢スライド制で気をつけるべき点があります。それは、自分では大人になっていないと考えていても、年下の社会人や学生から見れば、十分に大人。いや、大人を通り越しての、オッサン。周りからどう映っているかを理解していないと、コミュニケーションが上手く行かなくなる。
ビジネスでも同じ。自社のポジショニングを見誤ってしまうと、顧客から映っている姿と自身の振舞いとが一致しなくなります。それが不信感を生み出す結果、顧客が離れていきます。
自身が、どこに立っていて、誰に何を話すのか。このマーケティングの基本から外れてはいけません。まだ大人になっていないと思っていても、オッサンと受け取られるだけですからね。