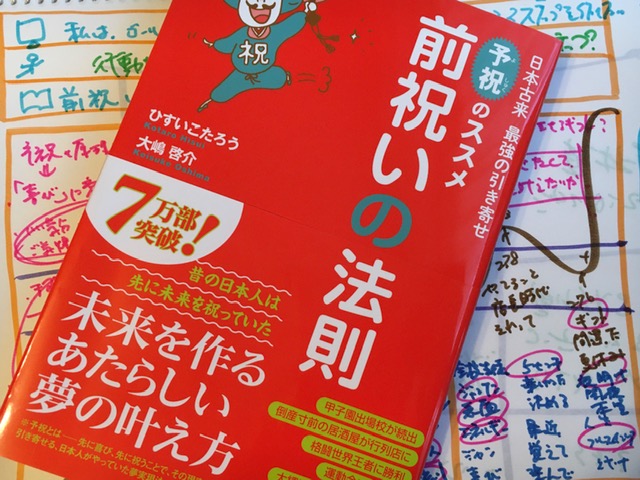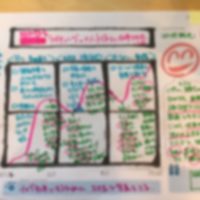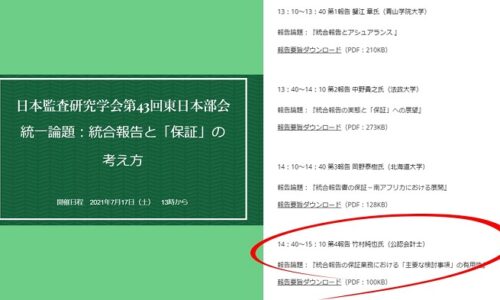セミナーや研修で講師をさせる方に、本日のボクの気づきを共有します。それは、参加者にゴール設定してもらった次の、得られる未来の描き方。
気の利いたセミナーや研修では、冒頭に、参加者にゴールを設定させる時間を設けることがあります。「今日の研修で何を得たいですか」と尋ねるアレ。これによって、脳が必要とする情報をキャッチしやすくなるために、この質問を投げるのです。
もっと気の利いたセミナーや研修では、設定したゴールの達成をさらに実現しやすくするために、達成したらどんなにワクワク、ニヤニヤするかも尋ねることもあります。未来の時点の感情をありありとイメージすることによって、ゴール達成に気持ちを駆り立てるためです。
ワクワク、ニヤニヤのワークは、サクッとできる人もいれば、時間がかかる人もいます。サクッとできる人には、イメージする力があることが多い。創造性があったり、身体感覚を表現できたりと、いわゆる右脳を働かせることができる方。
その反対に、ワクワク、ニヤニヤのワクワクに時間がかかる人とは、いわゆる左脳を働かせる方が多い。分析や論理といったことを得意にしていたり、仕事で扱っていたりとするケース。
特にボクが開催するセミナーや研修は会計や監査をテーマとするものが多いため、管理部門の人や会計士といった方々を対象としています。だから、左脳系の方が多くなるため、ゴール設定はすんなり出来ても、ワクワク、ニヤニヤとなると手がとまってしまう人も少なくない。
こうした人にも、ワクワク、ニヤニヤをイメージしやすくできないかと思い、手にとった本が、作家のひすいこたろうサンと講演家の大嶋啓介サンによる共著の『前祝いの法則』(フォレスト出版)という本。
先に喜んだり祝ったりする「予祝」によって、その現実を引き寄せる方法を説いたものです。なんでも、お花見も、豊作を祝う「予祝」だそうで。
で、この本から、ボクの課題に関してヒントが得られました。ワクワク、ニヤニヤしやすくさせるための方法論がひらめいたのです。それは、「行動を求めるなら感情から、感情を求めるなら行動から先に満たしていく」という2ステップの方法論。
というのも、行動と感情は一方向の順番ではなく、双方向だから。楽しいという感情があって、笑顔という行動になると考えがちですが、実際はそうではない。笑顔でいると楽しい気持ちになれるのです。行動と感情との間には順番がないのです。
予祝とは、何かを達成したいために、先に喜んだり祝ったりする行為。つまり、何かの行動を引き起こしたいために、先に感情を創り出すのです。
ならば、ワクワク、ニヤニヤという感情を想起させたいなら、予祝とは反対に、先にワクワク、ニヤニヤしている行動をとらせれば良い。行動と感情との間に順番がないのであれば、この理屈は成立するはず。
具体的には、ワクワク、ニヤニヤのワークを行う前に、参加者を笑顔にさせたり、パワーポーズをとらせたりすれば良い。何かしらワクワク、ニヤニヤしたときの行動をとらせるのです。そのうえで、こうした行動でいるときの感情を分析させていくのです。
この双方向の2ステップは、簡単に使えそうな方法論じゃありませんか。今月、会計士に向けのセミナーで講師を務める予定が2つあるため、活用してみようかとワクワクしています。あっ、ここでも、感情を満たしてから行動を引き寄せていくことを実践していたことに気づいたよ。