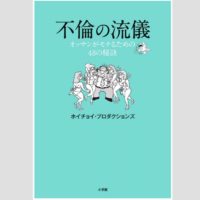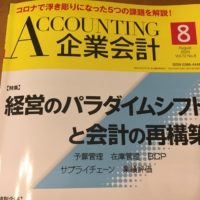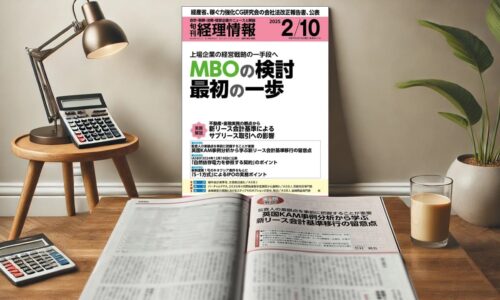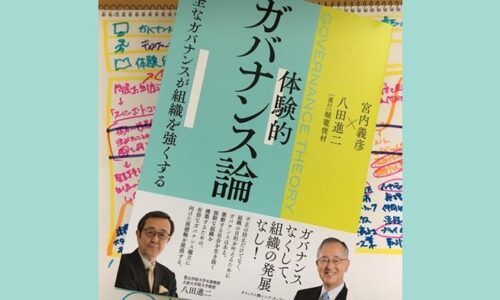ダイナミック・プライシングの導入の布石となるかどうか。サザンオールスターズによる、無観客の配信ライブの成功が後押しになるのではないかと考えています。
ダイナミック・プライシングとは、需要と供給に応じて製品やサービスの価格を変動させること。人気があるものは高く、そうではないものは安く提供することで、バランスをとっていくのです。
一方、サザンオールスターズは、デビュー42周年を迎える2020年6月25日(木)に、横浜アリーナから無観客ライブ『Keep Smilin’~皆さん、ありがとうございます!!~』をネット配信しました。ファンや医療従事者への感謝を込めた特別ライブとして位置づけられたもの。
ネット配信といっても、有料。世間には「ネットは無料」という見方がはびこる中で、有料コンテンツとして配信。まあ、当たり前のことではありますが、この点について評価している記事もあるほどに、ある意味、チャレンジングなこととして受け止められたイベントでした。
このライブは、報道によれば、チケット購入者は約18万人とのこと。総視聴者数は約50万人と推定されています。2019年のライブツアー『“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!』の全22公演の総動員数に匹敵する規模となりました。
昨年のライブツアーの1回当たりの動員数は平均で約2.3万人。今回のライブ配信では、チケット購入者ベースで考えても7.8倍の動員が行えた計算になります。
また、このライブの視聴料金は、3,600円。サザンオールスターズとしては格安の設定といえます。2019年のライブツアーでは、全席指定で9,500円。62%引きでチケットを販売したことになります。
このように、ライブのネット配信は会場でライブを観るよりも料金は安めに設定される一方で、1回当たりの動員数は多くできることが実証されたのです。先日のブログ「今後の音楽ライブは2つの顧客セグメントを持て」で、次のように話したことが実現したといえます。
すると、高額チケットほどではない価格でライブに参加することができます。しかも、会場の収容数に制約されない。当日に5万人しか体験できなかったところ、当日やその後に10万人、100万人にも疑似体験してもらえるのです。
今後は、リアルの会場に参加できる権利も別途、販売していくでしょう。3密を回避しなければならないため、これまでのような人数を収容することは厳しい。自ずとライブ会場に参加できる人数が限られます。
ただ、そこまでしてもライブを体験したい、という価値が付加されるため、高額でも販売が可能な状況にあります。仮に、今回のライブ配信の視聴料金3,600円を比較対象としても、3倍程度の設定は従来のライブと変わらないため、すんなりと受け入れられるハズ。
ましてや、サザンオールスターズほどのアーティストのライブは、入手困難なプラチナ・チケット。違法で高値で売買されていた状況を踏まえると、ダイナミック・プライシングを導入して転売を排除したほうがよほど健全。それが、新型コロナウイルスによって導入しやすくなっているのです。
業界の先頭を走る人がこうして先鞭をつけることは、リーダーとしてふさわしい行動。サザンオールスターズの次の打ち手に、ビジネスモデルの観点から目が離せませんよ。