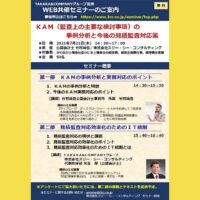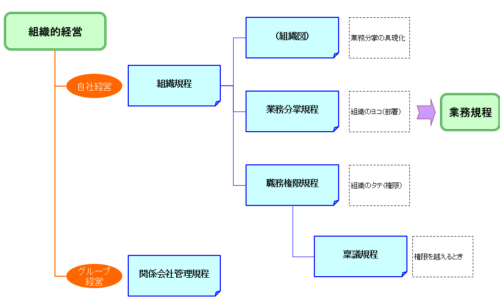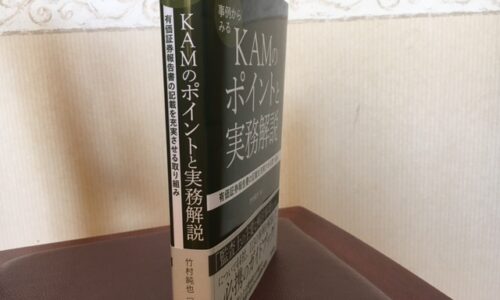今日の2022年12月15日、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)が開催されました。2022年6月の報告書による提言のフォローとして、四半期開示とサステナビリティ開示に関する施策が検討されていたため、注目の的でした。
前日に、金融庁のウェブサイトで、当日の審議で用いる2つの配布資料がアップされていました。ひとつは「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(案)」、もうひとつは「我が国におけるサステナビリティ開示のロードマップ(案)」。
しかも、報告書案の日付は「令和4(2022)年12月●日」と記されているため、今から2週間もしない間に正式版がリリースされそうです。当日の審議を視聴する限り、字句の修正はあっても、骨子までは変更されなさそうなことから、この報告書案で各種の改正が進むものと考えられます。
今回の審議では、情報開示を進めたい投資家と、作成負担を過重にしたくない企業側とがせめぎあっていた印象がありました。そのため、報告書案にはスタンスの異なるコメントが記載されています。「なるほど、これを『利害関係の調整』と呼ぶのか」と感心したものです。
加えて、四半期開示もサステナビリティ開示も、足元での開示府令の改正だけではなく、将来的な、いや、短期的な検討課題も挙げられています。このような性格のため、報告書案が、従来の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループによる報告書と比べて、若干、読みにくくなっている面も否定できません。
そこで、足元での改正に関連する部分を抜粋してみました。
四半期開示の足元改正
(1)第1・第3四半期に係る四半期報告書の廃止
四半期開示については、金融商品取引法の四半期報告書(第1・第3四半期)と取引所規則に基づく四半期決算短信とを「一本化」する方向性について審議されていました。その結果、報告書案では、金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止すること、すわなち、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」することが案として記載されています。
(2)四半期決算短信の義務付け
「一本化」後の四半期決算短信について、義務化するかどうかが審議されていました。その結果、当面は、四半期決算短信を一律に義務付けることが案として記載されています。
(3)四半期決算短信の開示内容の追加
今回の見直しが情報開示の後退と受け取られないようにする観点から、原則として速報性を確保しつつ、「一本化」後の四半期決算短信に投資家の要望が特に強い事項(セグメント情報、キャッシュ・フロー情報等)を追加することについて、取引所が検討することが案として記載されています。
(4)四半期決算短信に対する監査人のレビューの任意化
「一本化」後の四半期決算短信には 速報性の観点等から、監査人のレビューを一律には義務付けないことが案として記載されています。また、企業が任意でレビューを受けたかどうかについて四半期決算短信に開示することも案として記載されています。
さらに、会計不正や内部統制の不備などによって、取引所規則により一定期間、監査人によるレビューを義務付けることも案として記載されています。
(5)四半期決算短信の虚偽記載に対する罰則
「一本化」後の四半期決算短信は取引所における開示書類であるため、そこでの虚偽記載に対する罰則については、取引所が適切に実施していくことが案として記載されています。
(6)半期報告書への監査人の保証
第1・第3四半期報告書を廃止した後、上場企業は、開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することとなります。この半期報告書については、現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求め、また、提出期限を決算後45日以内とすることが案として記載されています。
一方、非上場企業は、上場企業に義務付けられる半期報告書の枠組み(現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビュー、45日以内の提出)を選択可能とすることが案として記載されています。
ただし、上場企業である銀行や保険会社等(金融商品取引法における「特定事業会社」については、破綻処理制度等との関連も踏まえ、金融監督上の観点から、引き続き検討していく必要があるとされています。
(7)会計基準・監査基準の整備
四半期会計基準及び四半期レビュー基準については、「一本化」後の四半期決算短信や半期報告書へ適用できるようにするため、企業会計審議会やASBJ、取引所、日本公認会計士協会などの関係者が、今回の見直しに伴う必要な対応を行うことが案として記載されています。
(8)公衆縦覧期間の延長
金融商品取引法上の第1・第3四半期報告書の廃止後に期中の法定開示として残る半期報告書及び臨時報告書の公衆縦覧期間(各報告書提出後からそれぞれ3年間・1年間)は、これらの報告書の虚偽記載に対する課徴金の除斥期間(各報告書提出後から5年間)より短いため、課徴金納付命令が行われる際に、公衆縦覧期間が終了している事態が生じかねない状態にあります。
そこで、第1・第3四半期報告書を廃止した後の半期報告書や臨時報告書の公衆縦覧期間については、金融商品取引法において、有価証券報告書の公衆縦覧期間及び課徴金の除斥期間である5年間へ延長することが案として記載されています。
サステナビリティ開示の足元改正
(1)我が国におけるサステナビリティ開示基準の取込み
法定開示である有価証券報告書には、国内において統一的に適用しうるサステナビリティ開示基準を取り込んでいくことが案として記載されています。
(2)サステナビリティ基準委員会の役割や開示基準の位置付け
我が国では、会計基準の設定主体や企業会計基準が、金融商品取引法令上の枠組みの中で位置付けられています。そこで、サステナビリティ情報も同様に、その開示基準の設定主体及び開示基準について、金融商品取引法令の中で位置づけることが案として記載されています。
なお、ここで、サステナビリティ基準委員会が開示基準の設定主体として要件を満たしうる旨が示されています。関係法令の整備とともに、サステナビリティ基準委員会が開発する開示基準について、個別の告示指定により我が国の「サステナビリティ開示基準」として設定することも記載されています。
以上が、足元の改正に限った報告書案の内容です。内容が少しでも読み取りやすくなったら嬉しいです。
そうそう、いくつかの点でコメントしたいところがあるのですが、文字数も多くなるので、別の機会にお話ししますね。