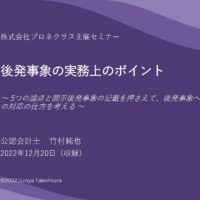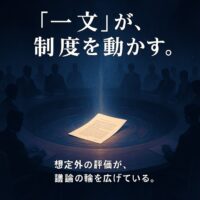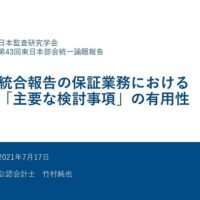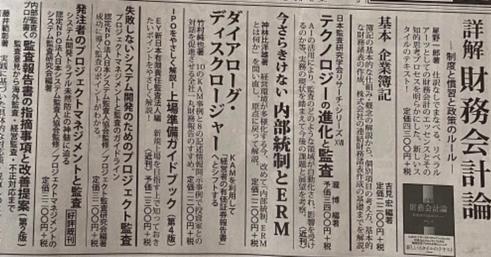予言が的中しましたよ。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が気候変動の次に着手するテーマが何かを。「タケムラダムスの大予言」という言うほどのものではありませんが。
その予言が記載されているのは、今日の2022年12月20日、株式会社プロネクサスさんのディスクロージャー・IRの実務支援サイト「PRONEXUS SUPPORT」にアップされた、ボクが寄稿したコラムです。そのタイトルは、次のとおり。
『なぜ、有報にはSDGsではなくTCFDなのか』(注:会員限定サイトです)
まずは、このコラムを執筆した経緯から共有しますね。
コラムの執筆経緯
ちょうど今、有価証券報告書において、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく形で気候変動の情報開示を求める開示府令の公開草案がリリースされていますよね。そうした中で、なぜ、有価証券報告書に気候変動に関する情報が求められるのかについて、戸惑われているような声を聞くことがあります。
そこで、その背景が理解できるよう、コラムを執筆した次第です。また、その背景がわかれば、単に炭素関連の指標の開示を求めているのではないこと、つまり、本来的にTCFDが求めている開示が何かについても納得できるハズ。それは、企業の財務報告に関する経営資源を適切な領域に配分できることを意味します。
そんな特徴をもったコラムは、次のような構成としています。
=====
(イントロダクション)
TCFDが開示項目とされる理由
1 背景
2 TCFDの目標
3 TCFDの開示媒体
SDGsが開示項目にならない理由
1 背景
2 SDGsの目標
3 SDGsの開示媒体
TCFDの次には何が来るか
=====
予言したテーマはズバリ、、、
コラムの最後に、「TCFDの次には何が来るか」という見出しで記載した箇所があります。ここで、サステナビリティ開示において気候変動の次に来るテーマについて言及しました。根拠はコラムをご覧いただくとして、予言したテーマは、ズバリ、「自然関連」。
この予言が的中するかどうかが判明するのは、一体、いつのことかと呑気に構えていたところ、こんなニュースが飛び込んできました。それは、シェルパ・アンド・カンパニー株式会社が国内外のESG関連ニュースを発信しているウェブサイト「ESG Journal」です。2022年12月19日に、こんなニュースを紹介しました。
「ISSB、気候変動報告書に生物多様性、ジャスト・トランジション開示を追加」
ちなみに、ソース元は、ロイターによる次の記事です。
“Global sustainability rules body steps up focus on biodiversity”
原文のニュース記事によれば、国際サステナビリティ基準審議会の議長であるエマニェル・ファベール氏が、気候変動の基準を公表した後は、生物多様性に関するルールを検討する予定だと述べたようです。しかも、検討に1年以上もかかることはないだろう、とも話したそうです。
このように短期間でルールを作成できるのは、国際サステナビリティ基準審議会とは別の機関で、自然関連の開示フレームワークが検討されているため。この団体の存在も含めて、まさに、コラムで紹介したとおりの展開となっています。
もちろん、開示の目的は、TCFDに同じ。コラムの中で説明していますので、ご興味をお持ちの場合には、ぜひとも、ご覧いただければ嬉しいです。
後出しジャンケンではありません
えっ、日本語版のニュースの配信日が2022年12月19日で、一方、コラムの掲載が2022年12月20日だから、予言ではないだろう、って。
確かに、日付としては、コラムの掲載はニュースよりも2日後。そこだけを見れば、後出しジャンケンのように映るかもしれません。
しかし、コラムは、プロネクサスさんのサイトに掲載されるものです。決して、ボクのブログに自分のタイミングだけでアップしているものではありません。つまり、プロネクサスさんによる作業が介在している点を見逃してはいけません。
具体的には、ボクの原稿を受け取り、その内容が検討され、サイト掲載のためにデータ加工されたうえで、今日のリリースに至っています。もちろん、ボクの原稿だけを相手にしている訳でもないため、一定の期間を要します。実際、コラムの初稿を提出したのが、2022年10月のこと。もう2ヶ月前のため、予言的中なのです。
まあ、そんなことはさておき。差し迫った課題は、気候変動ですよね。あまり注目されていなさそうな論点に、有価証券報告書に気候変動の開示が充実することによって、財務諸表の会計処理や注記事項に影響を及ぼしかねない点があります。また、監査法人から、企業側が気候変動の影響を考慮したどうかも含めた財務諸表監査が実施されることも想定されます。
そんな「気候変動の会計と監査」について、プロネクサスさんでもお話しする機会を頂戴しました。収録は2023年1月10日。新しい情報が次々と登場する分野であるため、今回は、セミナー資料の提出を期限間際まで引っ張ることにしています。最新の情報を得たいときには、こちらから、セミナー案内をご確認ください。