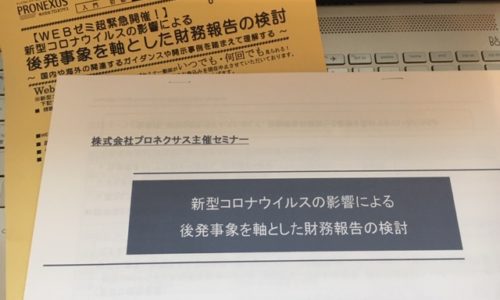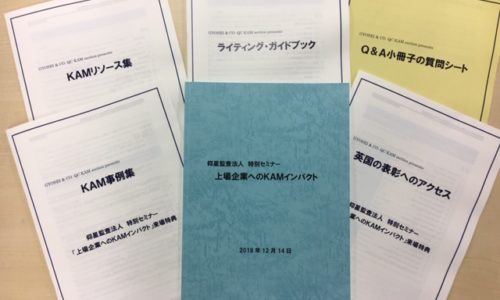2023年3月期からの決算では、KAM(監査上の主要な検討事項)の強制適用の3年目を迎えます。相変わらず代わり映えのしないKAM事例もあれば、有価証券の評価について個別銘柄を具体的に示したことが一部で話題となってるKAM事例もあります。
そんな中、2023年3月期に係る有価証券報告書の提出期限である昨日の2023年6月30日に、金融庁から、こんな報道発表がありました。
- 「監査上の主要な検討事項(KAM)」の実務の定着と浸透に向けた取組みについて
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630-9/20230630-9.html
果たして歩みを止めても良いのか
ここで注目すべきは、金融庁によるKAMへの姿勢です。なんでも、今後は、「KAMに関する勉強会」を開催することも、「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」を公表することも予定していない、とのこと。もしかすると、その分のリソースは、今後、サステナビリティ開示に充てていくのかもしれません。
個人的には、この発表は残念なものでした。そもそも、KAMが導入された目的は、財務諸表監査の信頼性の確保にあります。報道発表の中には「KAMの記載内容について検討が必要な事例も見られる」とも指摘しています。ならば、その達成が確認できるまでの間は、規制当局として勉強会や事例分析などを継続して実施するのが適当と考えられるからです。
しかも、その必要性は2023年3月期から、さらに増しています。というのも、サステナビリティ開示が義務化されたためです。一見すると、KAMとサステナビリティ開示とは関係がないように思うかもしれません。
KAMだけの分析ではモッタイナイ
KAMの導入によって、財務報告の利用者は、監査人が重要と判断した事項について知り得る状況となりました。これまで記述情報から経営者の視点しか得られなかったところ、監査人の視点まで理解できるようになったのです。もちろん、財務諸表監査という範囲ではあるものの、両者の認識が「見える化」されたことに大きな意味があります。
経営者は、何を重要な事業リスクとして考えているかを記述情報に反映します。一方、監査人は、事業リスクを踏まえたうえで、いわゆるリスクアプローチを実施していきます。このとき、両者のコミュニケーションが良好である場合には、互いに同じ方向を向きながら、それぞれが重要な事項にリソースを適切に配分していくことができます。
反対に、コミュニケーションが良好ではない場合、それぞれが別の事項を重要なものと捉える結果、リソースが適切に配分されなくなる可能性があります。それが財務諸表の虚偽表示や財務報告の虚偽記載を招くおそれも否定できません。
サステナビリティ開示とKAMとの関係
経営者の視点は、事業リスクに限りません。2023年3月期から義務化されたサステナビリティ開示にも当然に反映されます。つまり、従来よりも、サステナビリティに関する経営者の視点が追加されるのです。
その視点とは、「記述情報の開示に関する原則(別添)-サステナビリティ情報の開示について-」によると、次のものが例示されています。
- 環境(気候変動を含む)、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、ガバナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティなど
例えば、サステナビリティ情報において気候変動による財務的影響が大きい開示した場合、KAMを含む財務諸表監査において気候変動の影響を考慮すべき必要はなかったかがひとつの論点となります。IFRSを適用している企業では、そもそも財務諸表への考慮も論点となります。これについては、書籍『伝わる開示を実現する「のれんの減損」の実務プロセス』で一章分まるまる使って解説しました。

また、KAMにおいて、業種の特性からIT統制が取り上げられている場合に、サステナビリティ情報としてデジタルセキュリティが開示されていないことの適否が問われる局面もあるかもしれません。これ、気になる事例が登場しています。
このように、重要なサステナビリティ情報として開示している内容と、当期の財務諸表監査で特に重要と判断されたKAMとに齟齬があると、経営者と監査人との間のコミュニケーションに問題意識が持たれる可能性があるのです。
KAMだけでなく、サステナビリティ開示も
ボクが以前から指摘しているように、KAMだけを分析するだけでは限界があります。記述情報とセットで分析しなければ見えないことがあるのです。それは、サステナビリティ開示も同じです。
ということで、”Not only KAM but also Financial disclosures”という視点で、2023年3月期も粛々と分析を進めています。小さなことを見落とさないために、分析対象のすべてを自ら検討することを信条としています。実際、「この作業を外注していたら、気づかなかったよなあ」という論点にも毎年、遭遇していますしね。
そんな分析結果は、秋以降に予定されているセミナーで説明していく予定です。どうぞ、お楽しみに。KAM分析は、お任せください。
P.S.
”Not only KAM but also Financial disclosures”という視点での分析をもっと知りたいときには、書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』がオススメです。