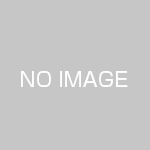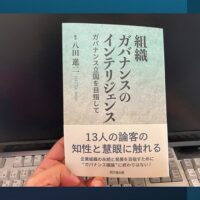2025年1月下旬。会議室の窓から差し込む冬の陽射しが、机の上に広げられた契約書の束を照らしていた。霧坂美咲は、南青山店の契約書に目を落としながら、わずかに視線を夜島誠人に向けた。先日の留学の話題から、彼の表情が曇ったままだ。その姿は、何かを失いたくないという感情をあからさまに物語っていた。
「今日は南青山店の賃貸借契約を検討しましょう」
その声に応じるように、陽野沙織が契約書を取り出した。総務部での半年間で培った手際の良さが、彼女の動きに表れている。
「これは、定期建物賃貸借契約ですね」沙織は一呼吸置いて続けた。「とりあえず『更新がないこと』の事前説明があるものとして…契約期間は7年。それと、中途解約条項がついています」
「中途解約条項?」誠人の声が上ずった。「定期契約に?」
その反応には、いつもの軽さが見当たらない。
黒嶺尚吾は眼鏡を押し上げながら、ゆっくりと説明を始めた。
「普通の賃貸借契約なら、借手はいつでも解約を申し入れることができる。ただし、解約予告期間は必要だがな」黒嶺は一呼吸置いて続けた。「しかし、定期建物賃貸借契約は違う。一定期間借りると契約する以上、原則として中途解約はできない」
「合意解約なら可能ですよね?」美咲が問いかけた。
「ああ。だからこそ通常、定期建物賃貸借契約では、新リース会計基準でいう『解約オプション』は借手には存在しないと考えるのだろう」黒嶺の説明は論理的で明快だった。
美咲は小さく頷いた。「私も最初はそう考えていました」
「しかし」黒嶺は続けた。「現実には、借手側が解約したい場合がある。例えば、ある店舗で赤字が継続しているとする。そのとき、期間満了までの賃料に相当する違約金を支払ってでも、人件費や各種経費を抑えたほうが合理的なケースもあるだろう」
「なるほど」誠人の声には、かすかな理解の色が混じっていた。複雑な現実を前にした戸惑いを隠せない。
「そのため」黒嶺は、誠人の反応を確認するように一瞬止まった。「定期建物賃貸借契約でも中途解約条項を定めることがある。その場合、民法上、解約申入れから1年経過後に契約を終了できる。この1年が『解約不能期間』となる」
「だったら」誠人が身を乗り出した。「中途解約条項を入れたほうがお得じゃないですか?」
その素直な疑問に、黒嶺は目を細めた。「借手の総合的な収支としては、確かにその通りだ。しかし」彼は意図的に言葉を区切った。「貸手には空室リスクがある。だから通常、期間満了までの賃料相当額をペナルティとして課すことが多い」
「ホントだ!」沙織が契約書を指さした。新たな発見への興奮が込められた声だった。「この契約にもペナルティ条項がある。それに…」彼女は眉をしかめた。「すごく複雑」
沙織は条項を読み上げ始めた。「契約開始から5年までは期間満了までの賃料全額、5年超6年までは6ヶ月分、6年超は2ヶ月分…」
「そんな高額の違約金なら、事実上解約不能だろ」誠人は頭を抱えた。「とはいえ、時期によって金額が変わるから、『解約不能期間』はどう考えれば…」
「それは違います」美咲の声が、誠人の混乱を切った。「これは借手の話です。確かに違約金は発生するけど、支払いさえすれば解約可能でしょ。だから『解約不能期間』は解約通知期間としての1年になるんです」
「じゃあ、このペナルティは?」
「中途解約条項があるから、借手には『解約オプション』があります」美咲は誠人をまっすぐ見つめた。「このオプションを行使しないことが『合理的に確実』な期間について判断していくんです。解約違約金は『経済的インセンティブ』として、その判断に影響を与える要因のひとつになります」
黒嶺が理解を示すように頷いた。「つまり、契約初期は違約金が高額だから、解約オプションを行使しない強力なインセンティブとなる。一方、6年超になると2ヶ月分まで軽減されて、解約が相対的に容易になる」
「さすが、黒嶺さん」美咲の声には、わずかな安堵が混じっていた。彼らの間に、確かな理解の共有が生まれつつあった。「経済的インセンティブには、他にも解約関連コストや事業上の重要性も含まれます。でも、7年の契約期間の中で、解約オプションを行使しない『合理的に確実』な期間をどう判断するかが、南青山店の『借手のリース期間』の重要なポイントなんです」
誠人は「……頭が痛くなってきた」と呟きながら、肉まんに手を伸ばした。その仕草に、三人は思わず笑みを浮かべる。それは、この緊張感の漂う空間に、小さな温もりをもたらした。
その瞬間、会議室のドアが開いた。
「このメンバーで、新リース導入プロジェクトを開始する」
氷倉隆の声が、突如として響き渡った。管理本部長の予期せぬ登場に、全員が息を呑む。誠人は思わず背筋を伸ばした。美咲との間に漂っていた気まずさが、一瞬で凍りついた。
「本部長、これは…」
黒嶺の問いかけに、氷倉は腕を組んだまま答えた。それは、揺るぎない決意を感じさせるものだった。
「この会社は百を超える小売店舗を賃借している。その影響を考えれば、新リース会計基準の適用は経営レベルの課題だ。だから、正式にプロジェクトチームを設置するんだよ」
氷倉は端的に言い切る。
「すでに管理担当取締役の承認は取った。各部長にも話は通してある。君たちにはこれから、正式な業務としてこのプロジェクトを進めてもらう」
美咲は静かに頷いた。彼女の目には、決意の色が宿っていた。最後のプロジェクト。それは彼女にとって、日本での集大成となるはずだった。そして、即座に応えた。
「不動産賃借契約に焦点を絞って、すべての賃借物件のオンバランス方針を説明する、というのはいかがでしょうか」
氷倉は満足気に頷くと、「本決算前までに粗々の報告をしたい。しっかり頼むぞ」と颯爽と会議室を後にした。残された四人は、互いの顔を見合わせた。そこには、これから始まる長い道のりへの覚悟と不安が混じっていた。
「……マジかよ」
「……つまり、これは遊びじゃなくなったってこと?」そんな沙織の言葉に、これまでの和やかな雰囲気は一変し、プロジェクトとしての緊張感が漂い始めていた。
夕暮れの光が会議室に差し込み、机の上の契約書の影を長く伸ばしていた。それは美咲の残された時間を刻むように、静かに、しかし確実に進んでいった。
(第6話「モデルの構築」へ続く)