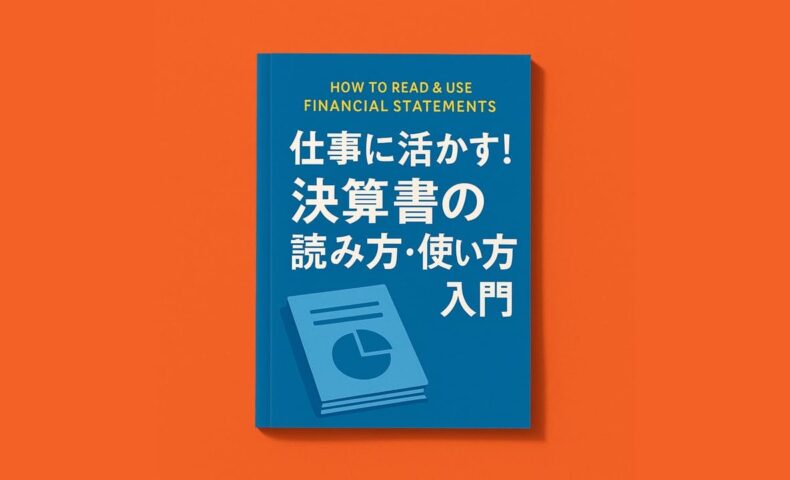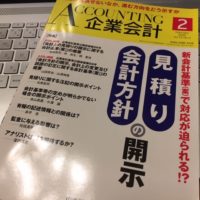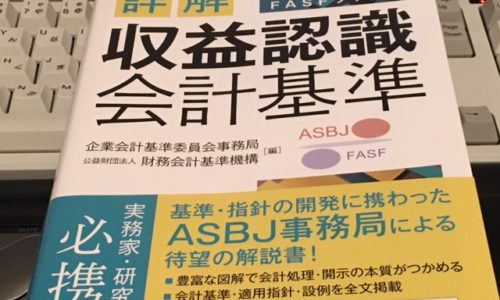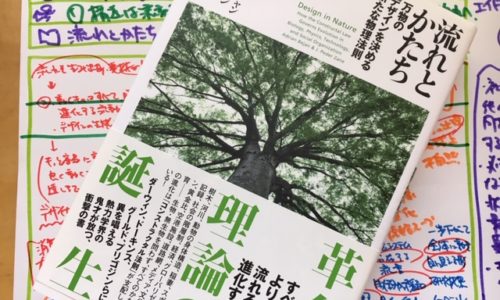2025年4月21日、ある企業の新入社員研修を担当しました。テーマは「仕事に活かす!決算書の読み方・使い方入門」です。リアル開催で、2時間弱の研修でした。
きっかけは、以前からご縁の企業のある方からの一言でした。「新入社員に決算書の見方をざっくりと教えてほしい」と。しかし私は、その控えめな依頼を額面通りには受け取りませんでした。というのも、「ざっくり」と言われたときこそ、ほんとうに伝えるべき核を見抜くチャンスだからです。
頭をよぎったのは、あのドラマ『プロポーズ大作戦』の名台詞——「求めよ、さらば与えられん」。そう、学びは与えるものではなく、求めた瞬間に本物になるのですよ。だから私はこの研修を、「数字の読み方」をなぞる場ではなく、「数字の意味」と出会い直す機会として再構成したのです。
■会計は「構造」で読む
私がこの研修で伝えたかったのは、会計知識を「決算書の構造」として暗記することではありません。むしろ、会計とは経営の言葉を翻訳するための装置であり、未来をつかむためのレンズだということなのです。冒頭の導入部分を除き、、次の3部構成としました。
第1部では、貸借対照表に焦点を当てました。資産・負債・資本という三項目を、ただの記号としてではなく、「この会社は何に投資し、何を背負い、どれだけ自力で立っているか」という問いへと変換していく技術を伝えました。特に、流動・固定という構造的分類を通じて、資金繰りの違いを受講者が体感できるよう、演習を交えました。
第2部は、損益計算書です。ここでは「利益の階段」という視点を用いて、どの段階で収益や利益が削られていくのかを見抜く演習を行いました。中でも、売上が2倍になっても利益が2倍にならない理由を、自力で数字から発見してもらう演習では、受講者の集中力が一気に研ぎ澄まされていくのを感じましたよ。
第3部では、実際の決算書を用いた応用演習に挑戦してもらいました。貸借対照表と損益計算書を読み解きながら、損益分岐点分析に取り組む内容です。正直、このレベルまで踏み込む入門研修は多くありません。けれど、ある受講者の「これ、実際のプロジェクトでも使えそうです!」というひと言が、すべてを肯定してくれましたね。
■「意味が見える」から、「使える」が始まる
この研修の設計方針は、あえて「教科書的な網羅」を避け、「意思決定の現場で役立つ視点」に絞ることでした。
たとえば損益分岐点分析。式を覚えても、現場では役に立ちませんよね。でも、「固定費が大きい業態では、売上がわずかに減るだけで利益が急落する」ことや、「変動費が高い業種では価格戦略が成否を握る」ことを体感すれば、式よりもずっと深い理解が得られます。
「数字に強い」とは、計算が速いことではありません。数字が語る“意味の文脈”を読み解き、それを現場の言葉に翻訳できる力です。それこそが、今の組織に必要な“知的体力”ではないでしょうか。新人教育にとどまらず、すべてのビジネスパーソンに問われる力です。
■数字の向こうに、自分の仕事が見えてくる
研修の最後、私はこう語りかけました。「数字の向こうには、“あなたの仕事”がある」と。だからこそ、「明日から、数字で見る習慣を始めてみよう」と呼びかけたのです。
数字は冷たい道具ではありません。その背後には、戦略があり、意志があり、現場のリアルな動きがあります。そして何より、数字は“嘘をつけない鏡”でもあるのです。
「会計」という言語にふれると、数字が話し始める瞬間があります。そんな瞬間を、一人でも多くの新入社員が自分の仕事の中に見つけてくれたなら、この日の2時間は十分すぎるほど価値があったと思うのです。
「決算書を読める人」は頼もしい。でも、「決算書から問いを立てられる人」は、ちょっと面白い。そう、会計は退屈な作業じゃなく、ビジネスの中でいちばんクリエイティブな遊び場なのかもしれませんよ。