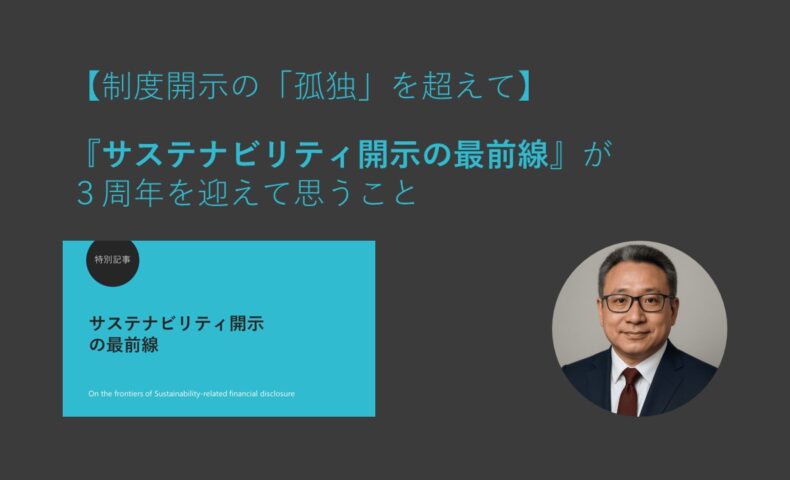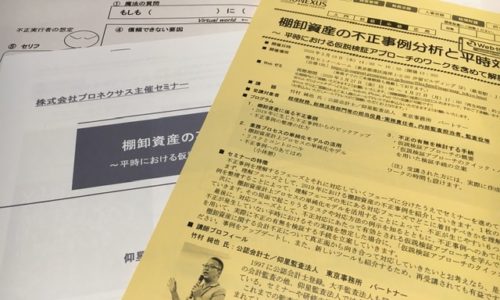「たった一人で、それをやり続ける価値はあるのか?」
誰にも言わなかったけれど、私は何度もそう問いかけてきました。
毎週1本、止まらずに書き続けてきた理由
制度の行間を読み、英語原文とも格闘し、サステナビリティ関連【財務】開示という、まだ誰も答えを持たない分野で、記事を書き続けてきました。
誰から頼まれたわけでもない。
報酬も名誉も、正直言って大したことはない。
それでも——
今、2025年6月2日の記事で 119本目 になります。
2年間、一度も止まらなかった のです。
続けられたのは、読者のまなざしがあったから
これは、ありがたいことに 1人じゃなかった からです。
購読を継続してくださる方々がいたからこそ、私は1本1本、更新し続けることができました。
そして何より、読者の問いかけ を想定することが、私の記事を深くしてくれました。
「この制度の意味は?」
「この事例、どう読み解くべき?」
その一つひとつが、次のテーマの原点でした。
つまり、このブログは、読者との共著でもあった のです。
この2年で見えてきた「真の課題」
最初は制度の概要解説でした。
でも続けるうちに、こう気づいたのです。
本当のハードルは、「知識の欠如」ではなく、「考え方の欠如」だ。
たとえば——
- ESGは自由記述だが、財務開示には 作法 がある
- 比較情報の取扱いは、従来型ではなく 財務思考 で判断する
- 海外の開示事例をそのまま真似ても、日本の制度と 整合しない ことがある
このような「解説されない前提」こそが、実務のボトルネックでした。
だから私は、従来のESG開示では解けない問題 を解き続けてきたのです。
でも、まだ仲間は足りない。
ISSBが動き、SSBJも整備され、ISSA5000によるサステナビリティ保証もやってくる。
いよいよ、サステナビリティ関連財務開示は「企業の競争力」になります。
それでも、現場ではまだこういう声が聞こえます。
- 「ESGと何が違うのか分からない」
- 「財務とどうつなげるかが分からない」
- 「誰も社内で相談できる人がいない」
だからこそ、今、あえて言いたいのです。
ここに来れば、答えの地図があります。
制度の先を読む力、考え方の整え方、そして確信を持って説明できる「判断軸」が、ここにはあります。
『サステナビリティ開示の最前線』は、あなたと共にあるために続いている
このサブスク記事は、月額980円。
でも、その価値は「情報」ではありません。
- あなたが 1人で迷っている時間を、確信に変える場所
- 制度の裏にある論理を、あなたの言葉で語れるようにする場所
- 「自分は正しいことをしている」という 実感を持てる場所
そのために、私はこれからも書き続けます。
そして、あなたが必要なときに、ここでお迎えできるようにしておきます。
■「たった一人で」は、もう終わりにしよう。
ここから、共に前へ。