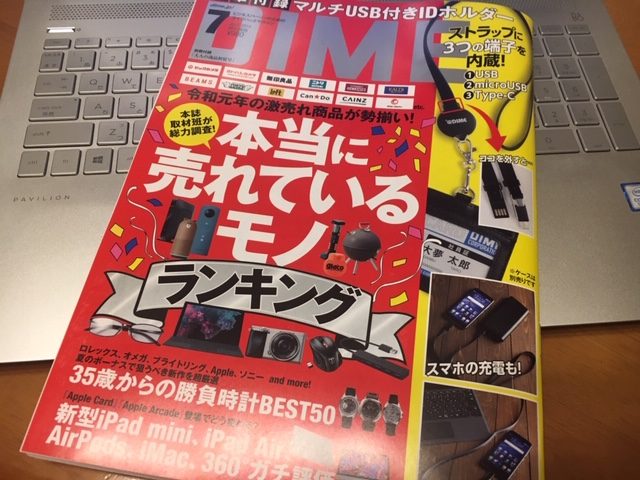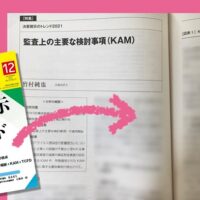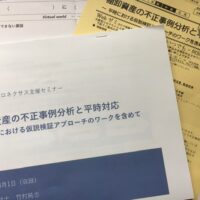最近、飲食店の「居抜き」が増えているそーで。そんな情報を、ビジネスパーソンのためのライフハックマガジン『DIME 2019年7月号』(小学館)から得ました。ボクの大好きなホイチョイ・プロダクションズさんが連載しているのです。
ホイチョイ・プロダクションズさんといえば、映画『私をスキーに連れてって』をはじめとした映像作品の他に、単行本『東京いい店やれる店』(小学館)をはじめとした飲食店の紹介記事も有名。
そんな彼らが、「客がホイホイやって来る飲食店作りの秘訣100ヶ条」として、飲食を巡るコラムを書いています。その今月号のテーマは、居抜き。
居抜きは、出ていくお店にとっては、内装や設備を撤去しなくても良いため、そのためのキャッシュアウトが少なくて済む。より拡大するための移転であっても、業績悪化による撤退であっても、手持ちの資金を確保する意味では大きな効果があります。
一方、これから入るお店にとっては、ゼロからお店づくりをしなくても良い分、同じくキャッシュアウトが少なくて済む。もちろん、こだわった内装や設備にしたいときには居抜きは向いていませんが、納得できるようなら、長期に回収していく設備資金を少額に抑えられるため、資金繰りに優しい。
また、そのスペースを貸している大家にしても、改装している間や次の借り主を探している間、お客さんが寄り付かないことは、その物件の魅力にも影響しかねない。営業していない期間が少ないほど、お客さんが離れていかないため、居抜きは悪くない経済取引。
この居抜きのポイントは、店舗の賃貸借契約にある原状回復義務。借りている物件を出ていくときに、借りる前の状況に戻すこと。まっさらな状態で物件を借りたのなら、出ていくときに、まっさらな状態に戻さなきゃならない条件。オフィスでもお店でも住宅でも、物件を借りるときには原状回復義務が契約で定められていることが多い。
原状回復義務は、会計に携わる者にとっては、あの会計上の論点を思い出させます。それは、資産除去債務。建物といった有形の固定資産を取得した際に、使用の結果として除去を契約上求められる義務のこと。
わかりやすいところでいうと、アスベストやPCB。これらが見つかると、除去しなければなりません。賃借建物に係る原状回復義務は、これらと性格は違うものの、契約上求められる義務として、資産除去債務に含まれているのです。
この資産除去債務について、今でも鮮明に覚えている話があります。資産除去債務に関する会計基準が適用になったのは、2010年4月1日以後に開始する事業年度から。その適用に向けて、当時、担当していた非上場会社の管理部長さんとお話ししていたときのこと。賃借している建物の資産除去債務をどう計上していくかを伺ったところ、こんなふうに返事されたのです。
「原状回復費用をいかに生じさせないように交渉するのが、自分の仕事だ」と。だから、「そんなものは生じない」と言い切るのです。
確かに、その会社さんが置かれた環境に照らすと、そうした交渉が行いやすい。実際、直近で賃借をやめた営業拠点では、原状回復のための費用が少額で済んでいた。
なるほど、ビジネスって、そういう力なんだと感心しました。「契約だから支払います」ではなく、いかに知恵を出して会社のキャッシュアウトを少なくしていくか。実務というのは、そうして工夫していくものなんだと。
本来、会計とは、ビジネスの実態に照らして適用していくもの。そうだからこそ、決算書はビジネスの一面を表現することができる。
しかし、その順番を反対にして、会計のルールありきで、ビジネスの実態を無視して適用していくと、決算書で表現するものが歪んでいく。それでは本末転倒。そんな本質を、管理部長から教わりました。
こうした実務の力は、本社で聞く以上に、現場で見たほうが理解は早い。まさに、百聞は一見にしかず。だから、ボクは監査で、現場に行くのがスキ。もう、大スキーと言っていい。だから、私を現場に連れてって。