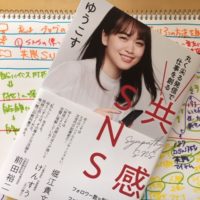子どもの頃に苦手意識があったものでも、大人になったら平気になるものがあります。ボクにとっては、ライティング。つまり、文章を書くこと。
昔は、何を書くべきなのかがさっぱりわかりませんでした。単行本を書ける人を心底尊敬したものです。よく、200ページ以上の原稿用紙を書けるなァと。学生の頃は、それこそ小学校から大学まで、文章を書くことはとにかく苦手。沢山書ける人を見ると、それが信じられないと心底思っていました。
それがいまや、当時のボクからしたら、とんでもないボリュームを短時間で書き上げていることに驚き。今日、とある文章を書くために、パソコンに向かっていました。そのボリュームは、このブログ以上。結構、書かなきゃならない。
で、結果として書いた文字数は、8,939文字。2時間かからずに、パソコンに打ち込んだ文字数がこれ。かなり入力できたと思いませんか。
日本語ワープロ検定試験によれば、1級の入力文字数は、10分間で700文字以上。ボクが120分で8,939文字打ち込んだとすると、10分間では744文字を入力できたということ。1級はクリアできた水準。
本当の1級合格には、1ミスに対する減点や漢字含有率などの観点も含まれますが、時間当たりの入力文字数といえば、10分間で700文字以上が1級のレベル。すると、今日のボクの2時間足らずの成果は、ワープロ検定の1級並みということ。
この成果を400字の原稿用紙に例えると、2時間足らずで22枚を仕上げた計算。いやいやいや、学生の頃のボクにしては信じられないスピード。400字の原稿用紙を1枚書き上げるのにも、ヒーヒー言って何日もかけていたのが、今やたったの2時間足らずで達成しているのです。あの頃のボクに、今の方法論を教えてあげたい。
もちろん、単なるファースト原稿の入力であって、これから推敲すると、減らすところもあれば、増やすところもあるでしょう。とはいえ、これまでの経験に照らすならば、もっとページ数が増える見込み。推敲していくと、これ以上のページ数になる、ということ。
このように、学生の頃とまったく違う世界が見られるのは、効果的なライティングの秘訣を知っているから。
ライティングの肝は、ワンステップではないこと。ツーステップもスリーステップも踏む必要があります。そうしたステップを踏むほどに、実は、ライティングが楽になっていくのです。
ライティング、すなわち、パソコンに入力していく作業は、何気に時間がかかるもの。これを最短にするためには、3つの秘訣があります。
1つ目は、素材をすべて集めること。集めた材料の中で書ける状態を作ることが何より大事。書き始めた後に、これも必要、あれも必要、という状態になると、手戻りが生じて不効率極まりない。だから、書くことになる候補の素材をすべて集めきることが重要なんです。
2つ目は、集めた素材を必要なものだけにしたうえで、伝える順番に並べること。いくら、素材を集めても、それを伝える順番を整理しないままにライティングを始めてしまうと、手戻りが生じてしまいます。そのため、伝わるための順番どおりに素材を並べ替える必要があります。
3つ目は、パソコンへの入力時間を短縮すること。実際にキーパンチを前提したときには、自身の指先の動きがキーとなる。それが遅ければ、そのスピードがボトルネックとなってしまいます。
今日、ボクが2時間足らずで、ワープロ検定1級並みに入力できたのは、音声入力のおかげ。パソコンに向かって話すだけで、予定していた以上の文字数がパソコンに入力できたのです。もちろん、これは粗々のファーストライティングのため、これから手直しが大幅に入ります。しかし、推敲する手間よりも、入力する手間のほうが精神的にはるかに大変。
何もない真っ白なページに向かってゼロから文字を入力していくよりも、すでに入力された文字を修正していくほうが気分的にラク。真っ白なページをゼロから埋めていくのは、経験がある人ならわかると思いますが、結構、大変な作業。だから、この作業はとにかく避けたいところ。
また、自身の指先でキーパンチするときには、回り道できないプレッシャーがあります。これはボクだけかもしれませんが、当初決めた文言以外にはキーパンチすべきではないと思い込みがちなんです。
しかし、セミナーや研修の場では、映写しているスライドを読み上げるだけではなく、その場の状況に応じて、適宜、付け加えたり、修正したり、削除したりしています。これをキーパンチしていく中で行うのは、結構、大変なこと。
これが音声入力だと、説明している状況で、想定する相手の理解度に応じて、伝えたいメッセージの言い換えだったり、その具体的な説明をもっと厚くしたりと、さまざまな対応が図れます。この対応をその時々の状況に応じて、決断していくのです。
今のスキルとマインドが学生の頃にあったなら、一体、どうなっていたか。それを考えることは、お酒のツマミになりますね。あなたが夢中で話し出すこと。それがあなたのキャリアの中心を占めるべきものかもしれませんよ。