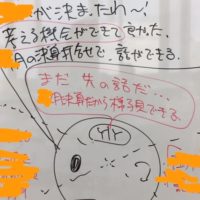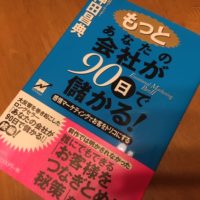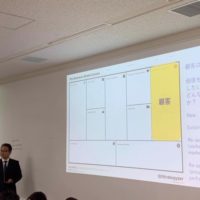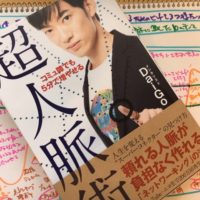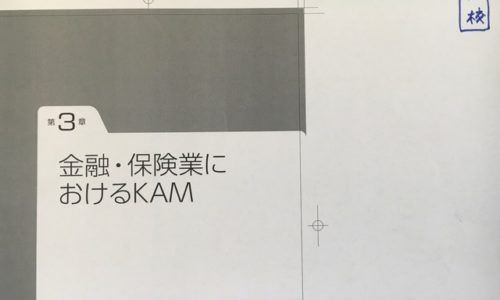あなたは、すごいコンサルに直面したことがあるだろうか。ボクは数年前、偶然にも究極のコンサルティング現場に居合わせたことがあります。
ある専門家と、その方のオフィスでお会いしていました。その専門家の雰囲気をわかりやすくするために、関西弁を話す「大阪さん」という仮称で呼びたいと思います。
途中で、大阪さんのクライアントが訪ねてきます。大阪さんはクライアント対応のために、すぐ隣の相談ブースに移動します。簡易な間仕切りのため、ボクが座っていた場所から、そのコンサル現場を垣間見ることができました。もっとも、その現場を見せる意図だったのかもしれません。
そこでのやりとりは、次のとおり。
「大阪先生、今日は相談があってまいりました」
「はあ~」と、どこか宙を見ながら、味気ない返答をします。
「実は今、我が社はコレコレという状況にありまして」と簡潔にまとめた説明を始めます。しかし、大阪さんは、うんともすんとも言いません。ただ、宙を見ながら、だまって話を聞いています。それでも、そのクライアントは話を続けます。
「そこで調べてみたのですが、Aという対応をとったときには、Bというメリットが得られます。しかし、Cという対応だと、Dというデメリットのほうが大きくなります。そこで、Aで行きたいと思うのですが、いかがでしょうか」
これを聞いて、大阪さんは数秒、目を閉じた後、こう、ボソリとつぶやきます。
「そやな~」
この返答を聞いたクライアントは、「ありがとうございます。では、Aで進めてまいります」と、深々と頭を下げて感謝しているのです。この光景に遭遇した瞬間に、「これが、究極のコンサルだ」と確信しました。その名も、「そやな~システム」。
表層的なところでは、大阪さんがクライアントにつれない素振りを取ることで、クライアントは関心を惹こうと一生懸命に話し出しています。ツンデレ的な態度がかえって、相手がこちらを振り向かせようと頑張りだす。
ところが、それだけでは究極のコンサルにはなりません。もっと、深いことが読み取れるのです。それは、クライアントを専門家に依存させていないこと。つまり、自立して判断できるように導いているところです。
何も、専門家がラクしているのではありません。クライアントは、大阪さんに相談を仰ぐところ、すべて自身で調べ上げて、自身で結論を出しているのです。こうした学びの姿勢を身につかせているのがすごい。コーチング的なアプローチなのです。
それに対して、クイックレスポンスを謳っている専門家がいます。すべてがすべて悪いワケではありませんが、レスポンスが早いことと品質が高いことは別の話。クイックレスポンスと聞くと、あたかも品質が高いようなケースだけを想像しますが、品質が悪いケースだって当然にあり得る。
よほど知見を重ねた専門家ではない限り、クイックレスポンスで品質が高いことはない。そこでのレベルに至った年月や努力を踏まえると、相応の報酬にならざるを得ないから。安価でクイックレスポンスを謳っているときには、注意が必要。
そういう意味では、ボクは組織に対してワークショップ型のセミナーをする機会があるため、そこに参加している従業員さんの様子を間近で見ることができます。グループワークでは助け合い学習をしていくと、事前にもセミナー冒頭にも説明しているにもかかわらず、途中で電話が鳴って席を外すのです。それも、頻繁に。
たった数時間も集中することができないのです。グループワークをすると言っているのに、お客さんからの電話だという態度で平気で中座してしまう。私は忙しいとアピールしているつもりなのでしょう。
しかし、そういう人は、単にコントロール権を握れていないだけ。大阪さんのように、クライアントを自立させるように導くのではなく、いつまでも依存させるように無自覚に行っているのです。
もちろん、「依存させる」という明確な意図をもっているなら、まだ救われます。ボクの好みではありませんが、そういう営業戦略もあるのは事実。
ところが、そうではなく、ただ単に作業を中断させられることを強いられているなら、話は別。本人の作業効率は落ちるわ、クライアントは自立できないわで、良いことが何もない。なんだか、哀れんでしまいます。きっと、大阪さんのようなコンサルを知らないのでしょうね。
自分の仕事はこういうものだと思い込んでしまうと、いつまで経っても、自分自身をコントロールできない。だから、無知を知っていくように視野を広げることが大事。そういう意味では、この「そやな~システム」は世界観がひっくり返されるような話だと思うのですが、あなたはどう思う?