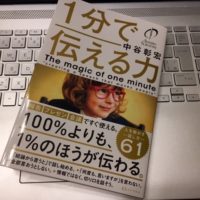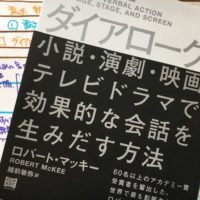セミナー講師をする機会が多いため、講演やセミナーが上手な人のやり方を研究しています。ボクが注目しているが、出だしのところ。どうやってセミナーや講演の本編に誘導しているか、そのやり方に関心を持っています。
というのも、最初に参加者の興味を掴まなければ、その先の本編をしっかりと聞いてもらえないから。本編を理解してもらいたくてセミナーや講演をしているのに、そこに辿り着いてもらえないと意味がなくなります。
だから、オープニングのところで、参加者の興味をどう惹きつけているかを分析しているのです。ここで発見したのが、参加者に共感してもらうための言い方。いかに多くの参加者に「これは、自分のためのセミナーだ」と思ってもらえるような表現の仕方があるのです。巻き込みの作法が。
この作法は、誰にでも当てはまるような言い方をすること。講演やセミナーが上手な人のオープニングを注意深く観察していると、ほぼ、これを活用していることがわかります。これに気づくまでは、「確かに、ボクもそう」と頷いていたものです。こうして知らずと、セミナーや講演の内容に巻き込まれていったのです。
その言い方で一番カンタンなのは、「A or Not A」のパターン。このパターンでは、必ずどちらかに当てはまります。例えば、「○○について取り組んでいる人もいれば、まだ取り組んでいない人もいるでしょう」という表現の仕方。
Aしか言わなければ、Aに当てはまる人は「自分のことだ」と感じるものの、Not Aの人は「自分のことじゃない」と感じてしまいます。すると、単純計算で参加者の半分の人の関心がそこで終わってしまう。つまり、半分の人が本編をちゃんと聞いてくれなくなる。
しかし、AだけではなくNot Aにも言及することによって、「ボクもそう」だと頷いてもらえる。その瞬間に、参加者のすべてを巻き込むことができるのです。
ただ、「A or Not A」のパターンは、あまりにも参加者にバレやすい。「そんなの、誰にでも当てはまるだろ」と冷静に聞いている人もいるからです。あっ、ボクもその一人か。なので、もう少し手の混んだ言い方にすると良い。
そのときに使えるのが、MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)。「漏れなく、ダブリなく」という意味。ミーシーやミッシーと呼ばれるフレームワークのこと。「A or Not A」という単純なパターンではなく、漏れなくダブリもないようなパターンにしていきます。
このときに使い勝手が良いのは、構成要素による分解。例えば、売上について話をするときには、会計の世界では、売上高は単価と数量とを乗じて算定されるため、この2つに分解します。また、マーケティングの世界では、単価と客数と購入頻度の3つに分解されることがあります。
これらを使うと、巻き込みの表現はこうなります。「売上アップについて、単価を上げたいと考えている人もいれば、来客数を増やしたいと考えている人もいるでしょう。あるいは、リピート率を高めたいと考えている人もいるかもしれません」と。
このように漏れなくダブリもないような表現をされると、参加者の誰もが「これは自分のためのセミナーだ」と感じるようになるのです。3つとも該当する場合には、もう本編を聞かざるを得ませんよね。
さらに進化させると、これを質問の形に変えます。「売上アップで単価を上げたいと考えている方はどれくらいいるでしょうか。挙手をお願いします。では、来客数が課題だと捉えている人は手を挙げてみてください。はい、それでは、リピート率に悩んでいるという人はどの程度いらっしゃるでしょうか」という感じで。
ここで参加者に手を挙げる動作を求めることで、耳以外の感覚を使うために、学習上の効果が得られます。つまり、積極的に参加するようになるのです。
こういう巻き込みの表現をセミナーのオープニングで使うことで、参加者の関心が高まっていくと期待できます。あなたが講師をするときには、ぜひ一度、お試しください。