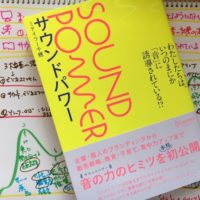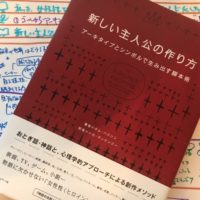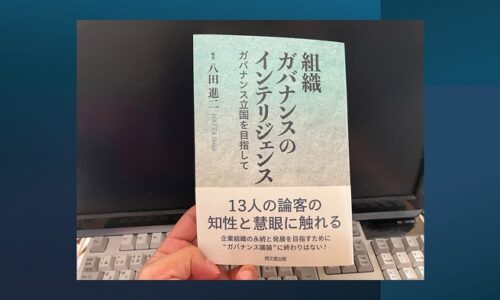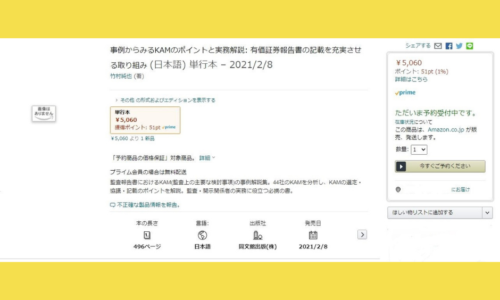反面教師という言葉がありますナ。正しいことを教える教師から学んだことは、みな、実践しようとします。その通りにすれば、良い成果を期待できるから。
それに対して、正しくないことを教える反面教師からは、みな、それを実践しないようにします。同じように振る舞っては、期待する成果が得られないため。
以前に、ある研修に参加したときのこと。そのときの講師を聞いて、ボクとしては参加したくない研修でした。なぜなら、その講師が、ボクにとっての反面教師だから。
できれば参加しないようにしたいのですが、ある立場上、参加しない訳にはいかない。そのときも直前まで欠席しようかと悩んでいました。でも、やむを得ず、参加することに。
で、参加したところ、激しく後悔。反面教師バリバリだったのです。いつも以上にバリバリだったかも。
何が嫌かというと、勝手な決めつけで参加者を罵倒すること。事実を確認することなく、思い込みと偏見をぶちかましてきます。
人前で主張するには、事実と根拠がなくてはいけない。これは、スティーブン・トゥールミンが1960年ごろに議論の作法を説いて以来の、ロジックの最低限の3要素。
ロジカル・シンキングを嗜む人なら、マッキンゼーの「雲・雨・傘」の型をご存知かと。傘を持って行こうと主張するときに、それだけだと「何で?」となります。その主張が受け入れられなくなります。
そこで、まず、「空に雲が広がっている」という事実を述べます。事実のため、誰も反論できない。しかし、この事実だけでは、傘を持っていく必要性がありません。
次に、「その雲は形状や色から、雨雲だ」という根拠を提示します。事実に対するその人の解釈を伝えるのです。その根拠に納得すると、呼び掛けられた人は傘を持っていきます。
このように、主張するなら、事実と根拠が不可欠。その2つがなければ、主張するのは自由だけれど、戯言に過ぎない。
ボクが嫌々、参加した研修の講師は、事実と根拠がないままに、主張だけ押し付けてくる。俺様の言う事に従え、と言わんばかりに。
その反面教師を分析した結果、事実や根拠がないと、主張が大雑把になることがわかりました。何でも一括りにしてしまうのです。例えば、こんな感じで。
・男たから。女だから。
・若いから。年配だから。
・そういう業種だから。
そんな主張は、客観的なデータに基づき、かつ、受け入れやすい根拠がある場合には、聞く耳を持ちます。「なるほどねー」「確かに、そうだねー」とうなづき、その主張を受け入れる。
しかし、その主張が寄って立つ事実と根拠がなく「お前らはダメだ」的な話をされても、反発しかない。「適当なことを言うな!」でしょ。
権威があるのかどうかは知りませんが、勝手にウワァーウワァー言われても、「知らんがな」しか言葉がありません。
参加者の聞きたいことを話すのではなく、講師の話したいこと、しかも、説教じみたことを話しまくる。そんなの、自慰行為ですから。一人でやってろ、でしょ。
しまいには、「こんなに空席が目立つなんて、どういうことだ」とキレる始末。そりゃ、あなたが、人の予定も構わずに押し込んだ研修だと、そうそう人は集まらない。得られるものがない研修だと、なおさらのこと。
この反面教師から学べることは、決めつけで人に説教しないこと。他山の石ですね。