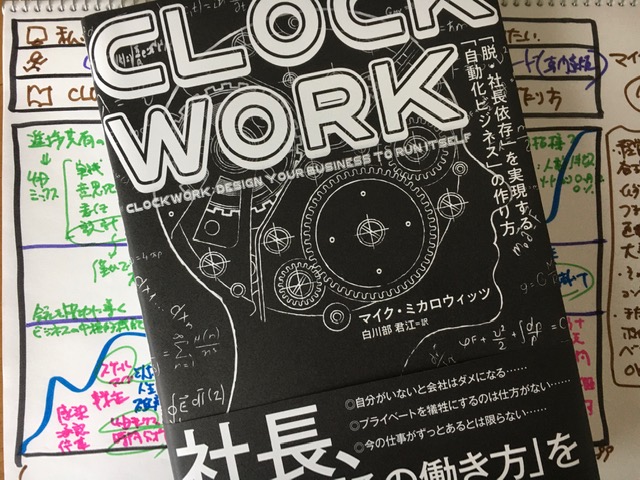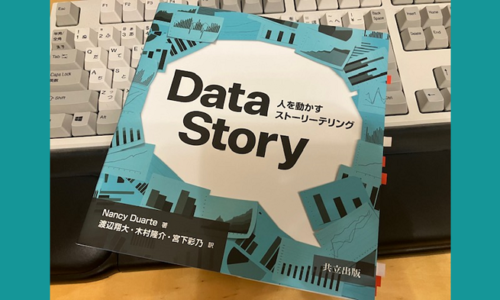AIという言葉も随分と大人しくなった印象がありますね。一時は、何もかもがAIに置き換わると大騒ぎしていたのに、今はそうでもない。これも、実務に進むと、何気に難しいからかと推測しています。
というのも、いわゆるAIを実務に適用するためには、現状の業務をすべてデータ化する必要があるから。そもそも、AIに検討を任せるデータがないのに、AI化なんて無理。AIの導入から躓いてしまう。
AI化の導入ステップを知っている人なら当たり前のことですが、対象となる業務がデータ化されていないといけない。営業のAI化なら、いつ、どこで、誰が、何を、どうした、というデータが記録されていないと、AIは検討するためのネタが手に入らないから。
何かシステムを導入すれば解決ではなくて、そのシステムを動かすための環境が整っているかどうかが大事。それはAIでもRPAでも何でも同じ。AIに関する研修論文でも、データを研究に活かせるための前処理が大変だと言われているとおり。
反対にいえば、データ化できれば何かしら業務を改善することができる、ってこと。つまり、業務の「見える化」ができれば、その先を打つことができるのです。だから、フローチャートや何かで「見える化」に務めるワケです。
今日、そんなことを再認識させてくれる本を読みました。それは、『CLOCKWORK 「脱・社長依存」を実現する「自動化ビジネス」の作り方』(ダイレクト出版)。著者は、『PROFIT FIRST お金を増やす技術――借金が減り、キャッシュリッチな会社に変わる』(ダイヤモンド社)が有名な、マイク・ミカロウィッツ氏。
この本は、社長ががっつりと働かなくても良いような仕組みを説いたもの。そのために最初に取り組むのが、4Dミックスの分析。4Dとは、ビジネスにおける時間配分のこと。
4Dとは、「実践(Doing)」「意思決定(Deciding)」「委任(Delegating)」「設計(Designing)」の頭文字。この配分が、理想的な状態と現状とがどれだけ乖離しているかを認識することから始まります。
ここで登場するのが、「時間分析ワークシート」。過去5日間の作業について、事細かく振り返る。つまり、どんな行動をしたのかを「見える化」することから始める。これをするからこそ、理想と現状との乖離が見えるため、改善に向かえるのです。
元となる活動の記録がなければ、改善も何もない。何を増やし、何を減らし、また、何を新規に追加し、何をまったくなくすのか。それらを検討する基礎がなければ始まらない。
でも、この活動の記録がなかなか行われていない。それができていないのに、AI化はおろか、IT化すらできない。RPAと叫んでいる経営者もいるようですが、完全に話題に振り回されている状態。
凄いツールで一撃なんて、基本、あり得ない。楽勝な裏技なんて、実務にはありません。コツコツと積み上げているからこそ、ITやAIによって爆発的に成長できる可能性があるのです。
もし、IT化やAI化で業務を無人化するなら、今の業務をデータとして記録しなければならない。困りごとに向き合うことなく課題が解消されることを期待するなんて、狂気の沙汰。
とりあえず、データ化できるように仕組みを考えましょう。それができたなら、飛躍的に成長することが目の前に現れますから。