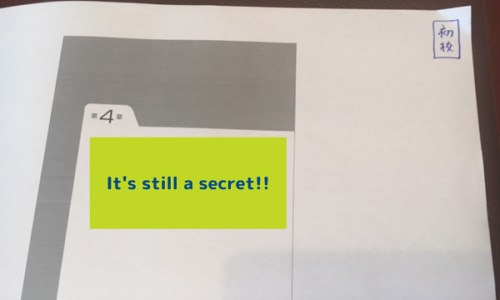世の中、知らないところで踏み絵が仕込まれているワケで。あるコミュニティに受け入れられるかどうかを、コミュニティの運営者側が見極めるために実施する、罠のようなもの。
以前に、京都に旅行に行ったときのこと。夜ご飯に、評判の良い和食料理店を予約しました。小さなお店で、カウンターに座ります。ちょうど、料理をさばく場所の目の前であったため、お店の大将と話したり、調理している様子を見たりと、ボクらは存分に楽しめました。
最初にボクはハイボールを、連れはビールを注文します。ところが、最初に提供された料理を一口食べるなり、「これはもう日本酒だよね」と確認しあう。メニューリストにはワインなども記載されていたものの、続く料理も魚を中心とした和食のため、日本酒しかないと確信しました。
そんな会話を聞いていたのか、大将が「次は日本酒にしますか」と尋ねてくる。で、オススメされた日本酒を注文。その後、絶妙なタイミング提供してくれる料理とともに、幸せを感じていました。
しばらくして、隣のカウンター席に二人組のお客さんがやってきます。どうやら初めての来店っぽい。40代から50代くらいの男女。風貌は決して上品とはいえないような二人。
彼らはいきなり、シャンパンのボトルを注文します。ドリンクメニューでは一番高い値段が記載されていたもの。確か、15,000円からと書いてあったハズ。
これ、今思うと、踏み絵だったと感じています。まったくの推測にすぎませんが、そのお店では選んではいけなかったお酒。
その証拠に、その二人が注文した料理は、食べることを確認することなく次々と提供されます。二人の前には手をつけていないお皿でいっぱい。しかも、大将が「お皿がいっぱいになって、すみませんね」と声をかける。勝手なイメージですが、いかにも京都っぽい、あしらい方だとおもいませんか。
ボクらにも、ボクらの前に来ていた客にも、そんなペースでは料理を提供していない。順番もペースも、しっかりと見計らって差し出してくれています。手を付けていないお皿がまだ残っているのに、あれもこれも提供するなんて考えられない。これはもう、早く帰ってくれ、というメッセージでしょ。
もしかすると別の踏み絵を踏んだのかもしれませんが、いずれにせよ気に入られなかったことには違いない。こんなメッセージを出すこと自体は、珍しいことではありません。そのお店が求めるお客さんでなければ、嫌われるだけ。
踏み絵を設けることは、何も悪いことではありません。多くは、常連を守る意味が強い。料理の味だけではなく、食器や会話、内装など全体的なサービスこそが価値提供だから。それを台無しにするような客は、価値提供を阻害し、また、常連さんの気も悪くしてしまうため、排除すべき存在。
このお店以外にも、踏み絵のある飲食店は普通に存在しています。もっと言えば、飲食店以外のビジネスにも踏み絵があります。
ある経営コンサルタントは、付き合う顧客を見極めるために踏み絵を設けています。受注から契約成立までのやりとりの中で、いくつかのチェックポイントを埋め込んでいるとのこと。それをクリアできないと、契約しないと言います。
例えば、期限。契約に至る前の間に、何かの資料を送ってもらうことがあります。この期限を守れない人は、契約が成立した後にも期限を守れない。その結果、コンサルティングの成果が生まれないことが想定されるため、こういう人とは契約しないそうです。
良いものを提供している人ほど、仕事に真剣に取り組んでいます。だからこそ、その相手である顧客にも真剣度を求めます。真剣に取り組まない人には、こちらが真剣になっているのはおかしな話。だから、その価値を提供するのは自分ではなくても良いだろうとなるのは至極当然のこと。
ビジネスでも、こんな風に踏み絵が仕込まれている状況は普通にあり得ます。ただし、真っ当である限り、踏み絵のことを気にしなくても、それを踏むことはありません。おそろくズレている人が排除されるのです。
もし、ビジネスが上手く行かないとすると、それはビジネスモデル以前に、真っ当でないことが原因かもしれません。真っ当ではない理由のひとつは、学ぶ姿勢がないこと。なので、不勉強な組織ほど、この踏み絵に注意が必要ですよ。