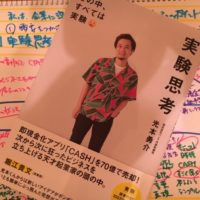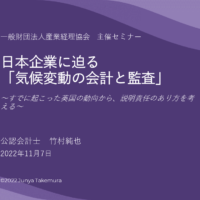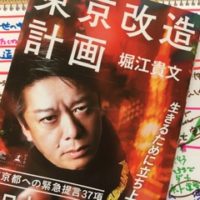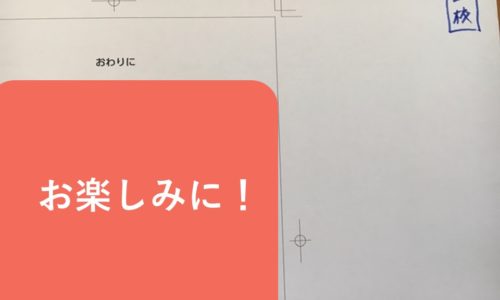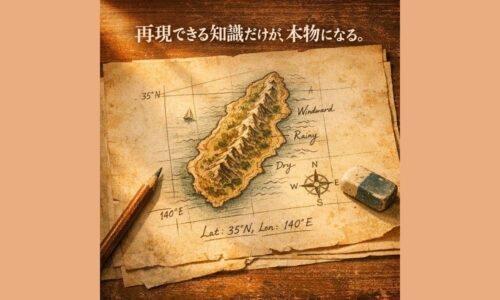海外の企業のアニュアルレポートを調べていたときに、ふと気づいたことがあります。12月決算の企業が、2月末から3月初めにかけて、監査人による監査報告書が付されたアニュアルレポートを発行しているのです。
欧州の企業であればアニュアルレポート、また、アメリカの企業であればSECに提出する10-K。いずれにしても期末日から2ヶ月ほどで有価証券報告書に相当する書類を外部に報告している。
一方で、日本では有価証券報告書の提出は、期末日から3ヶ月後。3月末決算の上場企業だと、6月末に近い日付で公表しています。ここを比較すると、1ヶ月近く遅い開示。
しかし、日本の上場企業は、決算短信のリリースも求められています。上場している証券取引所の要請によって、有価証券報告書よりも先に決算の状況を発表しなければならない。それも、監査人の監査が終わっていない段階で。
ここで思うことは、次の3点。
1点目は、決算短信は表紙だけでよいのではないか、ってこと。もともと証券取引所が求める決算発表とは、あの表紙の1枚、いや2枚だけ。それ以降の有報っぽい情報は、あくまでも添付資料という位置づけ。
実際、20年少し前までは、決算短信に添付する決算書は、当時の商法ベースで表示したものでした。当時の証券取引法ベースの表示も注記も求められていなかった。それがいつの間にか、ミニ有報を添付するような運用になっていったのです。
これは負担以外、何者でもない。だって、海外ですらアニュアルレポートは期末日から2ヶ月経ってからの公表のところ、それに近い開示を1ヶ月以内もしくは45日以内で求められているから。1ヶ月程度じゃ、売掛金や買掛金のキャッシュの動きすら追い込めない。
ここから、ミニ有報の添付まで求める必要はないでしょ、っていうこと。あくまでも決算短信の表紙だけで十分であって、添付資料まで求めるから現場が大変になるのです。
続く2点目は、監査が終わっていない財務数値を公表すること。今の決算短信では、監査を受けていないものだと明記するようになっています。少し前に議論となったことから、このような取扱いになっています。
しかし、そもそも監査を受けていない財務情報を開示することの是非がもっと問われるべき。実際、とある証券アナリストが某研究学会で話していたのが、決算短信を監査後に公表している企業を評価している、とのこと。
そりゃ、財務情報の利用者にとっては、監査を受けていない情報なんて開示するな、って思いは強いハズ。そのあとで数字がひっくり返っては、投資の意思決定に使えないから。決算発表の早期化が実現されても、公表される決算書に保証が付されていないなら、意味がないのです。
ここから、決算書は監査を受けたものだけが公表されるべき、っていうこと。決算短信のように決算書の一部の財務情報は100万歩譲歩して良いにしても、添付される決算書は監査を受けたものに限るべき。
で、最後の3点目は、有報に相当する情報の開示は、1ヶ月でなくても良いこと。まず決算短信はミニ有報の添付までは不要と話しました。純粋に表紙で十分だと。次に、監査を受けた決算書が開示されるべきだと。
有報が今のとおり期末日から3ヶ月後だと、欧米のアニュアルレポートと比較して開きが生じてしまう。であれば、決算短信は表紙だけにしながらも、有報は2ヶ月程度で、もちろん監査済み、という仕組みが良いのではないでしょうか。できれば、決算短信の表示単位も高めにして。
少し気になるのが会社法との関連。株主総会を経なければ決算が確定しないのではないか、ってこと。しかし、今では、株主総会よりも前に有報を提出することも認められています。であれば、あまり問題視しなくても良いハズ。
資本市場のグローバル化に進むのであれば、日本が突出している実務を見直すこともしていい。このとき、遅れている実務も合わせて改善する。こうしたセット技で良いのではないでしょうか。
2020年、そろそろ開示の大改革が起きて欲しい。それに向けて、このブログ記事をシェアしながら、コメントを付すのはどうだろう。