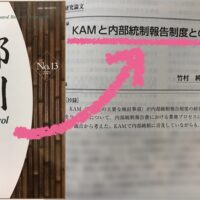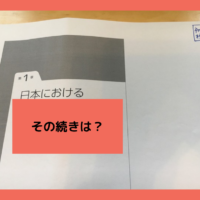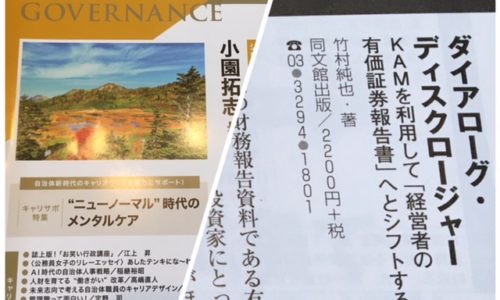こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。
監査人からKAM(監査上の主要な検討事項)のドラフトを渡されたときに、その内容次第では、企業は追加の開示が求められることがあります。そういう意味でも、経営者や監査役等の立場にある方は、その決定の適否についての検討が欠かせません。
とはいえ、KAMが適切に選ばれたかについて、企業側として、どう判斷すれば良いのでしょうか。監査のプロが選んだものに対して、どこに着目すれば良いかに困っているかもしれません。
そんなときには、KAMの決定理由をご覧になってはいかがでしょうか。決定理由として記載された内容に納得がいくかどうか、という観点からKAMの決定の適否を検討していくのです。
頻出するキーワード
日本におけるKAM早期適用事例をよくよく分析していくと、KAMの決定理由について、頻出するキーワードを見い出せます。つまり、監査人がKAMを決定するための観点がいくつかに絞り込むことができるのです。
頻出するキーワードが理解できれば、それが自社にとって当てはまるかどうかが判斷できます。そのため、経営者や監査役等としてもKAM決定の適否について検討しやすくなります。
これについて、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)の19ページでは、5つの事項のどれか、または、その組み合わせとなる傾向があると、紹介しています。これを知っているかどうかで、KAM検討のしやすさが随分と変わるはずです。
ただ、悩ましい点があるのも事実。それは、拙著で紹介した5つの事項は、事例を観察することで抽出していること。
確かに頻出しているキーワードであるものの、体系的かどうかの保証がありません。それでも実務で役立つなら意義があると考えたことから、紹介した次第。
体系的な観点が登場
ここで、朗報。それを体系的に整理したものが登場しました。
それは、2021年2月26日にJICPAから公表された、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の公開草案。まだ確定していませんが、そこの記述がKAMの適否判斷に役立つのです。
この内容は、JICPAによるまとめ資料「参考資料(監査基準委員会報告書315の概要)」に、コンパクトにまとめられています。5ページから8ページまでをご覧ください。
今回の公開草案では、「固有リスク要因」という概念が導入されました。簡単に言うと、内部統制がないと仮定したときに、財務諸表に不正やエラーを生じさせやすい事象や状況のこと。
例えば、「新しい会計基準の適用」という変化があると間違えやすい、というもの。この固有リスク要因が、体系化されたのです。
固有リスク要因はこの5つ
固有リスク要因として、次のとおり、5つが例示されています。
- 複雑性
- 主観性
- 変化
- 不確実性
- 経営者の偏向又はその他の不正リスク要因が固有リスクに影響を及ぼす場合における虚偽表示の生じやすさ
ほら、この5つって、KAMの決定理由に頻出するキーワードに極めて近い。しかも、この5つは明確に定義があり、また、具体的な事象や状況についても例示されているため、理解しやすい。
もちろん、例示のため、この5つに限らない。とはいえ、経営者や監査役等は、この5つの観点から、KAMドラフトの適否を判斷していくことができます。つまりは、使い勝手が良い、ってこと。
発展的な活用方法
もう、お気づきかもしれませんが、この固有リスク要因は記述情報にも活用できますね。
重要な会計上の見積りに関する記述情報はもちろんのこと、事業等のリスクや、経営方針等の箇所でも、こうした観点から重要度を検討していくことができます。
固有リスク要因が記述情報にも活用できる理由は、監査人はリスクアプローチに基づき財務諸表監査を行っていくためには、企業のリスクを見極める必要があるから。
そのための観点が「監査基準委員会報告書」という実務指針にまとめられています。ならば、企業側も、こうした観点から、リスクや重要度を捉えていくことが可能になります。使えるものなら使わなきゃ。
もしも、サポートが必要なときには、お声がけください。記述情報の充実に向けた取り組みも含めて、お手伝いいたします。