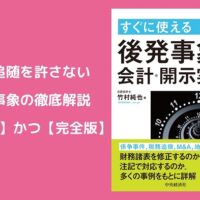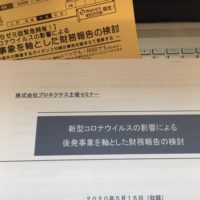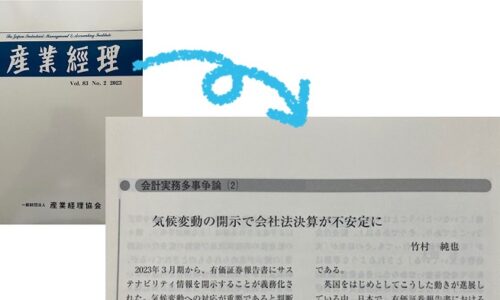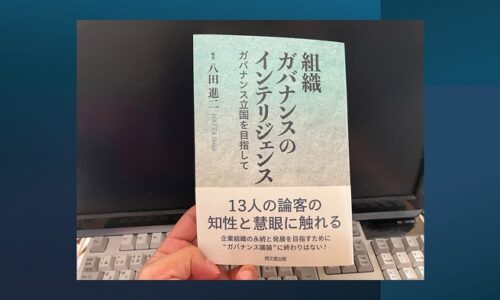家に帰るまでが遠足。これは、小学校のときに散々聞いたセリフ。最後まで気を抜いてはいけないことを注意喚起しているものです。
このセリフ、収益認識の新基準への対応についても、同じことが言えます。「注記を書くまでがシン収益認識の対応」だと。
先日、収益認識の新基準に関して、注記への対応が大切だと教えてくれる資料が公表されました。それは、2021年4月8日に、金融庁からリリースされた「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和3年度)」です。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210408.html
もうご覧になられたでしょうか。32ページ以降は、これから企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用しようとする企業にとって必見の内容です。
注目していたレビュー結果
金融庁は、毎年、有価証券報告書の記載内容を審査しています。その審査は、大きく「法令改正関係審査」「重点テーマ審査」「情報等活用審査」の3本柱で行われます。
ボクが注目していたのは、「法令改正関係審査」のレビュー結果。前年度は、「役員の報酬等」や「株式等の保有状況」の記述情報が審査されました。その結果、記載ぶりに改善の余地があると考えられる提出会社に対して、翌年度からの改善・充実に向けた検討を求める通知が、なんと3割程度の企業に出されたのです。
今回のレビューでは、2020年3月期から強制適用となった「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」「事業等のリスク」「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」などが対象とされました。これらの記載ぶりについて、前年度からの変更がみられない事例も少なくないため、前年度の記述情報への対応よりも厳しい結果になると予測していました。
その結果は、改善通知には言及がありませんでした。ただし、「法令で求める記載がない事例や法令が求める水準を満たすことのみを目的として最低限の記載をしていると考えられる事例も見られ、投資家が必要とする十分な情報が得られる記載とはなっていない事例も見受けられる。」とコメントされています。そのため、期待した状態ではないことが推察されます。
ノーマークじゃいられない「重点テーマ審査」
ボクの関心が記述情報に対するレビュー結果に向いていたため、正直、重点テーマ審査にはノーマーク状態でした。今回の重点テーマ審査がIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」であったため、IFRSを適用している企業だけの話だと勘違いしていたのです。
しかし、それは大間違い。そのレビュー結果が、日本基準を適用している企業、つまり、2020年4月1日以後に開始する年度から企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が適用される企業にとって大いに役立つ内容だったからです。
この重点テーマ審査では、IFRS適用企業が、顧客との契約から生じる収益に関する開示が IFRS第15号に基づいて適切にされているかが検討されました。検討にあたっては、質問を行うとともに、必要に応じて根拠資料の提出も求めています。開示された内容だけではなく、その根拠資料まで入手したうえで審査が行われています。
会計方針の文章まで用意されているか
重点テーマ審査の結果について、全般的な留意事項を示した次に、個々の内容を伝えています。その中から注目したい点をピックアップすると、次のとおり。
履行義務の充足時期の説明が、基準の表現の転記等の抽象的な内容にとどまっており、企業特有の収益の認識態様が具体的に説明されていない。
シン収益認識の下では、どのような履行義務を説明し、また、どのような時点をもって履行義務が充足されるかについて、個別具体的に開示しなければなりません。あらゆる業種を想定して会計基準が策定されているため、基準の文言を引用したような記載では、具体性がないため、財務報告の利用者が収益認識の仕方が理解できないからです。
その開示は、シン収益認識によって売上高の計上の仕方が変わる、変わらない問わず、求められます。影響を受ける項目がなかったからといって、収益認識の新基準への対応は終わらないのです。
いわゆる会計方針のような注記まで用意できていなければ、シン収益認識の対応は道半ば。まるで、遠足で行った先から学校まで戻ったような状態。家にまでは帰っていないのです。
要注意は、「収益の分解情報」
2020年8月に、注記まで検討範囲に含めないとシン収益認識の対応は終わらないことについて、緊急レポート「新・収益認識の対応プロジェクトが進まない理由」でお伝えしていました。入手された方が多数いらっしゃいますので、開示まで見越したうえで収益認識の対応を進め、終えている企業も少なくないでしょう。
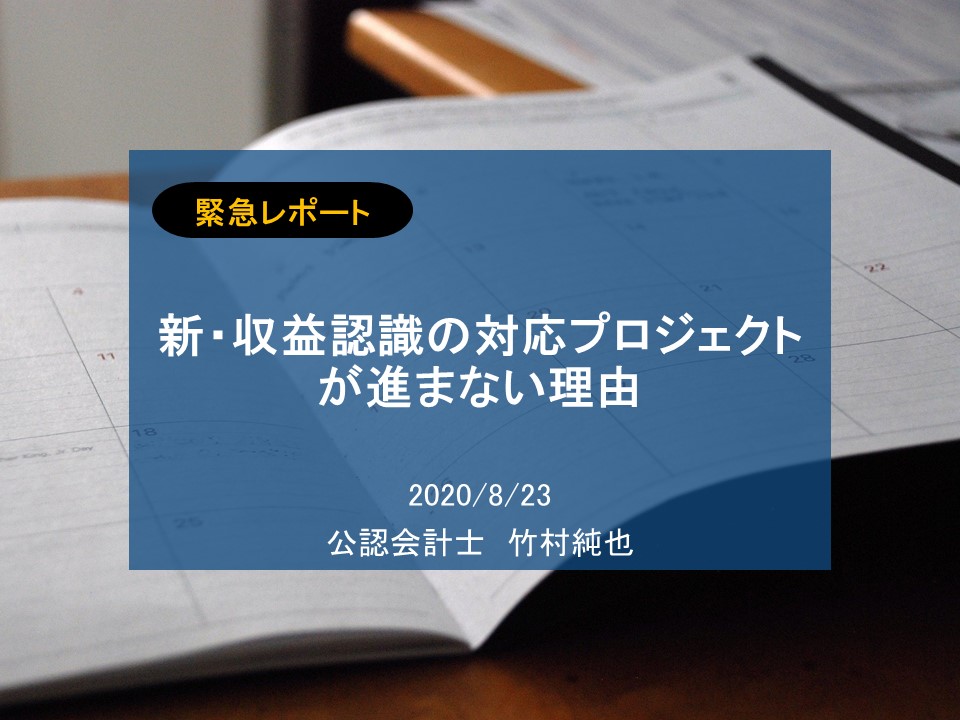
特に、収益の分解情報の注記は、四半期で求められる可能性があります。決算説明資料などでセグメント情報よりも詳しい情報を開示している場合には要注意です。開示が必要と判断されるときには、第1四半期から開示しなければならないため。3月末決算だと、2021年6月の四半期です。
もし、「まだ、家にまで帰っていない」状態のときには、お早めに検討することをオススメします。
P.S.
ボクが収益認識のコンサルで手放せない本は、ASBJサンによる『詳解 収益認識会計基準 (FASFブックス)』。遠足のおやつにバナナが含まれるかどうかは重大論点ですが、この本には基準や適用指針が含まれています。めっちゃ使い勝手が良いですよ。