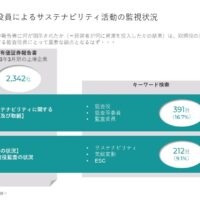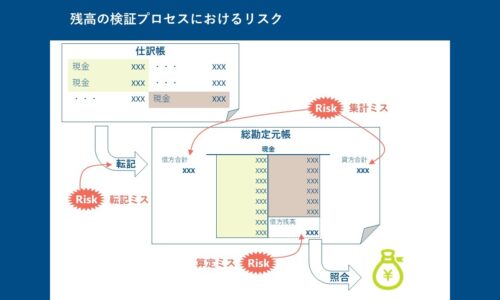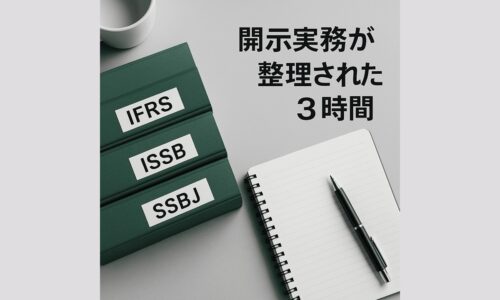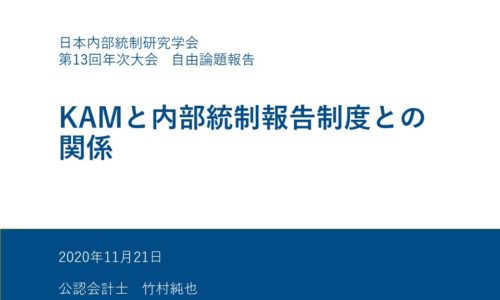先日、サステナビリティ基準委員会の審議動画を視聴していたときに、SSBJの委員長から興味深い発言がありました。
なんでも、IFRSサステナビリティ開示基準の中に、本来あるべき定め方をしていない規定があるというのです。このような規定となった理由として、各国制度に配慮したのではないかと推察されていました。
ここから、ある仮説がひらめきました。それは、サステナビリティ開示基準の設定にあたって、影響力を与えた主体は誰なのか、という点です。簡単にいえば、IFRSサステナビリティ開示基準が導入されることによって、誰が有利になるのか、または、不利にならないのか、です。
何らかのルールが作成される以上、それが適用される結果として、有利な状況や不利な状況が生じます。そのため、ルールメイキングにあたって、自身の組織に有利になるような働きかけが行われることもあるでしょう。実際、国内外における会計基準の設定にあたっても、そうした政治的な駆け引きもあったことが指摘されています。サステナビリティ開示基準の設定にも、同様のポリティクスが生じていてもおかしくはありません。
委員長の話を聞くまでは、サステナビリティに関する制度開示は欧州が先行しているため、てっきり欧州の企業が有利な流れだと思い込んでいました。しかし、S1基準の体系や導入背景、その後の展開などを考慮すると、必ずしも欧州の企業が有利とは限らず、むしろ不利になる状況も想定されます。
すると、有利になるのは、一体、どこか。それが自ずと導けます。これは、サステナビリティ開示を効果的に適用していく方法論が見えることを意味します。これまで、「この方法論が最も効果的な対応なんだろう」とおぼろげに考えていたことに根拠が得られた形となりました。
そこで今回の記事では、委員長の発言から、気になる規定ぶりについて共有します。これを知るだけでも、サステナビリティ開示への対応が過剰とならないような対策が図れるでしょう。また、仮説についても説明するものの、この仮説が棄却されたとしても、効果的なサステナビリティ開示の進め方について変わらないはずです。