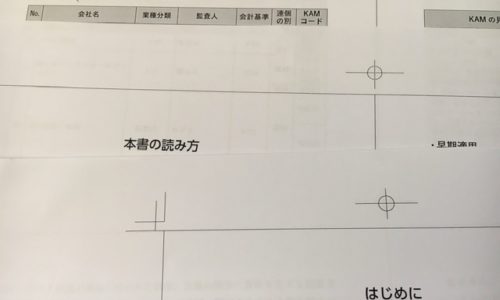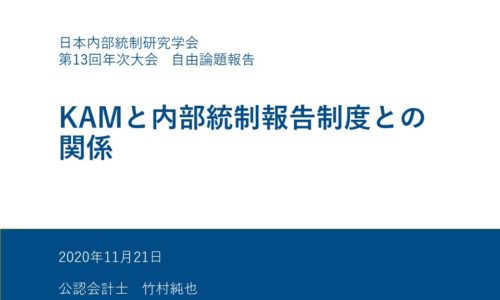昨日の2024年5月29日、役員向けのSSBJ基準(案)の解説セミナーを収録してきました。その控室で、主催者の方から興味深い話を伺いました。世界の主要国の中で上場企業数が増加しているのは日本だけという事実です。
その後、調べたところ、2023年12月12日付の東洋経済オンラインの記事が情報源であることが分かりました。
- 主要国の上場企業「減少時代」に日本で起きる変化 中小の退場ではなく大手の統合・再編が必要
https://toyokeizai.net/articles/-/720401
この話を聞いて思い浮かんだのは、SSBJ基準(案)が適用される範囲です。金融庁からは、プライム上場企業を最大枠とする方針が打ち出されています。この方針の拠り所については、解説セミナーで明確に指摘しました。したがって、この方針が大きく変わることはないでしょう。
ここで重要なのは、こうした方針によって上場企業の間で明確な線引きが生じることです。これにより、スタンダード市場やグロース市場の企業にはSSBJ基準(案)に基づく開示が義務付けられません。また、プライム市場の企業であっても、時価総額に応じて段階的に適用が開始されます。このように、サステナビリティ開示が義務付けられる対象は上場企業の中から選別されるため、開示義務を果たせる企業こそが「真の上場企業」とみなされる可能性があるのです。
もちろん、金融庁は、この方針がグローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業から始めることを意図していると説明しています。しかし、日本だけが上場企業の数が増加している事実と照らし合わせると、サステナビリティ開示を義務付ける有力企業を選別する動きとも捉えることもできます。そのため、上場企業を二極化する動きにつながる可能性があるのです。
実際、すでにサステナビリティ開示の状況は、全体的な傾向として、好事例に選ばれるような開示を行っている少数の企業と、そうではない大多数の企業とに区分されています。世界ではサステナビリティに関する情報が次々と提供されているため、常にキャッチアップしなければ、この差は広がるばかりです。
中には、「グロースだから」「スタンダードだから」「プライムだけど先行適用されないから」と様子見をしている企業もあるでしょう。これは非常に危険な姿勢です。なぜなら、サステナビリティ開示は関連する活動を実施していなければ、開示する情報がないからです。期末日を過ぎてからサステナビリティ開示のために急いでも、ありきたりな内容を記述するしかできません。そのような開示が評価されないことは明らかです。
したがって、会社のサステナビリティ関連の活動や開示のあり方を変えるためには、権限のある会社役員が危機意識を持つことが最も効果的です。セミナーの控室でその考えを改めて認識しました。
そうしたところ、今回のセミナーには、上場企業の代表取締役のお名前で受講を申し込まれた方がいらっしゃいました。この姿勢には深く感銘を受けました。その意識の高さに応えるべく、SSBJ基準(案)の開示要求だけでなく、会社としてのサステナビリティ対応の説明にも力を入れました。得られた気づきが、会社の中での新たな一歩となれば嬉しいです。
このセミナーはオンデマンド配信されます。SSBJ基準(案)の内容はもちろんのこと、それを踏まえた会社の対応についてのヒントを得るなら、配信期間が終了する前にぜひご視聴ください。