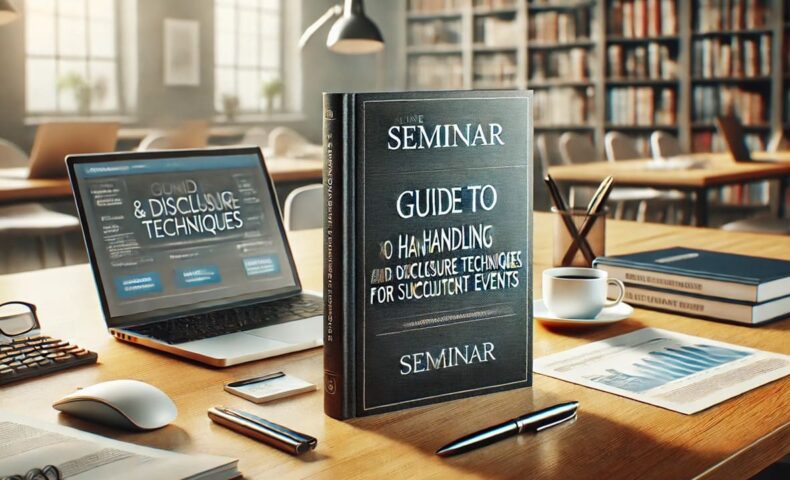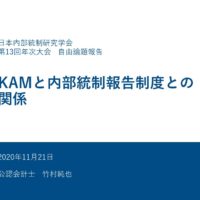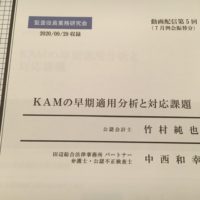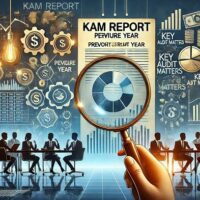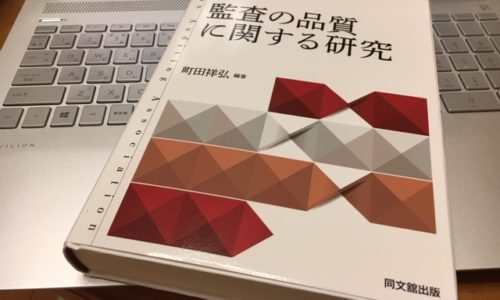2024年12月、財務会計の領域では、あまり注目されていないものの、実務面で影響を及ぼし始めているテーマとして「後発事象」があります。リース会計基準のような派手な話題ではないものの、着実な動きが出ています。その動きは、大きく2つに分類できます。1つは証券取引所による対応、もう1つはASBJ(企業会計基準委員会)による対応です。
■証券取引所における後発事象注記の省略
まず、証券取引所における動きから見てみましょう。2024年4月以降、第1四半期と第3四半期には四半期報告書の提出が不要となる一方で、四半期決算短信の開示に一本化されました。この四半期決算短信には「重要な後発事象の注記」を開示する義務がありません。結果として、開示後発事象が発生しても、強制的に注記を求めない状況が生まれています。
もともと後発事象の開示は、投資家が将来キャッシュ・フローを予測する手がかりを得るためのものです。実際、適時開示ガイドブックでも、企業による自発的な開示が推奨されています。そのため、今回の省略措置は後発事象の重要性を否定するものではありません。
しかし、投資家向け情報である四半期決算短信で注記義務が消えてしまったことに合理性は見出しにくいため、後発事象の意義を揺るがしかねない事態といえます。すでにこの制度変更は、実務に導入されています。
■ASBJによる実務指針の移管と基準開発再開
一方、ASBJでは、JICPA(日本公認会計士協会)による会計関連の実務指針を会計基準等へ移管するプロジェクトの一環として、後発事象の実務指針の扱いが検討されています。2024年6月には、過去に後発事象の基準開発が中断された経緯も踏まえ、実行可能性調査研究の結果が公表され、また、いくつかの課題が示されました。
その後、2024年8月に、ASBJは企業会計基準諮問会議の同意のもと、段階的なアプローチで後発事象に関する基準開発を再開することを決定しました。フェーズ1では、現行の実務指針の会計部分をほぼそのまま新基準として移管します。この審議は、2024年12月よりスタートしています。フェーズ2では、特例的取扱いの見直しなど、より突っ込んだ議論が行われる予定です。
■「修正後発事象」をめぐる難題と審議再開の背景
過去に後発事象の基準開発が停止した最大の理由は、会社法と金融商品取引法による開示制度が併存しているため、修正後発事象を一元的に扱う包括的な会計基準づくりが困難だった点にあります。
金融商品取引法ベースの開示では、会社法監査報告書日以降に発生した修正後発事象を、開示後発事象に準じて注記する実務が行われています。しかし、この特殊な処理を「会計基準」として包括的に定めることが難しいことから、議論は中断していました。
にもかかわらず、今回ASBJは「移管」を優先して再び審議を動かしています。過去の問題解決はフェーズ2で行うと割り切ることで、とりあえず基準開発を再開しているのが現状です。
■再燃する「レジェンド問題」の懸念
後発事象の会計基準を「移管」する過程で、もし修正後発事象を開示後発事象に準じて扱うことを会計基準に組み込んだとしても、海外のビッグ4監査法人がこれを認めなければ、約25年前に起きた「レジェンド問題」が再燃するおそれがあります。
「レジェンド問題」とは、2000年頃の会計ビッグバン期に、日本基準で作成した財務諸表を英文化する際、米国基準・国際基準との違いを示すために監査報告書へ警句を付した事例を指します。
- (参考)2004年6月17日開催、企業会計審議会第10回企画調整部会、資料2「2004年3月決算期におけるいわゆるレジェンド問題について(日本公認会計士協会)」
https://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/singi/f-20040617_sir/04.pdf
今回も海外勢の合意が得られなければ、日本独自の会計処理が再び国際的な不信や警戒を呼ぶことで、レジェンド問題が蘇る可能性が否定できません。さらに、フェーズ2になってから「移管は無理だった」と撤回することも困難なため、フェーズ1で適切な手を打つ必要があるのです。
■あまり知られていないが大きなインパクトを持つ動き
このように、後発事象をめぐる制度・基準の変更は世間的な注目は小さいものの、実務面で無視できないインパクトを持っています。この点も含めて、2024年12月20日の今日、収録したセミナー『実務に即応できる!後発事象への対応と開示テクニック ~制度別対応と記載の極意を押さえる完全ガイド~』で簡潔に解説しました。
セミナーでは、後発事象に「いつ」対応すべきかを実例とともに詳細に検討するとともに、開示後発事象の注記作成ポイントを提示しています。ここでの解説は、拙著にも収録していない新たな情報を含んでいます。また、JICPA指針よりも細かい時間軸で対応策を示しているため、実務担当者はより精密な理解を得ることができます。
このセミナー動画は、2025年1月15日から3月14日にかけて視聴可能です。セミナー資料は、表紙を除き113スライドというボリュームです。少しでも関心をお持ちの方は、ぜひご参加いただき、他では得られない情報を手に入れてください。