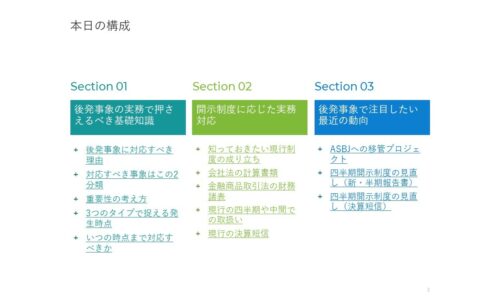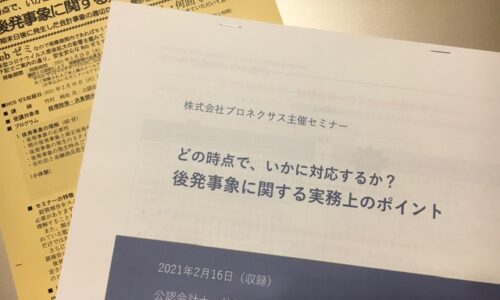2025年3月19日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の第50回会合では、単なる技術論を超えた本質的な問いが提起されました。それは、「SASBスタンダードは国際基準として格上げされるに値するのか」という、制度の正統性に関わる問題です。
現在、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)基準では、SASBスタンダードを企業が「考慮しなければならない」(shall consider)ガイダンスとして位置づけています。日本のSSBJ基準でもこの取り扱いが踏襲されているため、SASBスタンダードに関する議論は、企業のサステナビリティ関連財務開示の実務に直結する重要な論点となっています。
そこで今回の特別記事では、SSBJにおける議論を出発点とし、SASBスタンダードが抱える制度的課題を検証するとともに、今後の選択肢とその示唆について論じます。その内容は次のとおりです。
■国際基準「格上げ」の名の下に進む、静かな既成事実化
■地理的・制度的バイアス──「米国発」基準の限界
■リスクベース設計と制度的一貫性の不在
■SSBJの選択──「ゼロベース再設計」という戦略的決断
■いま問われるのは「制度のかたち」ではなく「制度の意味」
■今回の3つの重要ポイント
この記事を読むことで、デュー・プロセスの整備が制度の正統性を保証するとは限らないことを理解できるため、「形式に惑わされない」判断力が養われます。また、国際的な議論の現場で各国が何を問題視しているかを把握することで、自社に関係する制度上のリスクを見極められるようになります。さらに、リスクベース設計の構造的課題を認識することによって、自社の情報開示が制度的に不利な状況に置かれていないかを点検できるようになります。
制度は形ではなく理念によって支えられます。変化し続ける基準の本質を見極め、実務に活かす知識を手に入れることで、貴社の開示品質と信頼性は大きく向上するでしょう。ぜひ継続的な購読を通じて、制度の“今”と“これから”を捉える視野を広げてください。貴社の未来を支える洞察が、ここにあります。