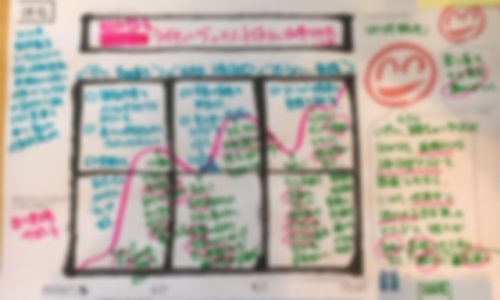サステナビリティ情報の開示が制度化されつつある今、最も注意すべき点は何か。ひとことで言えば、それは「誰に向けて書いているのか」を明確にすること。この一点に尽きると言っても過言ではないでしょう。想定読者を見誤ると、せっかくの開示も空振りになってしまいますからね。
かつて「環境報告書」や「CSR報告書」と呼ばれていた時代には、企業が想定していた読者は実に幅広いものでした。あるいは、そもそも想定などしていなかったケースもあったでしょう。そうした報告書が「企業のPRでしょ」と揶揄されたのも、ある意味では当然の帰結でした。なにせ、Public Relationsの名の通り、多様なステークホルダーに向けて広くアピールする内容だったわけですから。ただし、その内容が環境や社会への配慮をアピールすることに重点が置かれたため、「これって企業の宣伝では?」と批判されることもありました。
もし、今なお、その延長線上の開示を行っている企業があるとすれば、少々黄色信号かもしれません。なぜなら、ISSBやSSBJといった組織が定める開示基準は、これまでのスタイルとは一線を画しているからです。いわば「古い靴で新しい道を歩こうとしている」ようなものです。それでは靴擦れどころか、目的地にもたどり着けませんよ。