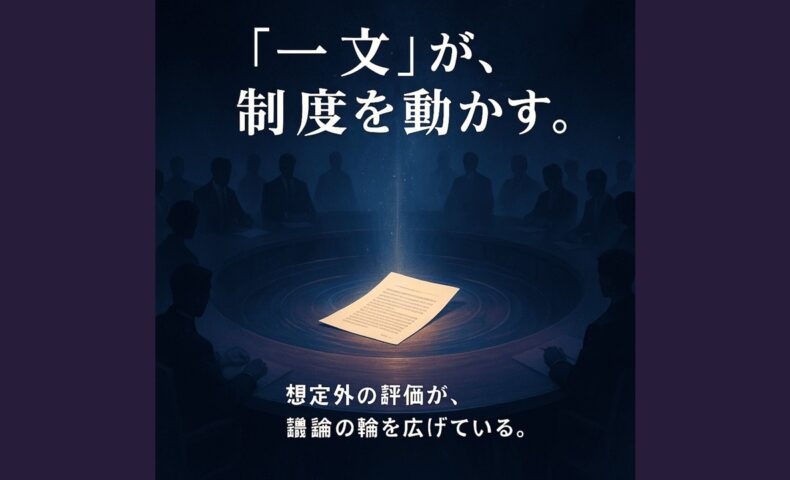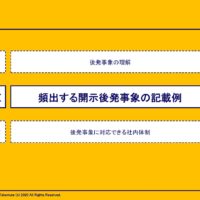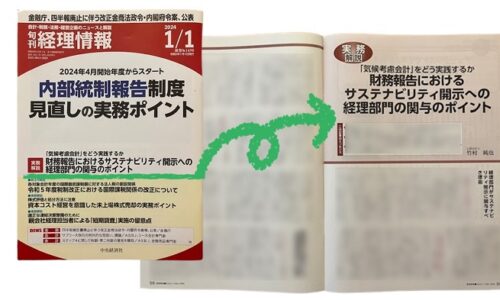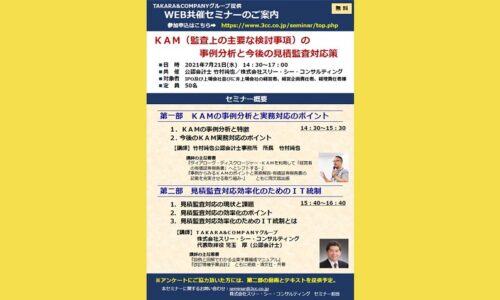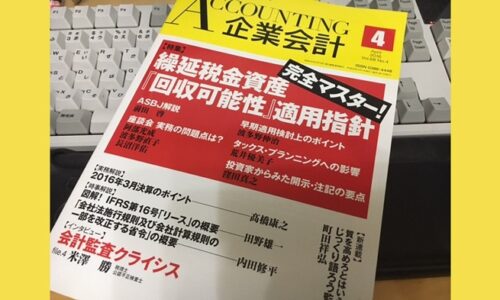2025年10月13日発行の週刊経営財務(No.372)のWEB限定コンテンツで、私が『企業会計』誌に寄稿した論考「後発事象をめぐる基準開発の本質を問う」が取り上げられました。それは、「Q&Aコーナー気になる論点(398)後発事象の会計基準案-特例的な取扱い-」です。
しかも執筆は、元ASBJ委員でもある早稲田大学の秋葉賢一教授です。この分野の第一人者からの評価は、率直に言って想定外かつ大きな後押しでした。
■適用指針による「上書き」という制度上の問題
私の寄稿では、適用指針が、会計基準本文の内容を事実上“上書き”している現状は、制度構造上の重大な問題であることを強く主張しました。
今回のQ&Aコーナーでは、まさにこの問題がQのかたちで提起されたのです。秋葉教授はAの中で、適用指針に特例的な取扱いを定めることはその役割を超えると明言しています。
これは、私の制度的問題提起が、ASBJの中枢を経験した方から公式に支持された瞬間とも言えるでしょう。
■私の寄稿の紹介
論考の注釈④では、私の寄稿が、適用指針による会計基準の上書きにより会計基準の階層性を毀損しているという問題に言及したことが紹介されています。後発事象の会計基準(案)に対する他のコメントと比較しながら、会計基準の階層性に関心を寄せている点を強調されています。
また、注釈②では、私の寄稿が、金融商品取引法の財務諸表と会社法の計算書類とで異なる数値を報告した5つの事例を掲載した点にも言及されています。これらの事例は、開示制度間における財務数値の乖離の程度を具体的に示すことで、両制度の単一性を維持しないことの意義を説いたものでした。
これについては、弥永真生先生による「単一性は制度上、必須ではない」との見解も併記されています。つまり、私の主張を制度論的に補強する構成となっているのです。
■いま何が動いているのか? 再公開草案の可能性も
このように、私の問題提起が想定していなかった形で発展したことで、ASBJによる議論が次の段階に入る可能性が出てきました。
仮に、修正後発事象に関する特例的取扱いを「適用指針」から「会計基準本文」に格上げするという動きになれば、これは「再公開草案」の形で議論が再燃する契機となります。
「制度論の話でしょう?」と思われるかもしれません。しかし、違います。これは実務対応の「手続」と「説明責任」を揺るがす論点です。
こうした議論の最新動向をふまえた実務対応を、セミナー形式で詳しく解説いたします。
■発信は、論点の“種まき”である
今回の出来事を通じて、私は強く実感しました。発信は、社会への“問題提起”であり、“共鳴の種まき”であると。
制度の綻びに気づいたら、声にする。
実務のリスクに気づいたら、共有する。
それを続けた結果、誰かが拾い、動きが生まれるのだと。
これからも、実務と制度をつなぐ視点で、発信を続けていきます。