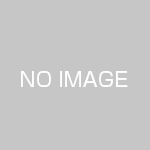学ぶという行為が、いつのまにか「正解を当てるゲーム」になってしまうことがあります。黒板に書かれた答えを目で追い、先生の声を聞き、ノートに写す。「この場合は、こう」と。
その理由は問われない。背景も語られない。ただ結果だけが提示される。それでも試験は乗り切れるでしょう。けれど、そこに面白さはありません。再現性も、応用力も、手の中に残らない。
私がそれに気づいたのは、高校生の夏でした。
河合塾の夏期講習。代々木上原駅から歩いていく校舎へ、親戚の家に泊まり込みで通った一週間。そこで選択したのが、権田雅幸先生の地理の講義です。
蒸し暑い教室で開いたテキストに描かれていたのは、仮想の島でした。南北に細長く、中央に山脈が一本走っている。与えられたのは、緯度と経度といった極めて僅かな情報だけ。
「こんなもの、いくらでも言えるだろう。」
当時の私はそう思いました。地理とは、「この国は熱帯」「この地域は小麦」と覚える科目だと思い込んでいたからです。存在しない島に、正解などあるはずがない。そう思っていました。
ところが、解説が始まると、その考えは崩れていきます。権田先生はこう話したのです。
「この緯度なら、気候区分はここまで絞られる。」
「この経度なら、暖流の影響を受ける可能性が高い。」
「中央山脈があるなら、風上側は多雨だ。」
そのとき、不思議な感覚に包まれました。見えなかった風が、山にぶつかり、雨雲を落としていく。乾いた空気が山を越えていく。答えが作られていくのではない。条件から浮かび上がってくるのです。
その瞬間、自分の理解の浅さを思い知らされました。「覚えれば足りる」と思っていた自分が、少し恥ずかしかった。
さらに衝撃だったのが、気候区分の説明でした。
それまで私は、「熱帯は年中暑い」「乾燥帯は雨が少ない」といった印象で区分を判定していました。設問の文章と頭の中のイメージを照らし合わせる。どこか曖昧な判断です。
ところが、権田先生の解説は違いました。例えば、「最寒月の平均気温が18℃以上か未満か」といった、具体的な数値基準で区分されるのです。(後に、ケッペンの気候区分の判定基準だと知ります。)
“暑い”かどうかではない。“雨が多い”かどうかでもない。数字で線が引かれる。印象で揺れていた区分が、測定できる基準で固定されたのです。誰が見ても、同じ結論に辿り着ける。地理は暗記科目ではなかった。論理の上に立つ体系だったのです。
入門だからといって、過程を隠す必要はない。基礎だからといって、理由を省略する必要はない。むしろ、過程こそが学問の面白さなのだ。この体験は、いまの私の執筆や講義にそのまま流れ込んでいます。
大学で簿記の講師をしていた頃のことです。3級テキストに沿った統一授業のテキストは「この取引ではこの仕訳」と結果を示します。しかし、それでは暗記に走りがち。
私は必ず問いかけます。
「なぜ、この仕訳になるのか。」
「なぜ、そのタイミングなのか。」
配当はなぜ決算時ではなく株主総会決議時に計上するのか。会社法のスケジュールを一度、図にしてみる。その流れを追うと、翌期計上であることが自然に見えてきます。
給与の仕訳も同じです。税金や社会保険の制度や納付の流れを説明すれば、「預り金」という言葉が単なる記号ではなく、資金の動きとして感じられます。
結果ではなく、構造を見る。
暗記ではなく、再現する。
サステナビリティ開示でも、会計基準でも、保証制度でも、私は同じことをしています。条文を並べるのではなく、なぜその設計になっているのかを辿る。制度の背後にある思想を理解すれば、新しい基準が出ても慌てずに済みます。
あの仮想の島がなければ、私はいまの教え方をしていなかったかもしれません。
もし学ぶことに、もう一段深い楽しさがあるとしたら、それは答えを知ることではありません。自分の力で、もう一度、そこへ辿り着けること。そのとき、知識は情報ではなく、力になります。
再現できる知識だけが、本物になる。そして私は、その瞬間に立ち会うために、執筆や講義を行っています。