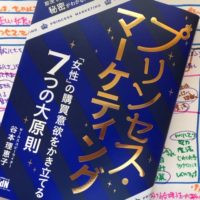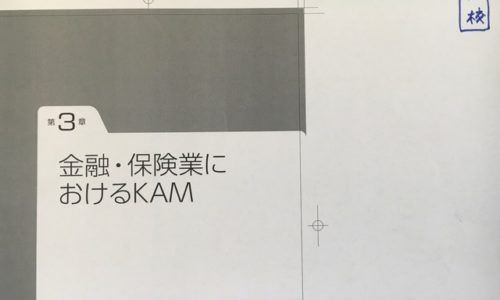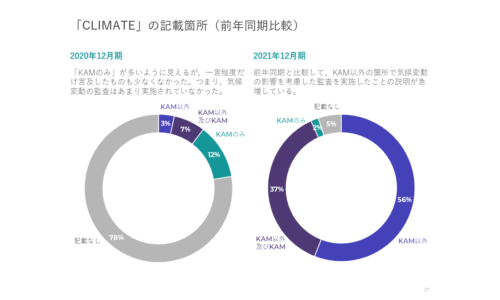ビジネスパーソンとなってから使う機会はあるのに、意外と作り方を学んでいないもの。頻繁に使う人でも、見よう見まねの独学も結構見かけます。
それは、プレゼンテーションのスライド資料。パワーポイントやキーノートなどで作りますよね。
スライドの作り方を体系だって学んでいる人は少ないから、いったん悩みだすと心配になることもあるようで。今日も、そんな後輩クンがボクのところに来て、「ちょっと、アドバイスをいただけますか」とパワーポイントのスライドの相談を受けました。
その悩みとは、スライドのタイトルの付け方。仮に、最も大きい見出しが「Ⅰ 背景」、次の大きな見出しが「1 問題の所在」であったとします。
後輩クンはこれまで、各スライドに「1 問題の所在」と付したうえで、それに関連する内容のスライドを何枚か作った次に、「2 ~」と続けていました。
このときに、「1 問題の所在」だけでは受講者が何の説明かがわからなくなるかもしれないと心配しました。そのため、「Ⅰ 背景」と「1 問題の所在」とをスライドのタイトルにうまく配置したいといいます。
あなたなら、どうする?
ボクも昔は、同じようなスライドを作っていました。後輩クンのように受講者の便宜を踏まえて「Ⅰ 背景」をどう配置しようなんて考えることなく、何枚ものスライドに「1 問題の所在」と付したタイトルに疑問を持っていませんでした。
12年ほど前に、あるプロジェクトでコンサルタントのかたとご一緒したときのこと。ボクが作ったスライドをレビューしてもらった結果、こう言われました。
「同じタイトルを付したスライドを何枚も作るなんて、センスがない」
その頃は、パワーポイントを使いだして1年程度。確かに、何かで学ぶことなく、パワーポイントをいじっていました。なんとなく、感覚で。
しかし、プレゼンテーションの経験豊富なそのコンサルタントは、作り方や魅せ方を研究し実践してきた人。再現性ある方法論を持っていたのです。
レビューを受けたときには、「そうか~、同じタイトルを付すのは変なんだ~」とテクニックとして受け取っていました。今なら、一枚のスライドに込めるメッセージはひとつであること、また、そのメッセージをスライドのタイトルに付すことだと理解できます。
ただ、プレゼンテーションのスライドの作り方に何か方法論があることに気づいたボクは、その後、書籍を読み漁り、また、上手なプレゼンテーション資料を見まくりました。女性誌に連載されていたホイチョイ・プロダクションズさんのコラムからも、デザイン的に洗練された図表も研究したものです。
そんな懐かしさを覚えながら、後輩クンにこう言いました。
「受講者への配慮は良いね。ただ、この研修資料は、何も説明せずに渡すものじゃない。説明を聞きながら見ている資料でしょ。『Ⅰ 背景』の仕切りページがあるのだから、それ以降の説明は背景に関するものだと受講者は理解できる。だから、それをわざわざ配置する必要はないんじゃないか」
「それに、もっと言えば、『1 問題の所在』というタイトルを何枚ものスライドに書くことをやめたほうがいい。ここには、そのスライドのメッセージを書くのが良い」
なーんて12年前に受けた指摘を、あのコンサルタントのようにボクは後輩クンに伝えた次第で。熱心に聞いていたので、きっと良い資料を作るんだろうなあ。
「少しのことにも、先達はあらまほしき事なり。」とは、徒然草に書かれた言葉。一度、ボクが学んだスライドの作り方を整理して伝えてみようかな。
P.S.
スライドのタイトルに参考になるかと思って手にしたのが、この本。まだ、神田昌典さんのお名前を存じ上げていなかった頃。
これがきっかけで、ボクはダイレクト・レスポンス・マーケティングに興味を持っていくのですが、それはまた、別の話。
・ジョン・ケープルズ(著)、 神田昌典(監訳)『ザ・コピーライティング―心の琴線にふれる言葉の法則』(ダイヤモンド社)