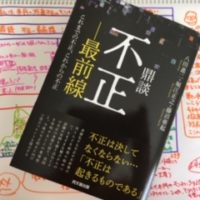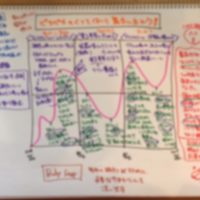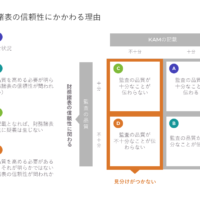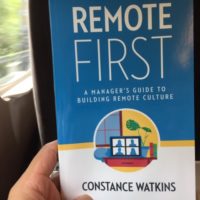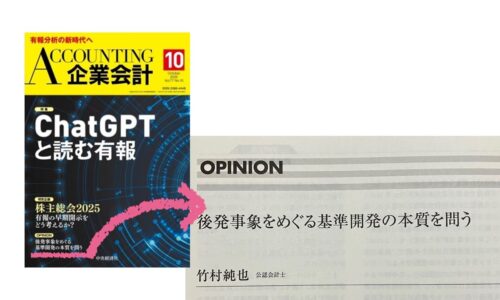以前、知人と話していたときに、組織の人は、次の2つのタイプに分かれると話し合っていました。
ひとつは、「私は、この業務をやってみたいです」と話す人。
もうひとつは、「私は、この業務がやりたいです」と話す人。
ボクも知人も、「やってみたい」と話す人を信じないことで一致。なぜなら、そこに本気度が感じられないから。
「やってみたい」と話す人は、その業務をちょこっと、かじってみたいだけ。なので、ちゃんとできるように教育しろだとか、成長できるように業務を用意しろだとか、とにかく誰かに手ほどきしてもらうことを前提にします。まだまだ大人が面倒をみないといけない、子どものまま。
自分で何とかやり遂げる覚悟がないため、本気度が相対的に低い。そんな人には、その業務を本気で獲得してきた人からは、仕事を任せられない。当たり前ですよね、なにもかもお膳立てされなければ動かないなら、わざわざその人に仕事を依頼しません。
一方、「やりたい」と話す人は、その業務について自ら開拓していく覚悟がある人。たとえ前例がなくても、必死に知恵を絞って最善の努力をします。
たとえその業務が差し迫っていなくても、関連する書籍で学んだり、セミナーに自費で参加したりと、お声がかかるときに備えて準備しているのです。
普段からそういう姿勢のため、どんな業務でも着実に成果を出すことが多い。そのため、業務を獲得した人は、その人に安心して仕事を依頼します。これも当たり前の道理。
例えば、ある会計士が、税務を「やってみたい」と話していたとします。
すると、その人は、ちゃんと税務申告できるように手ほどきされることが当然と考えます。また、自分の業務レベルにあった仕事を誰かが目の前に差し出してくれるとも思い込んでいます。
そのくせ、自身の確定申告はしません。所属する組織に必要な資料を提出して、年末調整をしてもらうのです。自分の税務申告ではなく、他人の税務申告で学ぼうとします。
これ、税務申告を依頼する人にとっては、えらい迷惑なこと。そんなの自分の税務申告でやってくれ、という話。誰だって実験台にはなりたくない。
それに対して、税務を「やりたい」と話す人は、所属する組織に対して年末調整に必要な資料を提出することなく、自身で確定申告します。たとえ給与所得だけであっても。他人の税務申告を踏み台にせず、自分の確定申告でトライアルしてみるのです。
失敗したら、自分の責任。そんな覚悟を決めて仕事をしているのです。こうした二人を比べたら、どちらに仕事が任されるかは明らか。
だから、ボクや知人は、「やってみたい」と話す人を信用していません。失礼な姿勢では相手にされないのです。
これは、世代の価値観とかいう話ではない。責任や覚悟の問題。仕事を依頼する立場になれば、すぐに理解できること。
本気で「やりたい」仕事があるなら、そのことについて必死に学んでいれば大丈夫。きっと誰かが探してくれます。業務を獲得した人だって、ちゃんと仕事をしてくれる人に任せたいのですから。
えっ、自分がやりたいことをどうやって理解してもらえるか、って。
それも問題ない。だって、ある業務に備えているなら、普段の会話からそれが漏れてきます。すると、「あの人、話の端々に税務がでてくるな」「あの人は、M&Aのニュースに興味があるようだ」などと、あなたの関心に自然と気付いてもらえます。
もし、ボクらのような想いの人が相手なら、「やってみたい」と話した瞬間に結果がでてしまうので要注意。大人が仕事の相手に選ぶのは、大人だけなのです。