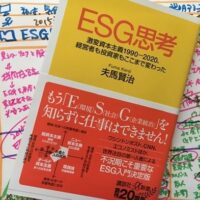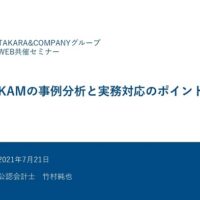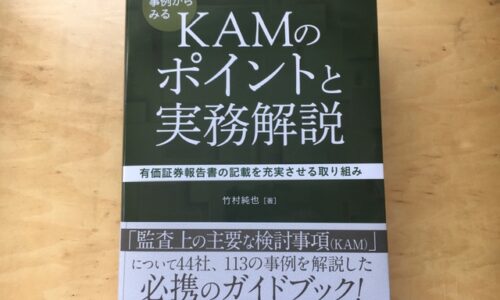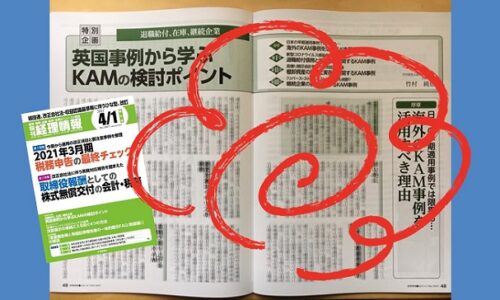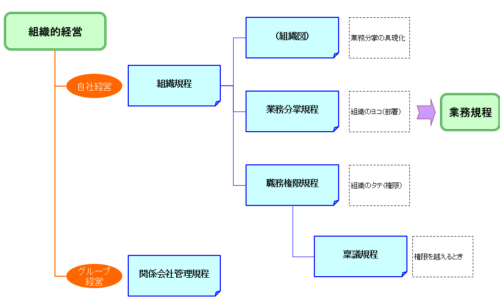文章をより良くするために必要なこと。それは、削ること。文章を書き上げた後の推敲の段階で、伝えたいメッセージに不要なものを削ぎ落とすのです。
せっかく、ここまで書いたのに消してしまうのはもったいない、と思うかもしれません。でも、それは書き手の都合。読み手にとっては、そんな苦労など、どーでもいい話。それを優先してメッセージが伝わりにくくなるのは本末転倒です。
今日も、「ここまで書く必要があるのだろうか」と感じさせる文章を見ました。それは、不正調査報告書。この数日、不正会計の界隈で少し話題になっています。ただ、話題になっているのは、不正会計の手口ではなく、不正会計を行った会社の経営者の女性関係。
この調査報告書では、経営者の資質全般について検証する目的で、その女性関係まで調査しています。経営者のプライベートの携帯を調べた結果として、1年2ヶ月の中で、50件以上の送信をしている相手方の名称と送受信件数を図表にまとめています。
正直、この部分を読んだときには、「ここまで要る?」と首をかしげました。仮に経営者としての資質がないことを裏付ける目的であったとしても、図表化するほどの重要性はないのではないかと感じました。
これでは、調査報告書が伝えたいメッセージが届きにくくなるのではないかと心配。実際、この報告書が話題になっているのは、経営者の女性関係をまとめた部分。歪んだ形で世に広まっている印象を受けます。まるでワイドショーの報道のように。
ボクも不正調査の補助業務に携わった経験がありますが、とにかく時間がありません。短い時間の中で手掛かりを得て、調査を行い、報告書を仕上げないといけないのです。その苦労は実体験として理解しています。だからこそ、ワイドショーのような取扱いによって、本筋のメッセージがぼやけるのがもったいない。
どうして、この部分を掲載したのだろうと勝手に邪推してみました。このようにワイドショー的に広まれば、会計や不正についてよくわからない人でも「あの経営者はけしからん」という印象を与えることができます。すると、経営者の座から引きずり下ろすことも容易になる。
そこで、それを望む人たちが、不正調査をした人たちにネタを与え、また、それを記載することを望んだんじゃないかと。あっ、これもワイドショー的な発想ですね。第三者としての立場を保持する不正調査の委員の方々が、そんなことに加担するハズがありません。
そんな風に邪推したのは、身近でワイドショー的な扱いに直面したから。最近、こいつは叩いても問題がないヤツだと認識した途端に、徹底的に叩くような風潮を見かけます。それがテレビの画面や週刊誌の紙面の向こう側の世界でとどまっているだけでなく、こちら側の世界にまで及んでいるのです。
先日も、ある場で、ある人が別の人を猛烈に批判し始めたのです。こいつは叩いても問題ないと、その人は判断したのでしょう。随分と上から、偉そうに説教しだしたのです。ただ、その説教には出口がない。何も解決せずに、ねちねちとイジメはじめようとしたのです。同席していたボクは、「やめろ」と止めます。「それじゃ、週刊●●と同じだろう」と。
何の関係もない人が、正義ヅラを振りかざすのは、良くない。そんなワイドショー的な振舞いが身近なところで生じたのがショックでした。
あれ、何の話でしたっけ。そうそう、文章をより良くするなら、伝えたいメッセージに不要なものを削ぎ落とす話でしたね。ほら、ボクの身近な話を付け加えたおかげで、そのメッセージがぼやけたでしょ。では、次の文章を復唱して、覚えましょう。
届けましょう、伝えたいメッセージを。削りましょう、不要な話を。