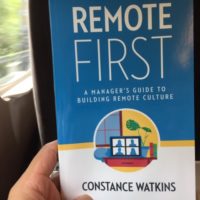本の中で、本文の前に読まれがちな箇所。昨日のブログ「本の「はじめに」は、セールスレターなんだよ」で説明したとおり、「はじめに」に最初に目が通されやすい。
その「はじめに」の次に、あるいは、それと同じくらいに本文よりも前に読まれるのが、「おわりに」の箇所。ここも著者としては軽く扱えない場所。
この「おわりに」を本文よりも前に読む人の期待は、ただひとつ。それは、本文の要約を知りたい、ということ。ここに本文の要約が書かれていることが多いため、ここを先に読んでおけば、本文の内容が大まかにつかめることがあるからです。
そんな性質があることから、ボクはたまに本を後ろから読むことがあります。最後のページを開き、段落ごとに読んでいく。まずは最後の段落を、次はその手間の段落を、という感じで。
本を書く理由には、ある主張を理解してもらいため。その主張に納得してもらうために、数百ページもかけて説明している。定義だったり、具体例だったり、似たようなものとの比較だったりと。それらの解説を経たうえで、主張というゴールに辿り着く。つまり、ゴールは最後に置かれているのです。
以前に、とある本に対して、後ろから読む方法を使ったときに、すごい経験をしたことがあります。最後の段落を読んだところ、「この本で一番言いたかったことは~である」と書いてあったのです。
すごくないですか、この瞬間に著者の主張を理解できたのですよ。200ページ以上あったと記憶している本であるにもかかわらず、著者の言いたかったことを、僅か数秒でつかめたのです。この主張を納得するための材料が本文に並べられているため、論理構成が気になるところを確かめていくだけ。めちゃくちゃ早く本を読むことができますよ。
このように、著者が言いたいことが最後に書いてある構成を前提とすると、人はここを先に読んでおきたい衝動に駆られます。だからこそ、「おわりに」も本文よりも前に読まれがちなのです。
これは、セールスレターでも同じ現象があります。よく、セールスレターの末尾に、「追伸」や「P.S.」というパーツがあります。読者は、セールスレターを必ずしも順番に読む人ばかりではなく、本文を飛ばして「追伸」を読みにいく人もいるのです。これもきっと、本文の要約を期待してのことかもしれません。
しかし、セールスレターの場合には、「追伸」の部分には本文の要約は書かれていない。書かれるのは、ゴールの後押し。セールスレターのゴールとは、そこで紹介する製品やサービスを買ってもらうこと。購買を促すような、次の文章が書かれています。
「お席の数は限られているため、お早めに確保してください」
「お申込みは、○月○日まで」
「この特典が得られるのは、あと○日」
このようにセールスレターの追伸では、本文の要約ではなく、本文を確認したくなるような文章で読者の興味をそそるのです。この手法は、本の「おわりに」でも使えますね。つまり、本の「おわりに」も、要約じゃなくて、PSのように本文を振り返えさせる内容を書くのが良い。
これは会計や監査の専門書に多いのかもしれませんが、「おわりに」がない本が多い。ボクもこれに倣って、あまり「おわりに」を書いたことがありませんでした。しかし、これだと本文がプツンと終わってしまうため、どうも読後感が良くない。どうしようと悩んでいたときに、セールスレターの「追伸」が思いついたのです。
そこで、直近の単行本『M&A会計の実務』(税務経理協会)では、「おわりに」を書いてみました。もちろん、本文の要約は直接的にはしていません。その代わりに、本文の内容に興味を持ってもらえるような本文の特徴を説明しました。
ボクとしてはしっくりとしたのですが、あなたはどう感じたでしょうか。良ければ、ご感想をお寄せください。
P.S.
今後、本を書く際には、「おわりに」は必ず書くつもり。それは、セールスレターの「追伸」のような効果を狙って。次の本を出すときには、そこにもご注目くださいませ。