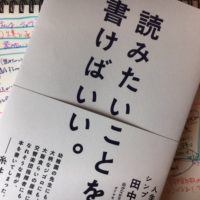セミナーは、2種類に分かれるのをご存知でしょうか。1つは、受講者に聞いてもらえるもの。もう1つは、受講者に聞いてもらえないもの。
あなたが何かを教える立場にあるなら、話す内容をちゃんと聞いてもらいたい。せっかくはなしているのだから、ね。
実は、あるアプローチを使うと、受講者に聞いてもらいやすくなります。あなたの準備も報われるのです。
セミナーで大事なのは、初っ端。始めが肝心なんです。結論から言えば、ここで関心を惹かないといけない。
なぜなら、関心を惹けなかったときのリカバリーが大変だから。いったん、そっぽを向かれた受講者をこちらに向かせるのは、そう簡単なことじゃない。
まだ、受講者が自分の意思で参加を決めるセミナーだと、その失敗は少ない。すでに関心や興味があるからこそ、参加の申し込みをしているから。
これが、組織の中で強制的に受講するセミナーだと、関心のある人もいれば、ない人もいる。ときには、受講者のほとんどが関心を持っていないこともあります。だからこそ、最初に関心や興味を持ってもらえないと、悲劇。
先日、ボクか受講していたセミナーは、この初っ端を失敗していました。細かいところでは、全体構成を説明していなかったり、その必要性を丁寧に説明できなかったりと、気になる点はいくつか挙げられます。しかし、最大の失敗は、セミナーの始めで関心を惹けなかったこと。
受講者にしてみれば、自分への関わり方が分からないため、自分ごとにならない。他人ごとであるから、聞く耳を持たない。これが、組織の中で強制的に参加させられるセミナーで講師をする場合に忘れてはいけない点。
すると、そうしたセミナーでは、冒頭で、受講者に関心を持ってもらうように仕掛ける必要があります。ここで、2つのアプローチが登場します。
これは、学習や成長について、意識的か無意識的か、また、できるかできないかの軸で捉える考え方に基づくもの。
最初は、無意識的で、かつ、できない状態。そもそも知らないため、できる訳もない。
次は、意識的だけどできない状態。そのことを知ってはいるものの、それを実施することができない。
その次は、意識的にできる状態。それをするための注意点に気をつけながらだと、できるもの。
最後は、無意識的にできる状態。それを意識せずにできるようになっている。
これが、学習や成長のレベルの話。これをセミナーで関心を惹きつけることに照らすなら、最初の2つのレベルをどうクリアするか、ということ。そのためのアプローチが、次のとおり。
1つ目のアプローチは、セミナーで呼びかけたい内容をどうやって知ってもらうかにフォーカスします。「〜をご存知でしょうか」と呼びかけます。
例えば、速読の方法を呼びかけるなら、「僅か◯分で200ページのビジネス書を理解できる速読法をご存知でしょうか」という感じ。
速読することが身近ではない状態のときには、できるかどうかの前に、そんな方法があることを知ってもらうことが必要。なので、「ご存知ですか」と問いかけるのが良い。
2つ目のアプローチは、セミナーで呼びかけたい内容がどうやったらできるようになるかにフォーカスします。「これによって、〜ができるようになります」と呼びかけます。
例えば、速読の方法の場合には、「この速読法によって、今までの◯倍も早く本を理解できるため、同じことをするには◯分の1で済みますし、別のことをするには◯個のことができるようになります」という感じ。
速読の方法はすでに知っているため、それができるようになりたいと思ってもらう必要がある。そうして初めて、「その話を聞きたい」と学習モードになるのです。
そんな2つのアプローチを組み合わせたなら、最強じゃありませんか。なので、今回のブログ記事にも使ってみました。ここまで読んでいるということは、その効果を証明されたということ。使えるでしょ、これ。