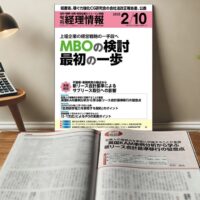人は、お金が絡むと、詩人になる。ホラ、競馬でも、株式投資でも、やたらと格言があるでしょ。
競馬なら、「最終レースは買うな」「発走前に勝負の5割は決まる」「1番人気はいらないから1着だけ欲しい」など。株式投資なら、「もうはまだなり まだはもうなり」「二番底は黙って買え」「相場のことは相場にきけ」など。ビジネス書のタイトルになりそうな勢いですね。
そんなせいか、M&Aの世界でもそう。使われる用語が、経済用語のような堅苦しいものではなく、キャッチーなものが多い。会計士試験の受験のときに、経営学のテキストに列挙されていた用語を見たときに、そのページだけ異色に映っていたことを今でも覚えています。例えば、こんな感じ。
「パックマン・ディフェンス」
「ホワイトナイト(白馬の騎士)」
「ゴールデンパラシュート」
「ポイズンピル」
ね、随分とキャッチーでしょ。これらはM&Aの中でも、買収を仕掛けられたときの手法の名前。こんな名前を思い出したのは、芸能プロダクションの騒動があったから。
非上場の芸能プロダクションで、経営サイドと現場サイドとがぶつかっています。現場サイドからは現経営陣の徹底を求める声も挙がっている。まったくの架空の話として、「もしも買収話に展開したら」という設定で、これらの用語を学んでいくのが今回の趣旨。
企業の内部で経営サイドと現場サイドが揉めてしまうと、事態を収束するのが大変。内部で何とかできれば良いのですが、組織特有の「バランス」の問題があるため、足の引っ張り合いにもなりかねない。
内部でダメなら、外部を利用すればよい。企業の外部が手を差し伸べることによって、このゴタゴタが丸く、かつ、迅速に収まるのなら、選択肢の一つになり得ます。もちろん、それが最適かどうかの保証はありませんけどね。
で、どこかの企業が、この非上場の企業を買収しようとするシナリオを考えてみます。シンプルなのは、同業の企業が買収するケース。もっとも、ネットでのコンテンツを充実させる観点から、インターネット企業が名乗りを挙げるケースもあるでしょう。いずれにしても、どこかの企業が、ゴタゴタしている企業を買収するとしましょう。
まず、「パックマン・ディフェンス」とは、買収されようとしている企業が、反対に買収しようとしている企業に対して買収を仕掛けることをいいます。
ゴタゴタしている企業が、外から口を出してきた企業に対して、「うるさいわ、ワレェ」と逆に飲み込んでしまうのです。これが、テレビゲームのパックマンのひとコマを彷彿させるために、こう呼ばれます。
次に、「ホワイトナイト(白馬の騎士)」とは、買収しようとしている企業とは別に、買収しようとする企業が現れることをいいます。最初に買収を仕掛ける企業が、買収されようとしている企業の経営サイドにとって敵対的な関係。これに対して、新たに現れた買収しようとする企業は、まだ友好的な関係にある。
買収をもちかけられて「あいつのところに吸収されたくない」と思っているところに、「あんたのところなら、お願いしますわ」と救いの手を差し伸べるかのような相手が目の前に現れる。それが、まるでお姫様の前に登場した王子様のように見えるために、こう呼ばれます。
また、「ゴールデンパラシュート」とは、買収されようとしている企業の経営者の退職金を多額に設定しておくこと。敵対的な買収では、買収された企業の経営者は、買収後に解任されることがあります。買収する企業としては、「お前の経営じゃ、アカンで」と考えたからこそ、買収に至っているから。
そこで、買収される前に、解任させる経営者が解任される場合には多額の退職金を支払う条件としておくのです。すると、買収が成功しても、多額のキャッシュアウトが生じることになるため、買収にあたって支障にさせる効果が得られます。買収される企業の経営陣が、大金を背負って企業から抜け出すさまから、こう呼ばれます。
経営陣への退職金でなくても、買収後に多額のキャッシュアウトが生じる事態だと、ゴールデンパラシュートと同じ効果となりますね。例えば、多額の違約金が生じるとか。
最後の「ポイズンピル」とは、買収されようとしている企業の経営陣に新株予約権をあらかじめ与えておいたうえで、買収しようとする企業が現れたときに、安く権利行使できるような条件を設定しておくこと。発行する株式の総数を増やすことで、買収しようとする企業が買い取った株式の比率を下げるのです。
例えば、買収しようとする企業は「これで、90%を押さえたぞ」と思っていたら、新株予約権を行使されたことで、30%に届いていなかった、という状況。せっかく買収できたと思っていたところ、蓋を空けたらまだ買収できないために、毒が回ったように見えるため、こう呼ばれます。
これが、M&Aでのキャッチーな用語。どれも、見事に表現していますよね。ボクが『M&A会計の実務』(税務経理協会)を執筆していたときに、これらも盛り込もうと考えていました。ボクの受験時代の経験のためか、これらの用語がページに出てくるだけで、なんだか楽しそうになってくるから。
ところが、説明のストーリーも変わり、ページ数も変わることから、別の機会にとっておくことにしました。その機会が、このブログというワケ。では、あなたに素敵な王子様や王女様になってもらって、ホワイトナイトを見せてくれるのを楽しみにしています。