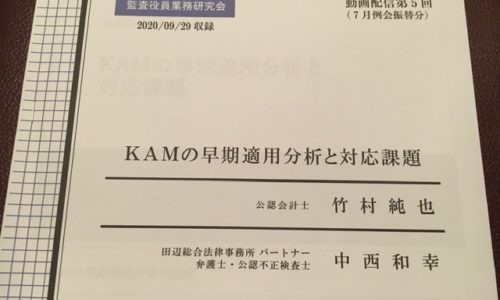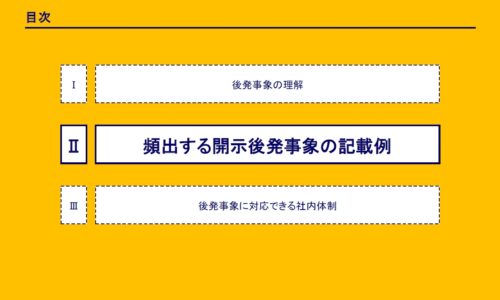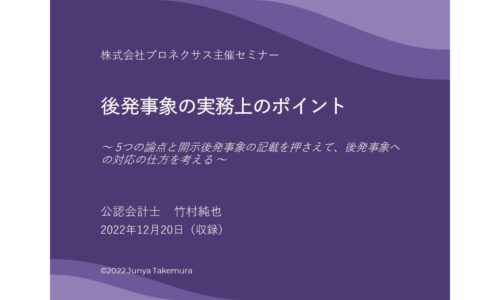それは、1997年3月28日のことだった。映画『Shall we ダンス?』が、地上波テレビで初上映された日。ボクはこの映画を見て、心の底から確信したのです。
「自分には絶対に、社交ダンスの才能がある」と。
社交ダンスを舞台にしたこの映画は、1996年に公開されました。その年の日本アカデミー賞では、史上最多の13冠を獲得したほどに人気となった映画です。最優秀作品賞は『Shall we ダンス?』、また、最優秀監督賞と最優秀脚本賞は周防正行サン。さらに、主演を務めた役所広司サンと草刈民代サンは、それぞれ最優秀主演男優賞と最優秀主演女優賞を得ています。
一方で、最優秀助演男優賞となったのは、竹中直人サン。言わずと知れた名俳優。テレビの世界に出始めたときには、俳優よりもコメディアンとしてのほうがメインだったかと。竹中直人サンの「笑いながら怒る人」という芸は、当然にマネしましたよ。
そんな竹中直人サンは、映画の中では、主人公の会社の同僚の役。ラテンダンスで世界的に有名なドニー・バーンズ氏に憧れている設定でした。劇中でラテンダンスを踊る際には、大きな身振りで情熱的に身体をクネクネさせた様子が、笑いを誘います。
その踊りは、滑稽という意味で目を引いただけではありません。なぜだか、「これ、きっと踊れる」という自信も生じたのです。
ちょうど当時の職場に、社交ダンスの大会に出場している女性の先輩がいらしたので、この映画や社交ダンスの話題で盛り上がりました。ボクが社交ダンス、特にラテンダンスの才能がある気がすると話したときには、優しく微笑みながら、「竹村くんも、始めなよ~」と大人の対応をしてもらったものです。
もちろん、踊った経験もなければ、レッスンを受けたこともないため、今すぐに踊れるものではない。それは十分に承知しています。しかし、センスがあると強く確信しているため、ある程度のレッスンを積むと、イケそうな自信があるのです。
こんなときに、「経験がないから自信がない」「やったことがないから無理」と、何もすることなく諦める人がいます。根拠がないから自信がないというのです。
しかし、「自信」という文字は、「自ら信じる」と書きます。根拠はなくても良い。根拠があるなら、自信を持つ必要はないワケで。根拠がないからこそ、自らを信じなければならない。
だから、ボクがラテンダンスの自信を持っても問題はない。あなたが何かについて自信を持っても、同じく、何の問題もない。堂々と自信を持てば良いのです。
ところで、作家の中谷彰宏サンは、いくつかの著書の中で、社交ダンスを学んでいるとお話しされています。また、別の職場では、ラテンダンスのひとつである「サルサ」を嗜んでいる友人もいました。こうして振り返ると、周りはラテンダンスで囲まれている。
これらは、そろそろ始めなさい、というサインでしょうか。”Shall we dance?” と。