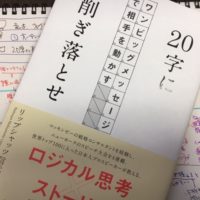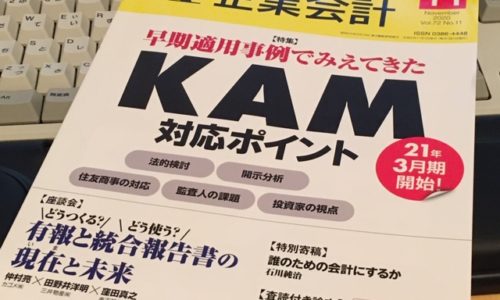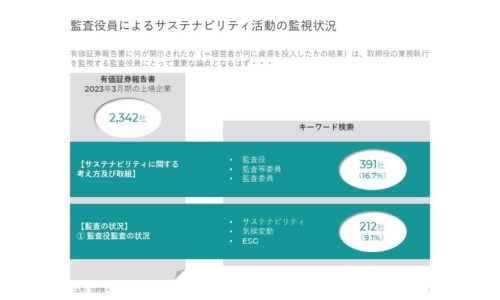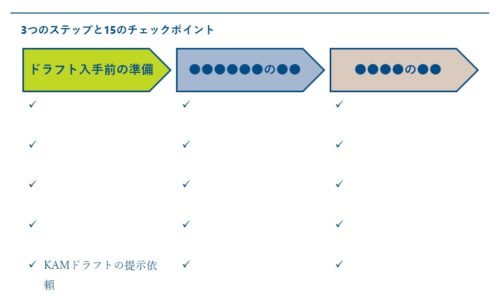手放すと聞くと、ポジティブな印象を持ちます。きっとそれは、マサチューセッツ工科大学上級講師のC・オットー・シャーマー氏による『U理論』(英治出版)の影響を受けているから。
人によっては、何かを失う側面にフォーカスすることで、マイナスのイメージを持つことがあります。そういう側面もあるのでしょうが、そればかりではない。
U理論とは、ある課題に対して、未来から解決法を学ぶもの。といっても、水晶玉を持ち出すのではなく、深く理解することによって、解決した未来が出現するというもの。
その未来が出現する前に行うステップが、「手放す」(レッティング・ゴー)です。散々考え抜いた後に、それへの固執を捨てることを指します。こうして手放すことで、未来を出現させるのです。
ビジネスでは、仕事を手放す局面がいくつかありますね。例えば、部門内でのローテーションもあれば、部門を超えた配置替えもある。また、会社を超えての出向や転籍もあれば、会社からの離職もある。
本人の望む、望まないにかかわらず、仕事や業務を手放す局面に直面することがあるでしょう。ボクも、今日、ある業務を手放しました。
しばらく、ボクの手元で抱えていた業務。早く着手しなければと思いながらも、なかなか気が乗らない。つい、他の業務を優先してしまう。
ここで、立ち止まって考えてみました。これは、「手放す」サインなのではないかと。
U理論に基づく整理ではありませんが、仕事や業務を手放すことで、手放す側にとって良いかどうか、手放されたそれを引き受けた側にとって良いかどうかが考えられます。これらの組み合わせると、次の4つのケースになります。
1つ目は、手放す側にとって良いケース。仕事や業務を手放すことで、新しいことに取り組めるため、本人は次の成長フェーズに進むことができます。
その仕事や業務としても、他の人でも回っていくため、持続可能性があります。後継者問題に悩むこともありません。
2つ目は、引き受けた側にとって良いケース。後進を育成する意味が大きいでしょう。チャンスが得られなかった仕事や業務をできるようになると、社会的に価値が付加されます。
3つ目は、どちらも良いケース。いわゆる、Win-Winってやつ。
で、4つ目は、どちらも悪いケース。手放す側も引き受けた側もダメになるような状態。手放した側が新しいチャレンジをすることもなく、引き受けた側も成長することもないようでは、何も価値が付加されない。つまりは、意味がないのです。
この4つ目のケースは、まだ、あなたが手放してはいけないとき。あなたが利己的な視点で、単に楽をしたいとか、何だか嫌だとかという観点から、状況を回避したいときだから。
とはいっても、手放すのが良いケースなのか、あるいは、手放してはいけないケースなのかを見極めるのは難しい。そんなときには、いきなり手放すのではなく、少しだけ手放してみるのがよい。ゼロから100ではなく、10とか20といった一部分だけを手放すのです。
その結果、仕事や業務が回りだすなら、それはもう、あなたが抱える必要はありません。残りの部分も徐々に手放していきしょう。
案外、あなたが思っているよりも、何とか回っていくもの。たまには、周りの人を信じてみてはいかがでしょうか。手放しても回っている光景を目の当たりにすると、爽快ですよ、ホント。